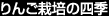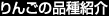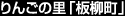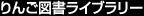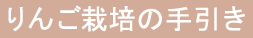|
| 12.収穫と貯蔵 |
|
1) 収穫時期の決め方
りんごは十分味をのせて「旬の味」として供給する一方、貯蔵りんごの供給も重要である。収穫時期は果実品質、貯蔵性に大きく影響するので収穫時期の決め方は慎重に行う。品種別の収穫時期は下表が目安となるが、地域、その年の気象、栽培管理、台木(「わい化栽培収穫」の項を参照)、樹勢などによって多少のずれがあるので果実の熱度を調査して決定する。
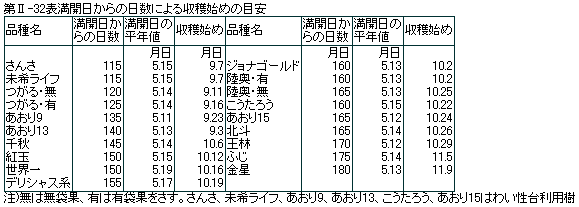 |
|
2) 熱度調査の方法
(1) りんごの採取
調査樹はできるだけ樹勢の平均釣なものを2樹選ぶ。1樹の南〜西両側と北〜東面側から大きさ、着色の平均的な果実を各々2個程度採取する。
(2) 果肉硬度(硬度計のない場合は省略)
果実硬度計は7/16インチプランジャーを使用する。相対する2か所の赤道部分の果皮を薄く剥いで測定する。
(3) 糖度
陽向面と陰向面の二か所を測定して平均値をとる。果肉切片は果皮部分だけでなく果心部までナイフを入れて半円形にとり、果皮と芯をとり除いて搾汁し、屈折精度計で測定する。糖度計は温度による誤差があるので、測定前に水で0点調整してから行う。
(4) 蜜入り程度
果実を横断(種が切断されるように)して判断する。
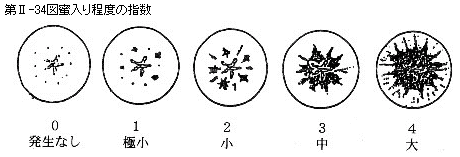
(5) ヨードでんぶん反応
蜜入りを判定後、果実の横断面にヨウ素・ヨウ化カリウム液(水100mlにヨウ化カリウム5gを溶かし、さらにヨウ素を1g溶かす)を塗り染色反応(面積)をみる。判定基準は次のとおりであるが、品種により染色模様が違うので、染色面積を合計して判断する。
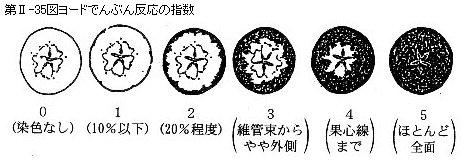
(6) 食味
〔指数〕5:非常に良好 4:良好
3:品種特有の風味が出始めた時期で、やや未熟ではあるが、まあまあ食べられる。
2:未熟であり、食用としてはやや不適
1:未熟であり、食用としては不適
(7)酸度
100mlの三角フラスコに20〜30mfの蒸留水を入れ、それに果汁5mlを取り、フェノールフタレイン指示薬(1%)を2〜3滴加え、N/10水酸化ナミリウム水溶液(ファクターのわかっているもの)で滴定し、それを果汁100ml中のリンゴ酸含量に換算する。
[換算計算の仕方]
リンゴ酸含量(g/100ml)=a×F×0.0067×100/5
a:N/10水酸化ナトリウム水溶液の滴定値(ml)
F:N/10水酸化ナトリウム水溶液のファクター
(8) その他
上記の方法で大体の熱度判定ができるが、落果の状況、着色の進み方なども参考にする。 |
|
3) 品種別収穫、貯蔵上の注意点
(1) つがる
ア 平年の収穫始めは無袋果が9月11日、有袋果は9月16日ころからである。
イ 熟期が揃わず収穫前落果を生じやすいので地色、着色をみて2〜3回くらいに分けて収穫する。
ウ 収穫後高温下に置くと果肉の軟化、油あがりが早く、また、茶星、ビターピットの発生が多くなるので迅速な冷却が望ましい。
エ 販売期間は10月末までに終了するのが望ましい。
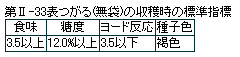
(2) デリシャス系
ア 平年の収穫始めは、普通冷蔵用が10月19日ころからである。
イ 収穫時期が早すぎると貯蔵やけ、遅すぎると内部褐変が発生しやすいので、特に適期収穫が大切である。
ウ 蜜の多く入った果実は軟質化しやすく、また、内部褐変(蜜褐変を含む)を起こしやすいので、早めに販売する。
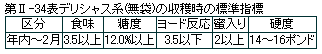
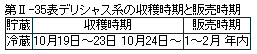
(3) ジョナゴールド
ア 平年の収穫始めは10月20日ころからである。
イ 収穫時期が早すぎると酸味が強すぎるばかりでなく、貯蔵中にビターピットの発生がある。遅すぎると無袋果は特に果面の油あがりが多く、貯蔵中の欧化、ゴム病の発生が多くなる。
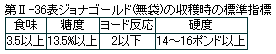
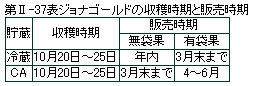
(4) 陸奥
ア平年の収穫始めは有袋果が10月20日、無袋果は10月25日ころからである。
イ無袋果は熱度が揃わず、また収穫前落果も多いので地色のあがりをみて、3回くらいに分けて収穫する。地色は黄緑色(濃緑色1〜黄色5とした指数で3〜4)が品質、貯蔵性とも優れている。
ウ収穫時期が早すぎると、渋みが強く食味が劣るばかりでなく、貯蔵中にビターピット及び貯蔵やけ発生の心配がある。遅すぎると、ゴム病が発生しやすい。
エ有袋果の果面に水浸状に出る蜜入りは軟質化が早く、ゴム病に進展するので早めに販売する。
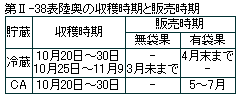
(5) 北斗
ア平年の収穫始めは10月20日ころからである。
イ熟期が揃わず収穫前落果を生じやすいので地色、着色をみて2回くらいに分けてすぐりもぎをする。
ウ完熟あるいは完熟に近い状態で収穫し、収穫後はできるだけ早く冷蔵庫に搬入する。収穫時期が早すぎると貯蔵後にビタ一ピットの発生、収穫が遅れると果肉の軟化、酸味抜けによる食味低下、貯蔵やけの発生が多くなりやすい。貯蔵やけは未熟型と異なり陽向面に発生しやすく、1月以降に多発する傾向がある。
エ早い時期から地色のあがりすぎたもの、大王、がくあ部の広すぎるものなどに心かびの発生が多い傾向にあるので選果はていねいに行う。また、着色が劣り、地色の上がらないものは、加工に回して生食用として販売しないことが肝要である。
オ北斗は味を身上とする品種であり、貯蔵やけの発生を考慮すると、年内に販売を終了することが望ましい。
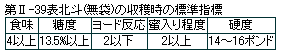
(6) 王林
ア平年の収穫始めは10月29日ころからである。
イ収穫時期が早すぎると貯蔵後にビターピット及び貯蔵やけの発生が心配される。
ウCA貯蔵のガス組成は酸素濃度が低いほど、貯蔵やけ防止効果及び鮮度保持効果が高い。
エ出荷時に健全果でも消費地において10℃以上で保管されると貯蔵やけが急速に発生することがある。
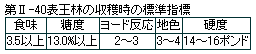
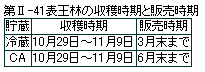
(7) ふじ
ア 平年の収穫始めは11月5日ころからである。
イ 収穫時期が早すぎると貯蔵後にビターピット及び貯蔵やけの発生、遅すぎると内部褐変が心配される。
ウ 蜜入り果は食味が良く、し好性が高いので、早期販売用(年内〜1月末)には十分蜜を入れて収穫することが望ましいが、貯蔵期間が長くなると蜜褐変を生ずることがある。
エ CA貯蔵の場合、ふじは炭酸ガス耐性が弱いのでできるだけ低い濃度とし、特に無袋果は蜜褐変が問題になるので1.5〜2.0%で管理する。
オ CA貯蔵用の無袋果は蜜入り程度を2〜3とし、2〜3月販売を主体にすると食味の優れた果実の供給ができる。
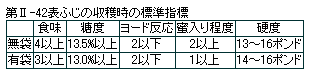
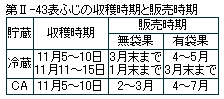
(8) その他品種
ア 未希ライフ
平年の収穫始めは9月7日ころである。熟期が不揃いで落果がみえはじめたら、2〜3回に分けてすぐりもぎをする。また、収穫が遅れるとつる割れの発生がみられる。貯蔵性は普通冷蔵で1カ月間である。
イ さんさ
平年のI叉穫始めは9月7日ころである。収穫適期は地色が乳白色から黄色に変わる時期である。樹上での日持ちは比較的良好であるが、収穫後、急速に軟化が進む。日持ち性は室温で2週間前後である。
ウ あおり9(彩香)
平年の収穫始めは9月22日ころである。着色の進んだものから、すぐりもぎをする。なお、収穫が遅れると油あがりがあるので適期収穫につとめる。貯蔵性は常温で10日、普通冷蔵で1か月間(10月末ころまで)である。
エ あおり13
平年の収穫始めは9月30日ころである。着色が先行するため、果色が濃紅色と十分着色してから収穫する。収穫前落果が少しみられるので、収穫は2回くらいに分けて行う必要がある。貯蔵性は常温で3週間、普通冷蔵で12月末頃までである。
オ 千秋
平年の収穫始めは10月6日ころである。収穫時期が遅れると果面に油あがりが多くなるが、完熟させて即売するのが望ましい。貯蔵後、酸味抜けによる味の淡白化がやや早いので、12月末までに販売を終了する。
カ こうたろう
平年の収穫始めは10月22日ころである。全面によく着色し、地色が黄色に変わる時期が収穫適期である。貯蔵性は普通冷蔵で2月下旬頃までである。
キ あおり15
平年の収穫始めは10月24日ころである。収穫が11月以降に遅れると硬度が極端に低下するので注意する。長期貯蔵用には地色が上がりすぎないうちに収穫する必要がある。貯蔵性は普通冷蔵で6月末頃まである。
ク 金星
収穫始めは11月9日ころである。早すぎる収穫は味が劣り日持ちも悪い。無袋果は貯蔵中に萎凋しやすいので4月が貯蔵限界である。有袋果を袋をつけたままCA貯蔵する場合は、炭酸ガス障害を防ぐため袋口を開けてガスが滞留しないようにする。 |
|
4) 収穫後の管理
(1) 冷却
収穫後、果実が高い温度下に放置されると呼吸量が急速に高まり、樹上で蓄積した養分の消耗が早まり、また、茶星、ビターピットなどの生理障害の発生も多くなるので、できるだけ迅速に冷却する。
(2) 貯蔵果選別上の―般的注意
りんごの選果に当たっては、外観だけでなく果実の素質も考慮し、販売時期に対応した選果が必要である。
ア 年内〜3月貯蔵用
地色のあがった完熟果か、完熟に近い状態のもの及び大王を中心とする。ふじなどは蜜の多く入ったものが良い。つる割れ(梗元の裂傷)は熱度の進んだ味の良いものに多いので、傷の大きいものは山選果で除き、小さいものは即売用とする。落果はたとえ外傷がなくとも、貯蔵中に疫病菌(土壌中に存在)による腐敗の恐れがあるので即売用とする。樹上凍結果は果実の弾力性が失われているため、押し傷がつきやすく貯蔵性を低下させることがあるので早めに販売する。
イ 4月以降貯蔵用
収穫時に食用として最適のものよりも幾分未熟のものを選ぶ。地色の緑が濃いものは未熟すぎて、貯蔵やけ、ビターピットなどの障害が出やすく、また、萎凋しやすいので加工用に仕向ける。果実の大きさは、品種の特性にもよるが、中〜小玉を中心とする。 |
|
5) 貯蔵管理
りんご貯蔵管理の概念は、呼吸の抑制、水分の蒸散防止、寄生菌及び生理的障害防止、エチレンの除去であるが、呼吸の抑制に重点が置かれ、温度を下げる、湿度を高める、酸素を減らす、炭酸ガスを増す方法などが実用化されている。
(1) 普通冷蔵
ア 温度
りんごの凍結温度は品種、あるいは内容物の充実度によって異なるが-2℃前後にある。低温ほど鮮度保持効果が高いが、庫内の温度分布にむらがあるので、0℃からややマイナス側で管理する。
イ 湿度
相対湿度85〜95%が適当である。果実の水分は蒸散の形で失われていくが、細胞内の水蒸気は飽和状態になっており、周囲との湿度差で移動する。特に冬は外気中の湿度が非常に低いので、入出庫の際は厚手のビニールシ一トなどで扉口を防ぐなどして外気が庫内に入らないような工夫が必要である。
ウ その他
果実を入庫する4〜5目前までに冷蔵庫内温度をー1℃くらいまで下げておく。りんごでは一般に予冷蔵庫を設けないので、収穫した果実は午前中に収容能力の1〜2割程度ずつ入庫し、一度に大量のりんごを入庫させない。また、冷蔵庫の機能を十分に発揮するには、庫内の冷気をよく循環させるような荷積みが大切である。
(2)CA貯蔵(Controlled Atmosphere Storage)
CA貯蔵とは、りんご貯蔵庫内の気体組成を人為的に調整(酸素を減らし、炭酸ガスの濃度を高める)し、さらに低温で貯蔵する方法である。
ア CA貯蔵の方式
(ァ) 再循環方式
プロパン燃焼装置(コンバータ)と炭酸ガス除去装置(アドソーバ)からなる。庫内とコンバータ間に空気の循環があり、コンバータでプロパンを燃焼させるが、酸素濃度が下がっても完全燃焼させるために触媒を用いる。アドソーバは活性炭を用いており、炭酸ガスの吸着と新鮮な空気による再生を交互に行なうため、二塔に分かれている。
(ィ) 窒素発生方式
外気の空気を圧縮させ、活性炭で酸素を吸着し、窒素ガスを分離するもの(P.S.A方式)と気体分離膜を利用した方式が実用化されている。酸素及び炭酸ガスを低濃度で維持するのに適しており、現在約80%がこの方式を採用している。
イ 運営上の基本
りんご流通の基本は鮮度の保持にある。CA貯蔵法は現在最も有効な鮮度保持方法であるが、りんごの品質を高めるものではなく、あくまでも鮮度保持手段である。また、りんごにかなりのストレスを与えることになるので、貯蔵するりんごの素質を十分吟味して障害を起こさないように、特にガス濃度管理には十分注意する。
ウ 温度、湿度
普通冷蔵庫に準ずる。なお、CA貯蔵は気密性が高いので扉を閉じて急速に冷却すると壁などがはがれて、気密性が破れ気体組成が調整できなくなるので、扉を少し開けた状態で冷却を始め、10℃以下に下がるのを確認してから閉じる。
エ ガス濃度
酸素濃度は一般に1.8〜2.5%で管理する。酸素濃度を下げた方が貯蔵障害抑制及び鮮度保持効果が高いので、できるだけ低い濃度で管理する。しかし、1.5%以下では無気呼吸を起こし発酵臭(アルコール臭)を帯びてくるので、1.5%が酸素濃度の下限値と考えられる。庫内の場所による濃度差、自動ガス分析計の誤差など、安全性を考慮して決める。炭酸ガス濃度は一般に1.5〜2.5%で管理する。炭酸ガス濃度は高めの方が鮮度保持効果も高まるが、炭酸ガス障害発生の危険性も増す。CA貯蔵におけるトラブルは炭酸ガス濃度の管理に起因するものが多いので特に注意が必要である。中でも、ふじは炭酸ガス障害を発生しやすい品種なので蜜の多く入った年は2.0%より低めにし、無袋果は1.5%程度まで下げた方がよい。
オ 品質の検査
月に1〜2回、りんごを数個取り出して品質の検査を行う。
カ 入出庫
CA貯蔵庫内の空気は酸素欠乏症状態になっており、一息でも吸うと目まいを起こしたり、気を失うので絶対吸わないこと。庫内に入るときは、酸素が18%以上になっていることを確認する。
(3) ポリエチレンフイルム包装
果実の水分蒸散防止とCA貯蔵効果をねらったものであり、フイルムはりんご包装資材用に市販されているもの(高圧密度製法)を使用する。
ア 原箱で使用する場合
フイルム内の底と上に吸湿紙(新聞紙など)を入れて水滴がたまるのを防ぎ腐敗を防止する。封をするときに果実温度が高いときは炭酸ガス濃度が高くなり炭酸ガス障害(果肉及び果心部の褐変症状)を起こすことがあるので果実を冷却後に封をする。袋口は折り畳む程度でよい。できれば、炭酸ガス障害防止対策として消石灰を1箱に100g程度紙袋に詰めて入れる。
イ 包装、荷造りに使用する場合
内装資材にモールドパック、中仕切り(片段ボール)を使用すれば吸湿紙は不要である。鮮度保持剤(エチレン除去剤など)を使用するときは上段のネットなどの上に置く。
ウ フイルムの厚さ
0.03〜0.05mmのものを使用する。フイルムの厚い方が鮮度保持効果が高いが、ふじなどは蜜褐変を生じやすいので、障害発生を避けるため0.03mmの薄いものを使用した方がよい。 |