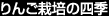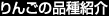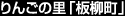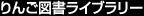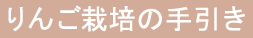|
|
|
| 13.�y����� |
|
��̐��Y�͒n�͂Ɉˑ�����Ƃ��낪�傫���A���ɏ�������́A���̌�̐���A���ʂɑ傫���e������B�V�A�A���A�ɓ������Ă͓y��̏��������悭�c�����A�L�@���y�ѐΊD���엿�̎{�p�Ɛ[�k�A�r����A�A�������ǂȂǂ��\���s�����Ƃ��d�v�ł���B�܂��A�������͗L�@���A�ΊD�A��y�Ȃǂ̉���ނ̕⋋���\���s���Ȃ��܂܂ɁA����܂Œ��N�ɂ킽���Ă�͔|�����Ă������Ƃ���A�y��̗����w�I�������������A�����I�Ȓn�͂��ቺ���Ă���B���̂��Ƃ��e���Q�̔������������A���Y�͂�ቺ�����Ă���̂�����ł���B���������āA���Y�͂̑�����}�邽�߂ɂ́A�V��y�щ��A���A������������̏ꍇ���q�������𒆐S�Ƃ����y��Ǘ����s���A�y��f�f�Ȃǂ����p���ēy��̌��N��Ԃ����A�y��̈����h�~������{����B��ȓy��̐����A�v���Ɖ��Ǒ�������Ɛ}�̂Ƃ���ł���B�܂��A�y����ǖڕW�l�������Ǝ��̂Ƃ���ł���B
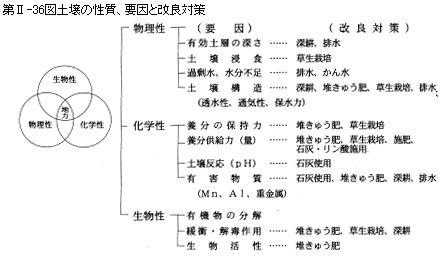
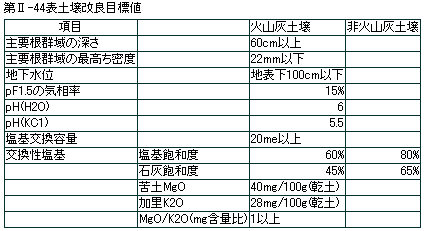 |
|
1)�@�V�A�y�щ��A���̓y�����
�A���t����̓y����ǂ͍���Ȃ��Ƃ������̂ŁA�V��y�щ��A���ɐ[�k�A�S�y�j�ӂ����{���A�͂��イ���ΊD���엿�Ȃlj��ǎ��ނ��ʂɎ{�p����B
(1)�@�S���̉���
�A�@���n�����y�ѓy����ǂ̏���
�@�@ ���n�����y�э͐A�܂ł̓y����ǎ菇�������Ǝ��̒ʂ�ł���B
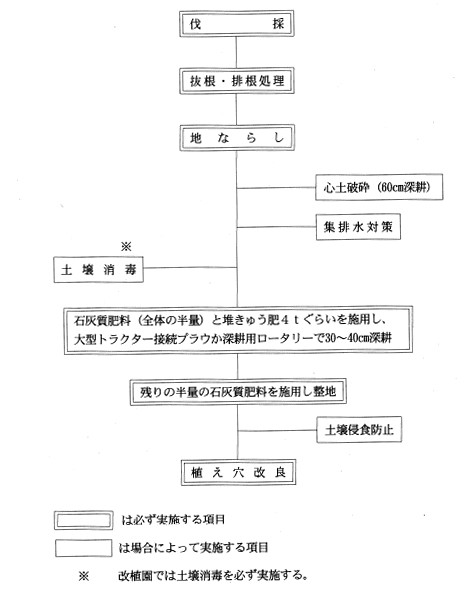
�C�@���n�����y�ѓy����ǂ̋�̍�
�V�K�J���A���A���ɂ����鉀�n�����y�ѓy����ǂ͎��̂Ƃ�����{����B�Ȃ��A���c�]�����ɂ��Ắu���c�]�����̓y����Ǒ�v�̍����Q�ƁB
(�@)�@�����E�r������
���͒��J�ɏE���W�߁A�������邩�A���O�ɔ��o����B
(�B)�@�����`�ԂƐؓy�A���y
�@�B����Ƃ�O��Ƃ��������`�Ԃ͓y�n�̌X�Γx��10�x�ȉ��̒n�`�ł͎R���蔨�A10�`15�x�ł͍�Ɠ��^�Ζʔ��A15�x�ȏ�ł͍�Ɠ��^�K�i���Ƃ���̂���ʓI�ł���B�������A21�x�ȏ�̐V�K�����n�ł́A������4�`5�N�o�߂��Ă����͐A�̉��n���U������A�y�n���p�����������Ă���̂ŁA���܂�}�Ȍ��z�̏ꏊ�͑������Ȃ��悤�ɂ���B�܂��A�ŋ߂ł͋@�B�͂𗘗p���A���G�Ȓn�`�𐮂��ĎΖʂ̎R���蔨�ɂ��Ă���������A�����I���邢�͑S�ʓI�Ȓn�`�����ɂ���Đؓy�A���y�������ł���B�ؓy�����͍d���āA�������ȉ��w�y���I�o����̂ŁA�[�k�Ȃǂ̑��O�ꂷ��B�܂��A�n�`�����ɔ����āA��₭�ڒn�����߂��邱�Ƃ��������A���R�r���𑣐i�����邽�߂ɂ͂ł��邾��������̂܂c���Ċ��p����B
(�D)�@�n�Ȃ炵
���R�n��R���蔨�ł́A�����B�r�����s�Ȃ����Ƃ��ɒn�\�ʂɓʉ����ł���̂ŁA�y���n�Ȃ炵������B
(�F)�@�S�y�j��
���w�y�������ŁA���̐L����j�Q���₷���y��ł�60cm�܂ŐS�y�j�ӂ�����B�S�y�j�ӂɂ̓��b�p�[�h�[�U�\�A�o�b�N�z�[�A�u���h�[�U�[�Ȃǂ𗘗p���邪�A���b�o�[�h�[�U�[�͏c�A��2�������炢���s����B���A���ł͔������y�ѐ[�k���ɍ��J�ɏE���W�߂�B�S�y�j�ӌ�͐[�k�p�v���E(�g���N�^�[�ɐڑ�)��[�k�p���[�^���[��30�`40cm�k����B���̍ہA�͂��イ��ƐΊD���엿���{�p����B
�E�@�y�����
���A���ł́A��H�a����A��Q(����n)�̔�����h�~���邽�߁A�N�����s�N�����ɂ��y����ł�K�����{����(�u��H�a�v�̍����Q��)�B�y����ł����ꍇ�A�������3�T�Ԉȏ�o�߂��Ă���K�X�������s���A�͂��イ��̎{�p�͂��̌�Ɏ��{����B
�G�@�͂��䂤��̓���
�V�A�y�щ��A���ɂ�10a������5�`6t�̑͂��イ����������邪10a������4t���x��S���Ɏ{�p���A�A�����ւ̎{�p�ʂ͑�U�[47�\�́u�A�����Â���̖ڈ��Ɖ��ǎ��ނ̎{�p�ʁv���Q�Ƃ���B
�I�@�Δ�앨�̗��p
(�@)�@�͂��イ�삪����ł��Ȃ��ꍇ�͗L�@���⋋�̂��߂Ƀ��C�O���X�ށA�����C���ށA�\���K����(�X�_�b�N�X�Ȃ�)�̗Δ�앨���͔|���ď����݂�����B
(�B)�@�Δ�앨10a������̔d��ʂ͉��\�̂Ƃ���ł���B�܂��A�����݂͐A���t��2�������炢�O�܂łɏI����B
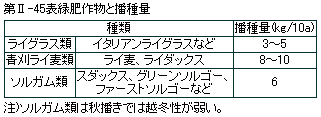
(�D)�@�X�_�b�N�X�Ȃǃ\���K���ނ̔d��ɓ����Ă͂��͔̍|���Ԃ�2�����A�����݂��Ă���A���t���܂ł̕��n���Ԃ�2�����ł��邱�Ƃ��l�����Ĕd��������肷��B�d�펞���͍~�����Ȃ��Ȃ���5�����{����7�������܂łł���B�Ⴆ�A�y����ł�6�����߂Ɏ��{���A11���̏H�A��z�肵���ꍇ�A7�����߂ɔd�킵�A��2�����ԍ͔|����9�����ߍ�(�o�䒼�O)�ɏ����ށB
(�F)�@�e��Δ�앨�̐����ʂ͕\�̂Ƃ���ł���B
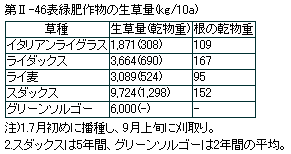
�J�@�ΊD���엿�̓���
(�@)�@�V��y�щ��A���̐ΊD���엿�̎{�p�͋�y�̊܂��̂��g�p���A�����̎�v���Q��(60cm)�������ʂ𓊓�����B���̕K�v�ʂ͓y��̎�ށApH�ɂ���ĈقȂ邪�A10a�����艫�ϓy��y�ь���̉ΎR�D�y���800�`1,500kg�A�Ìy�̉ΎR�D�y���2,000�`3,000kg�A�X�Βn�y��(�c�ϓy��)�ł�1,600�`2,400kg�{�p����(�u�_���y��̉��ǁv�̍����Q��)�B
(�B)�@�ΊD���엿�͐[�k�p�v���E���[�k�����[���[�ɂ��k�N�̑O�ɔ��ʂ��{�p���A�c��̔�������[�[���\�k����@�Ȃǂōӓy����Ƃ��Ɏ{�p����B
�L�@�W�r����
�K�i���̒����ł͒�ؐ����₷���̂Ŕr���H��ݒu����B�܂��A�X�Βn�̉����ł́A�������ɂ���Ĕr���s�ǒn�ɂȂ�₷���̂ňÂ���▾�����K�v�Ƃ��邱�Ƃ�����(�u���c�]�����̓y����Ǒ�v�̍����Q��)�B
�N�@�y��N�H�h�~
�y��N�H��h�~����ɂ́A�[�k��ł��邾�������@��ɑ����͔|�����{����B�������A�V�A�n�̂悤�ɂ₹���y��ł́A�P���ɖq����d�킵�Ă����̐L�т������A�܂�����ނ炪�ł��A�N�H���N���邱�Ƃ������B�K���y����ǂ��s���Ă���q����d�킷��B�܂��A�傫�Ȓf�R�ȂǂŁA�y������̐����₷���ꏊ�ɂ́A�q���̐������H�@���l�����Ă����B�K�i���ł́A�@�ʂ̕ی�̂��߁A�����A�Y�ł��A�Ő��̒��t���Ȃǂ��s�Ȃ��B���ɁA�@�ʂ̌������͏\���ɋ�������B
(2)�@�D�����̉���
�A�����̑召�͂�̈ꐶ�����E���邩��A�c��A���鎞�͂ł��邾���A������傫���@��A�K�ʂ̉��ǎ��ނ��{�p���ēy����ǂ�����B
�A�@�A�����̑傫���ƌ@����
�A�����͂ł��邾���傫���@�邱�Ƃ����z�ł��邪�A�l��ɂ��@�����͑����̘J�͂�K�v�Ƃ��邩��A�ł��邾����^�@�B�𗘗p���ĐA�����Â��������B���������Ɖ��\�̂Ƃ���ł��邪�A�S�y��j�ӂ��Ȃ��ȂǓy����ǂ��s�\���ȏꍇ�ɂ́A��90cm�A�[��60cm�̑傫�ȐA�����Ƃ���B
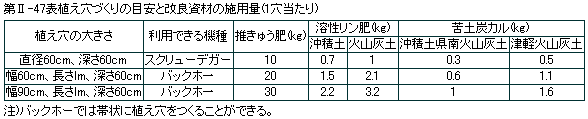
�C�@���ǎ��ނ̎g����
(�@)�@�g�p����͂��イ��A�n���胓��A��y�Y�J���Ȃǂ̉��ǎ��ނ͐A�����̑傫���A�y��̎�ނɂ���Ď{�p�ʂ�ς���B�܂��A�͂��䂤��͂悭���n�������̂��g�p����B
(�B)�@�A�����ɉ��ǎ��ނ�����ꍇ�͓y�Ƃ悭�����Ė��ߖ߂��B�܂��A�\�w�y�ƒ��w�y�͒��J�ɍ�������B
(�D)�@�͂��イ�삪����ł��Ȃ��ꍇ�̓A�Y�~���A�e���|�����A�n�C�t�~���Ȃǂ̉��w�͔��s�[�g���X�Ȃǂ��{�p����B��2kg��y�ƍ������č����핔�Ɏ{�p����B
(�F)�@���A����ɗc��A���t����Ƃ��́A�A���t����̐�����悭���邽�߁A�Â����J�ɏE���W�߂Ă�����ǎ��ނƓy����������B
�E�@���݂��̐ݒu
�V�A�n�ŐS�y�j�ӂ��ł��Ȃ��������́A�A�����ɐ������܂�c���͎������Ă���Ⴊ�����̂ŁA���݂�������ĉߏ萅��r������B���݂��͍a�@��@�Ŏ���ɉ����ča�����A�X�Ή����֓����B�܂��A���݊k�Ȃǂ̑a���ނ�����B
(3)�@�A���t����̔�|�Ǘ�
�A�@�엿�͊������Ă���(6������)�A10a�����蒂�f2kg�����ʂ��{�p����B
�C�@���炪������ꍇ�ɂ́A���߂�1�`2�N�Ԃ͔A�f�̗t�ʎU�z(��100l������A�f200g)�𐔉�s���B
�E�@�V�A�n�ȂNJ����̌������n�тł̓}���`(�~���Ȃ�)�����{����B |
|
2)�@�������ɂ�����y�����
���؉��ł̐[�k���y����ǂ͒f����Q�����O�����̂ŔN���v��𗧂ĂȂ�����{����B
(1)�@����Ԃ̉��ǖ@
��^�g���N�^�[�ɐ[�k�p�v���E��[�k�p���[�^���[��ڑ�����30�`40cm�[�k������A�g�����`���[�𗘗p������@������B���ǎ��ނ͑�^�g���N�^�[�𗘗p����ꍇ�A10a������͂��イ��1,000kg���炢�A�ΊD���엿250�`500kg�A�܂��A�g�����`���\�𗘗p����ꍇ�͍a10m������͂��イ��70kg���炢�A�ΊD���엿4�`8kg�{�p����B
(2)�@�������̉��Ǖ��@
�A�@�f�K��ɂ�����
�f�K��ɂ��[�k�́A�ʏ�̐��؉��ł͊�����1.8�`2.5m�͈̔͂�ΏۂƂ��A�a60cm�̃f�K�[�ł�4�`6���A�a23cm�`30cm�̃f�K�[�ł�12�����x�Ƃ��A3�`4�N�Ԍp������B��؉��ł͎����~��������n�߁A�Q���O���֍L����B���ǎ��ނ͌a60cm�̃f�K�[�𗘗p�����ꍇ�A�ꌊ������͂��イ��10kg�A�ΊD���엿0.5�`1.0kg�A�a23cm�`30cm�ł͑͂��イ��2�`5kg�A�ΊD���엿0.2kg���{�p����B
�C�@���N�k���y��[�k�@�ɂ�����
�f����Q���Ȃ��A�������[�k(�c�)���ł���@��Ƃ��āA���N�k���y��[�k�@(�p���_�[�Ȃ�)������A�y�낪�d�����n�ŗ��p���������B |
|
3)�@�_���y��̉���
�ߔN�A�_���y��̉��ǂ͒�؋C���ŁA�����ȏ�̉��n�����_���`�Ɏ_���ɂȂ��Ă���B�����lj��ł͐ΊD���엿�̑�ʎ{�p�����{���A���lj��ł��_�����h�~�̂��߂ɁA�ΊD���엿�̎{�p�𑱂���B
(1)�@���ǂ���ڕWpH�l
�A�@����ɂ�����_�����ǂ̖ڕW�l��pH(KC1)5.5�ApH(H2O)6.0�Ƃ���B
�C�@�_���y������ǂ��鎞��pH���[�^�[���g�p���Ď_�x������s���B�y��͐[��15cm���Ƃ�60cm�܂Œ���ɍ̎悵�ApH�𑪒肵�ĐΊD���엿�̕K�v�ʂ��Z�o����B
(2)�@10a������ΊD���엿�̕K�v��
�A�@�y��̎�ށEpH�Ƌ�y�Y�J���̕K�v��
�ΊD���엿�̕K�v�ʂ͓y��̎�ށApH�l�ɂ���ĈقȂ邪�A��v���Q��60cm�̐[���܂ʼn��ǂ��邽�߂ɕK�v�ȋ�y�Y�J���ʂ͕\�̂Ƃ���ł���B
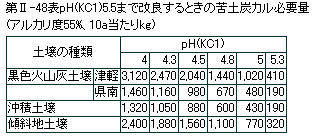
�C�@�ΊD���엿�̎�ނƕK�v��
�g�p����ΊD���엿�̓����ƕK�v�ʂ������ƕ\�̂Ƃ���ł���B�Ⴆ�A�Ìy�̍��F�ΎR�D�y���pH(KC1)��4.0�̏ꍇ�A��y�Y�J����10a������̕K�v�ʂ́A�\����3,120kg�ƂȂ�B��y�Y�J���ȊO�̗�Ƃ��āA��y���ΊD���g�p����ꍇ�́A3,120kg×0.79=2,465(kg)��10a������̕K�v�ʂƂȂ�B
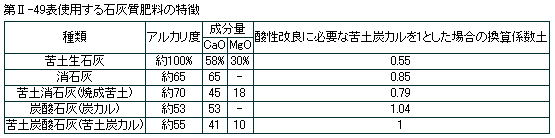
(3)�@�{�p���@
�A�@�\�ʎ{�p
(�@)�@�\�ʎ{�p�ł́A���Q���z�̑����������Ɏ{�p����B���ʑ���ł͎�����(���𒆐S��5m�l��)��ΏۂƂ��A��y�Y�J�����g�����ꍇ�ɂ�20kg���x���{�p����B���łɑ�ʂɎ{�p����Ă��鉀�n�ł͍k������J��Ԃ��A���w�Z����}��B�k����@���g�p���čk�N����ꍇ�͑傫�ȍ����Ȃ��悤���ӂ���B
(�B)�@pH�̉��ǂ��ꂽ���n�ł�10a������������{�p��100kg���x(20�{�A��1��������5kg)���{�p���Ď_�����h�~�ɓw�߂�B
(�D)�@���߂Ă�����k�N���ĐΊD���엿���{�p����Ƃ��́A�f���̈��e��������邽�ߔӏH�Ɏ{�p���������悢�B���łɎ_���y��̉��ǂ�i�߂Ă���Ƃ��́A�O�v�f�엿���Ɏ{�p���A�~�J��������2�`3����ɐΊD���엿���{�p����B�~�J���Ȃ��ꍇ�ɂ́A�{���2�T�Ԃ��炢��Ɏ{�p����B�ΊD���엿�̎{�p��͍k����B
�C�@���͐��ɂ�钍���{�p
�f�����邱�ƂȂ��ꋓ�ɐ[�w�܂ł̓y����ǂ�}��A�e��a�Ȃǐ�����Q���̉𑁂߂邽�߂ɂ͐ΊD���엿�̒����{�p���s���������悢�B�ΊD�����t��|���v�⍂���|���v�ɐڑ����������_����f�o�����A���̓f�o���͂œy�������E���ĐΊD���엿��[�w�܂Ŏ{�p����B�ʏ�A��1,000JB��60�`80kg��n�����A�������ɒ�������B��ł͎��̑傫���ɂ���Ď{�p�ʐς�����B |
|
4)�@����r��
�r���s�ǂ���͓y��̉ߎ��ɂ�萶��s�ǁA���ʁA�i���̒ቺ����������łȂ��A��^�@�B�̓����ɂ�铥����Q�������₷���B�����̉��n�͑��̓y����ǂɐ�đ��}�ɉ��P�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
(1)�@�Â���̑g�D
�Â���̑g�D�\���͈�ʂɕ\�̂Ƃ���ł���B
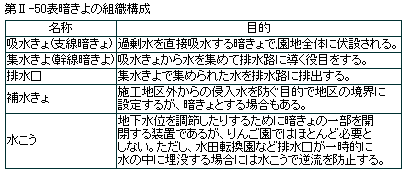
(2)�@�r���v��̗��ĕ�
�Â���̎{�H�ɂ������ẮA�r�����̈ʒu�A�[���ƊԊu�A���z�Ɗnja�Ȃǔr���v����\����������B
�A�@�r�����̈ʒu
�r�����̈ʒu�͔r���H��͐�̐��H�Ɨ������\���Ƃ��Ƃ���ɐݒ肷��B���ϓy�n�т̂悤�ɗ������������Ƃ��́A�����r������ݒ肷�邩�A�@�B�r�����s���B
�C�@����z�����
�v��n�悪������n���A���͋ɂ߂Ċɂ₩�ȌX�Βn�̂Ƃ��́A�r�����̈ʒu��X�̕����ɂ���Č��肳��邪�A�^�ϑ�n�̂悤�ȊɌX�Βn�͎x��(�z������)���ł��邾����������ɔz��B
�E�@�Â���̐[���ƊԊu
�n�����ʂ�n�\��100cm�ȉ��ɕۂ��߂ɈÂ���̐[����120�`130cm�Ƃ���B�܂��A�Â���̊Ԋu��2���Ƃɂ���B
�G�@�Â���̌��z�Ɗǂ̑傫��
�Â���̌��z�͉ΎR�D�y�n�тł́A�n�`�I�ɂ��Ղ��A���ϓy�n�т̂悤�ȕ�����ȉ��n�ł͌��z�����ɂ����B������̉��n�ł�1/250�`1/300�̌��z������悤�ɂ���B�z���ǂ�60mm���炢�̂��̂��g�p���A���̉�����100m�ȓ��ɂƂǂ߂�B�W������̊nja�͎x�z�ʐς�Â���̌��z�ɂ���ĈقȂ邪�A�x�z�ʐρA���z�Ɗnja�Ƃ̊W�������ƕ\�̂Ƃ���ł���B
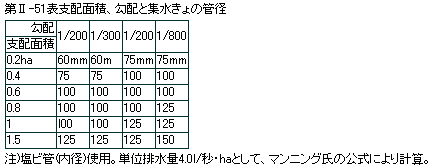
�I�@�g�p����Â��厑��
�Â��厑�ނƂ��ă|���G�`�����≖���r�j�[�����̂��e���܂Ȏ��ނ��g�p����Ă��邪�A���ނ̑I���ɓ����ẮA�y�̏d�����^�@�B�̓����ŕό`���Ȃ��悤�Ȋǂ�I�ԁB
(3)�@�Â���̎{�H
�Â���̎{�H�͎��ނ̔z�u-�@����-�p�C�v�̐ݒu-���ߖ߂��̍H���ōs���B
�A�@���ނ̔z�u
�Â��厑�ނ͂�����ɉ����đO�����ēK���ɔz�u���Ă����B
�C�@�@�����ƃp�C�v�̐ݒu
�g�����`���\�{�H�̏ꍇ�ɂ͂��ׂĉ�������s���B�܂��A�@�������ɂ́A�[������z���m�F���Ȃ���A�a��ɓʉ����Ȃ��悤�ɂ��A�a��ɗ������y��͂������グ�邩�n�Ȃ炵������B
�E�@�핢�ޗ�
�Ǔ��ւ̓y���̗�����h���A�����Ǔ��ɗ���₷�����邽�߂ɁA���݊k��z�^�e�L�k�Ȃǂŋz���ǂ�핢����B�핢���͊ǂ̒ꕔ�ɂ͎g�p���Ȃ��ŁA��Ɖ������Ɏg�p����B
�G�@���߂�
�p�C�v�̐ݒu�Ɠ����ɁA�p�C�v��핢����ی�A�Œ肷����x���߂�������B�{�i�I�Ȗ��߂��͔r�����m�F���Ă���s���B
�I�@�{�H����
(4)�@�r�����̊Ǘ�
�A�@�r�����̊Ǘ�
�r�����̓R���N���[�g�Ȃǂ̕ی�H��������B
�C�@���H�̐���
�r��������m���ɔr�������邽�߂ɂ́A������̂悤�ɐ��ʂ������Ƃ��ł����H�ɓˏo�����r���������v���Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ���ł���B���̂��ߐ������H�̓D�グ��̊��荞�݂�����B
(5)�@�o��
�Â���r���̌o��͎��{�ʐρA�{�H���@�Ȃǂɂ���ĈقȂ邪�A�l�{�H�̏ꍇ�̌o������Z����Ύ��̂Ƃ���ł���B
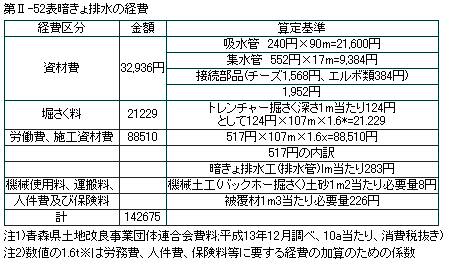 |
|