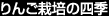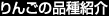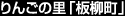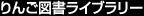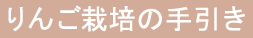|
| 16.施肥 |
|
| 最近、主要品種に対する窒素施用量は10a当たり20kgを下回っており、極端な多肥はみられなくなった。施肥量の多少はりんご樹の生育、収量、果実品質ばかりでなく、土壌反応、土壌中の塩基バランスにも影響するので、今後とも施肥の適正化に取り組むべきである。 |
|
1) 施肥量の基準
(1) りんご標準施肥量及び三要素の比率
10a当たりの標準施肥量(本県の大部分のりんご園において、樹勢の維
持や収量の確保にとって、肥料は不足しないという施肥量)は下表のとお
りで、三要素の施用比率は窒素10に対し、リン酸3、カリ3程度とする。
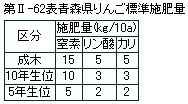
(2) 各園地の施肥量適量点の見い出し方
1園に3樹程度の施肥増減区を設け、1〜3年先行させ、樹勢や果実品質の変化を観察しながら徐々に適量点を見いだすのが安全である。紋羽病発生地帯では、慣行施肥量から急激に無肥料状態にすると、極端な樹勢低下を招くことがあるので注意する。
(3) 施肥量増減の判断
ア 着色のよくない園地、樹勢の強すぎる園地では、慣行施肥量を半減する。また、高接ぎによる一挙更新園及びビターピットやコルクスポットが発生する園地などでは2〜3年無肥料にする。
イ 減肥によって樹勢が明らかに衰弱した場合は、基肥の時期に窒素を5kg程度増肥し、尿素の葉面散布(水100l当たり尿素200g)を開花直前から6月中旬まで3〜4回行う。
ウ 県南地域、新植園、りんご栽培年数の少ない園、水田転換園、客土した園、有効土層の浅い園地や肥料の流亡しやすい園地では、2〜3年に1回土壌診断を行い、深さ30cmまでの交換性カリ含量が土壌100g中(乾土)28mg以下の場合はカリ施肥量を10kg/10aとする。
エ 幼木を密植した場合でも、成木に対する標準施肥量を上回らないようにする。
オ 肥料要素の過不足による生理障害が発生した場合の施肥対応は、「生理障害対策」の項を参照して行う。 |
|
2) 肥料の種類と施肥時期
(1) 肥料の種類
ア 使用肥料の種類については、どの肥料を用いても使用方法が適切であれば効果はほば同じである。最近、有機入りの複合肥料の使用される例が多いが、これらの肥料から土壌に入る有機物は量的に少ない。りんご園の有機物補給は、草生栽培、堆きゅう肥施用に頼るべきである。
イ 土壌の酸性化をくいとめるため、硫安や塩化カリ等の生理的酸性肥料の使用は避ける。
(2) 施肥時期
ア施肥は消雪後できるだけ早く、遅くとも4月20日ころまでに行う。
イ有効土層の浅い園地や、肥料の流亡しやすい園地では、窒素の施肥を2回に分けて行い、その年の窒素施肥量の6割を基肥として4月20日ころまで、残り4割を追肥として6月末までに施す。追肥を尿素で施すときはリン酸、カリは基肥に全量施してよい。
ウ石灰窒素を使用するときは、翌年の窒素施用量の3〜4割を秋に施用するが、幹に直接ふれると木がやけることがあるので注意する。
エ石灰質肥料を春に施用するときは、施肥を先に行い、降雨があったら2〜3日後に施用してよいが、降雨がない場合は2週間後位にする。石灰質肥料施用後は耕うんする。 |
|
3) 肥料の成分と施用量
10a当たり必要な窒素、リン酸、カリ成分量を施用するため、保証成分(%)別の現物施用量(kg/10a)は次のとおりである。
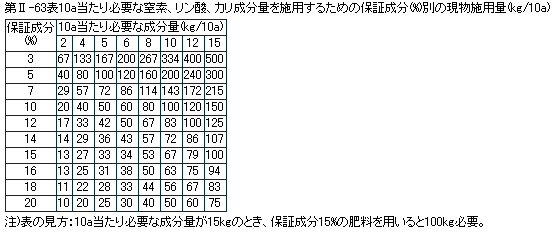 |
|
4) 主な有機質肥料と自給肥料の標準含有成分量
主な有機質肥料と自給肥料の標準含有成分量は表のとおりである。
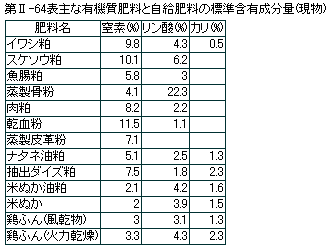 |