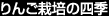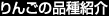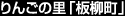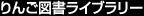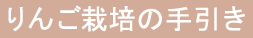|
| 3.整枝剪定 |
|
1) 整枝剪定の基本
整枝は樹の骨格を作る作業であり、骨格は健全で長い年月の生産に耐え、作業がしやすく充実した成り枝を多く作ることのできるように、樹齢に応じて作っていき、樹齢20〜30年で目標の樹形に近づける。
(1) 剪定時期
剪定を行う時期は、腐らん病防止の観点からみれば厳冬期を過ぎてからが望ましい。しかし、労力の都合上あるいは雪害軽減のために初冬や厳冬期に剪定する場合は大枝単位に行い、中・小枝は春に剪定する。この際、大枝の剪去は長めにし、春に所定のところまで切る。なお、枝の切口には剪去後できるだけその日のうちに塗布剤を塗る。
(2) 樹形
ア 骨組みの作り方は関心形か遅延関心形とする。
イ 樹冠の外形は半円形(又は主枝中心総合半円形)とする。
ウ 主幹の長さは中幹仕立てとする(ただし、主幹の長さはデリシャス系・北斗・陸奥はやや長めに、ふじ・王林はやや短めにする)。
(3) 主枝
ア 主枝の本数は2-3本とする。一般には樹間間隔が狭いときや樹勢が弱い品種では2本主枝が、また樹間間隔が広いときや樹勢が強い品種では3本主枝の方が有利であるが、樹が古くなるといずれも2本主枝の方が有利となる。
イ 主枝の発出位置は、地面からの高さで、2本主枝では下位主枝1.5〜1.8m、上位主枝1.8〜2.1mとし、3本主枝では下位主枝0.9〜1.2m、中位主枝1.5〜1.8m、上位主枝2.1〜2.4m程度とする。
ウ 主枝の角度は、0.9mくらいの高さから出たものは仰角30〜40度、1.5mくらいでは20〜30度、2.1mくらいでは10〜20度程度にし、枝の下がりやすい品種は斜立度を強めに、下がりにくい品種は緩やかにする。
エ 主枝の長さは最上位亜主枝の基部までとし、約2.0〜2.5mとする。
(4) 亜主枝
ア 本数は1本の主枝当たり1〜2本とする。
イ 長さは1〜2mとし、その先は延長部とし更新の対象にする。
ウ 角度は主枝に対する狭角で40〜50度とし、垂直角度は定まってないがお互いに同一平面に並ばないよう角度を違え、先端の高さが1.5〜2.5m以内に収まるよう、高い位置から出た亜主枝は角度を緩やかにする。
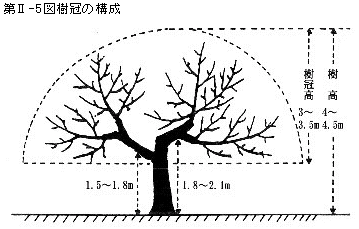
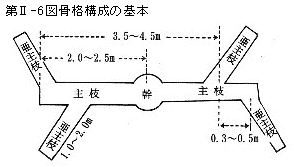
(5) 成り枝
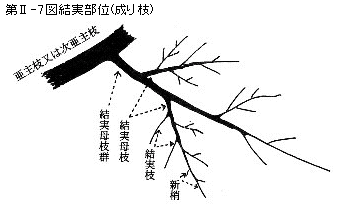
ア 素質の良い新梢を選んで成り枝とする。
イ 成り枝は主軸を中心として側枝を大きくせず、基部を底辺とした組長い三角形状とする。
ウ 適度の間隔をもたせながら、上下の方向に交互に発出させた立体的配置とする。
エ 骨格となるような大枝はできるだけ少なくする。
オ 樹冠の所々に大きな窓、つまり結実母枝群位の枝を単位に十分な間隔(空間)をもたせる。
(6) 枝量と頂芽数
収量を左右するのは頂芽数であるが、この頂芽数の多少は基本的には枝量とそれぞれの枝の充実度によって決まる。
ア 枝量
10a当たり良品果収量4tを目標とした場合の成木園における標準枝量は表のとおりである。
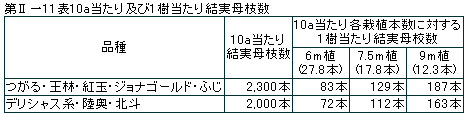
イ 頂芽数
10a当たり収量4tを目標とした場合の成木園における頂芽数のおよその標準とそれにともなう着果数は次表のとおりである。なお、頂芽数の多少は枝量と密接に関連するので、不足の場合は枝量の増加とその内容の充実に努める。
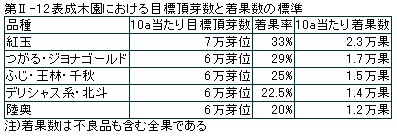
ウ 枝量と頂芽の増やし方
頂芽数が標準より少ない場合は一般に枝量が少ないことに起因していることから、剪定によってこれを増やす必要がある。成り枝は発育枝(新梢や果(花)台枝)、結実枝(短、中、長果枝をつけた3〜4年生の枝)、結実母枝(発育枝や結実枝を数本つけた5〜6年生の枝)、結実母校群(結実母校を数本つけた8〜11年生の枝)で構成されているが、いずれの枝も出発は発育枝からである。将来成り枝に仕立てようとする発育枝は一般には主軸から直接出た枝ではなく、短果枝か中果枝から発生した果(花)台枝で斜め上向きの枝を選んだ方がよい。このような発育枝は将来主軸との釣合いがとれ、花芽の付きもよい結実枝となりやすく、成り枝としての寿命も長い。
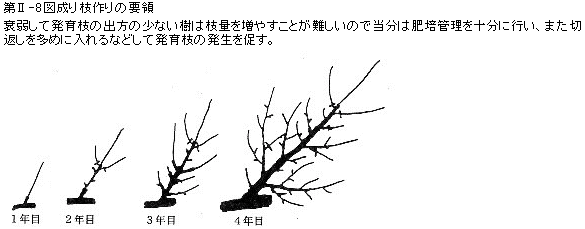
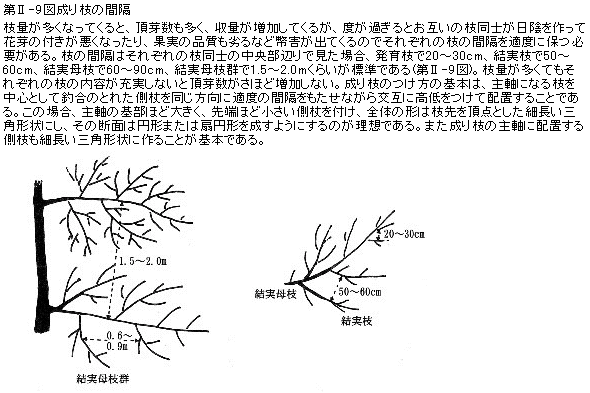
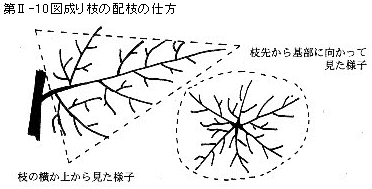 |
|
2) 樹齢別剪定
りんご樹は樹齢の進みとともにいろいろな樹相を経て成木に達する。したがって、整枝剪定に当たっては、それぞれに樹の年代に応じた目標を立て、その目標樹形が達成できるよう作業の要点をつかんで取りかかる。
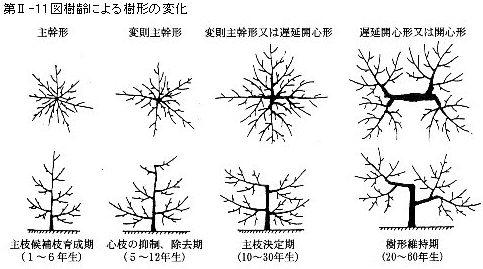
(1) 主枝候補枝育成期(1〜6年生)
ア 目標
(ァ) 主枝候補枝を必要な部位に多く発出させる。
(ィ) 樹を健全に育成させ、樹冠を早く拡大させる。
(ゥ) 樹形構成に支障のない範囲で、早く結実に導く。
イ 樹形
主幹形とし、樹冠の外形は初め円錐形でだんだん半円形に近づける。
ウ 作業の要点
(ァ) 栽植当年(1年目)
i 植え付けた苗木を地上70〜90cmの所で切り返す。
豩 苗木の大きさ(太さと長さ、根量などの総合)が不揃いの場合は、切返しの高さを一定にすると以後の生育がかえって不揃いになるので、生育の悪い苗木は全長の2/3ぐらいを残して切り返す。特に貧弱な苗木は切返しをしないで1年間生育させる。
豭 デリシャス系のように狭い角度で枝が発出しやすい品種は6月に入って最上位の新梢が10cmくらい伸びたとき、最上位の新梢を残して下位の1〜2本を摘み取ると下位に発出角度が広く望ましい主枝候補枝ができる。
ィ) 次年度以降
i 主幹の延長部の新梢を45〜60cm程度の長さに切り返す(新梢の長さの20〜30%くらい剪去)。
豩 最上位の新梢が強過ぎる場合はこれを剪去して次位の枝を主幹延長枝として用いる。
豭 狭い角度で枝の発出しやすい品種では1年目と同様に6月に入ってから最上位の新梢を残して下位の1〜2本を摘み取る。
豳 主枝候補枝の先端は軽い先刈りをする。
𧲸 発出角度が狭く、かつ強過ぎる主枝候補枝は剪去するか、縄などで誘引する。
(2) 心枝の抑制、除去期(5〜12年生)
ア 目標
(ァ) 主枝候補枝を健全に育成し、不要なものは次第に切りつめる。
(ィ) 心枝は徐々に抑制し、10年生前後に勢去する。
(ゥ) できるだけ結実量を高める。
イ 樹形
初め主幹形、後に変則主幹形に移行する。
ウ 作業の要点
(ァ) 心枝の剪去は上位の主枝候補枝の熱度、つまり花芽がかなり付き、新梢の伸びも若干衰えた頃をみて行う。
(ィ) 主枝候補枝のうちから高さ1.2〜2.4mくらいの範囲で3〜4段に1本ずつの最有力候補枝を選定し、これに強めの切返しを入れ、側杖の発出を促すとともに下垂を抑える。
(ゥ) 有力主枝候補枝の選定に当たっては平担地の場合、第1主枝を南側に最上位主枝を北側に置くようにするのが理想的である。また、傾斜地では谷側に第1主枝、山側に最上位主枝を設ける。
(ェ) 有力主枝候補枝の生育に邪魔する他の候補枝は次第に抑制する。
(3)主枝決定期(10〜30年生)
ア 目標
(ァ) 主枝を決定し、各主枝に対して亜主枝を設定する。
(ィ) 主枝以外の枝を切りつめ、間引く。
(ゥ) 充実した結実母枝を多く作る。
(ェ) 主枝を強固にする。
イ 樹形
初め変則主幹形、後に遅延関心形又は関心形となる。樹冠は半円形。
ウ 作業の要点
(ァ) 主枝以外の大枝の切りつめ、間引きは急激に行うと収量が減るばかりでなく、樹が徒長するので慎重に行う。一般に、剪去する枝の取扱い手順としては、結実部位を徐々に先端方向に追いやり、着果量が少なくなってきたら剪去する。あまり躊躇すると主枝の発達を阻害するので注意する。
(ィ) 亜主枝の設定は、主枝の基部から2m前後とし、1主枝当たり2本以内にとどめ、他は側枝として働かせ大枝にしない。
(ゥ) 主枝が基部の大きに比べて長さの釣合いがとれなくなり、しかも結実が盛んになってくると、基部から下垂するおそれがあるから枝先から5、6年、場合によっては7、8年さかのぼって(基部からみれば2〜2.5m付近)大きな切返しを入れることがある。この場合、不用意にやると主枝の徒長が激しいので切返し部の付近には、できるだけ多くの側杖をけん制枝として数年前から準備しておく。
(ェ) 主枝延長部や亜主枝には4〜8年生の充実した結実母枝を適度の間隔を持たせて多く付ける。
(ォ) 成り枝を頻繁に更新すると果実品質が劣るので、いったんできたものはできるだけ長く保持するよう「割り」や「切上げ」を随時入れる。
(ヵ) 発育枝を大きな枝に育成させたいときは、切返しを強く、成り枝として利用するときや、小さい枝で収めたいときは無勢定にするか弱い切返しにとどめる。
(4) 樹形維持期(20〜60年生)
ア 目標
(ァ) 骨格の維持(場合によっては更新)
(ィ) 結実部位の増大
(ゥ) 結実母枝の充実と更新
(ェ) 相互の樹または枝の空間の保持
イ 樹形
遅延開心形か関心形
樹冠から見れば半円形か主枝中心総合半円形
ウ 作業の要点
(ァ) 主枝、亜主枝などの骨格を維持するため、枝量過多にならないように調整する。
(ィ) 樹冠間隔に余裕があるときは、次亜主枝を作る。
(ゥ) 主枝、亜主枝は原則としては更新しないが、枝折れや下垂のひどいときは更新する。
(ェ) 樹冠同士は触れ合わないように1m以上の空間を保持する。混んできたら切下げを活用する。
(ォ) どうしても樹が混んで収まりがつかないときは、大枝の剪去か間伐(規則的な)を実施する。
(ヵ) 結実部位はできるだけ立体的に配置し、厚みをつける。
(キ) 結実母枝群の間隔は50cm程度の空間を維持し、また、結実母枝や結実枝間にもそれぞれ適度の空間を与えて、日光が樹冠内部まで入るよう間引きを活用する。
(ク) 成り枝が下垂し、衰弱がひどくなったら更新する。更新枝は枝先から2mくらい基部にさかのぼって立てる。
(5)骨格更新期(50年生以上)
ア 目標
(ァ) 骨組みの枝を少なくし、枝のはげ上がりを抑える。
(ィ) 結果部位が幹から遠ざかるのを抑える。
(ゥ) 枝の衰弱を抑え、樹勢を維持する。
イ 樹形
遅延開心形または関心形
ウ 作業の要点
(ァ)骨組みの枝は漸次整理し、剪去した付近から発出した発育枝を利用して結果枝を作る。
(ィ)基部がはげ上がり、腕の伸びすぎた主枝や亜主枝は、幹から近い発育枝を利用して結果部位を作り、長さをつめる。
(ゥ)下垂枝など衰弱気味の枝は、切返しや間引きなどを多めに入れるとともに、肥培管理を十分に行って樹勢回復を図る。
(6) 高接ぎ樹の剪定
ア 高接ぎした枝が自由に伸びられる空間を与えるよう、中間台の枝を剪去する。
イ 接ぎ木本数が多いと3〜4年で混み合ってくるので思い切って間引きをする。
ウ 高接ぎ3〜4年後から中間台の果実の発育が劣ることもあるので、このような場合は中間台の樹冠を縮小し、また技量も薄めにする。
エ 中間台の枝を全部剪去する時期は、樹の大きさ、接ぎ穂の本数、位置、生育状況などで相違するが、接ぎ穂が30本程度の場合は3〜4午後、15本程度の場合は5〜6午後とする。
オ 接ぎ木本数が不足のためとか、枝の誘引が行われないために、枝の成熟が不十分なものが見られる。接ぎ木本数の足りないものはなるべく幹に近く、主枝や亜主枝に補充の接ぎ木を行い、枝の成熟不十分なものには誘引や捻枝、剪枝量の調節によって枝の成熟を図る。特に、斜立度が強く太くなった枝は、7月に枝の基部の腹面20cmくらいにわたって、深さは太さの1/3、間隔lcmくらいの鋸目を入れて縄で誘引する。誘引をすることのできない枝は冬期に適度の高さに切り下げる。
(7) 間植更新園の剪定
間植更新園では、老木の切りつめが不十分なために、間植樹の日当たりが不十分になり、また樹形構成にも支障をきたしている園が見られるので老木を思い切って切りつめ、若木の枝先との間が1mくらい離れるようにする。 |
|
3) 品種別剪定の要点
(1) ふじ
ア 未結実期
(ァ) 上枝が強くなりすぎ、上下の枝の釣合いをとるのが難しいので、主枝延長部は弱めに切返し、下部の主枝候補枝は強めに切返す。
(ィ) 先刈りすると他の品種より側杖が多く出やすいので、頂部から4〜5番目の枝を主枝候補枝にすると発出角度が広くよい枝が得られる。
(ゥ) 上方の主枝候補枝は、斜立が強すぎて意図する角度に維持できないことがあるので、このようなときにはけん制枝をうまく活用する。
イ 結実初期
(ァ) 下位の主枝候補枝が衰弱しやすいので、心枝の抑制を十分に行う。
(ィ) 斜立した枝でも結実しやすく、結実が始まると枝の衰弱が早いので結実部位は水平から上下30度の角度をもった枝を主体に構成する。
ウ 盛果期〜生産持続期
(ァ) 成り枝は結実すると衰弱や隔年結果が激しいので、丁寧に鋏を入れ、切上げを早めに行う。
(ィ) 日当たりの悪い枝に着いた果実は着色や食味が極端に劣るので、枝や樹の間隔を十分に保ち、各枝に日光を十分に当てる。
(ゥ) 新梢や長果枝の頂芽は花芽になりやすいが、これを開花結実させると果枝上に頂花芽が付きにくく、翌年の開花量が不足することがあるので、部分的に先刈りして果枝上に充実した花芽が多く付くのを助ける。
(ェ) 下垂した枝は早目に更新して枝を若く保つ。
(ォ) 無袋の場合、特に樹勢によって着色や糖度が異なるので、樹勢に応じた切り方を心掛ける。
(2) つがる
ア 枝は立ち上がる性質があるが、結実が始まると下がるので立ち気味の枝でも成り枝として使える。
イ 側枝が出にくいので切返しにより発生を促す。
ウ 2〜3年枝の短、中果枝に良果が生産されるので、母枝の軽い切返しで成り枝をやや若く保つ。
エ 成り枝が裸枝となったときは、思い切った切戻しをする。この場合、"こぶつきの枝'(一般には果(花)台枝から出たような枝)を残すように切り戻すとはげ上がりの少ない良い成り枝となりやすい。
(3) 王林
ア 枝が鋭角に出やすく、かつ立ち上がりやすいので誘引が必要である。
イ 2・3年以上の枝を無理に誘引すると裂けたり折れたりしやすいので、1年枝から誘引が必要である。
ウ 衰弱した枝には小玉が出やすいので切返しにより枝をやや強めに保つ。
(4) 陸奥
ア 未結実期
(ァ) 心枝が強くなりすぎ、側杖の生育が弱くなることがあるので、心枝の切返しは弱めにする。
(ィ) 主枝候補枝から側枝が発生しにくいので、適度の切返しにより側枝の発出を促す。
イ 結実初期〜生産持続期
(ァ) 中果枝に良果が生産されるので枝の先刈りを随時行い、中果枝の発生を促す。
(ィ) 立ち気味の枝に良果が成るので、水平〜30度くらいの枝を主体に結実部位を構成する。
(ゥ) 下垂した枝には良果が生産されないので早めに更新する。
(ェ) 成り枝は裂けたり下がったりしやすいので角度の広い枝を付け、割りを活用して成り枝を下がりにくくする。
(ォ) 無袋の場合、樹勢が著しく強すぎる樹や日当たりの悪い枝では青実が出やすいので、樹勢と日照には十分に気を配る。
(5) ジョナゴールド
ア 花芽が付きやすく豊産性であるが、枝の衰弱も激しいので、他の品種より早めに切返しを入れて枝の若返りを図る。
イ 着果の多い枝は新梢や果台枝の発生が極端に少なくなるので切返しを多めに入れる。
(6) 北斗
ア 若木
(ァ) 樹齢の若いうちは樹勢が特に強いので、剪定は間引き主体の弱剪定とし、樹勢の安定、早期結実につとめる。
(ィ) 主枝候補枝の有力なものには先刈りするが、そうでない枝は先刈りしない。
(ゥ) 心枝の切返しは、最上位の主枝候補枝が発出する高さまで行うが、切返し程度は延長新梢を50〜60cm位の長さ(新梢長の20〜30%)をめどに切り戻す。
(ェ) 心枝の抑制は5、6年生ころから徐々に行い、剪去は12、13年生ころとする。心枝の剪去時は最上位の主枝候補枝に花芽がよくついていることと、樹勢が適正で、下位の主枝候補枝との調和がとれていることがのぞましい。
イ 高接樹
(ァ) 樹勢が一般に強いことから結実が遅く、果実品質がよくないので、新梢長は25〜30cmに収まるように、果重は350〜400g中心の生産を心がける。
(ィ) 樹勢の強いものを適正な樹勢に導くには無勢定、間引き主体の弱剪定、誘引、けん制枝の利用、スコアリングなどがある。樹や枝の生育状況を見て対応し、早く適正樹勢に導く。
(ゥ) 主軸枝の延長新梢に対する切返しは骨格とする枝には必ず行い、それ以外の枝は行わない。
(ェ) 結実母枝として数年経過し、下垂してしょうが芽が多く、新梢の伸びが劣ってきた時はその状況に応じて適宜切返しを入れる。果台枝がある程度発出しているようであれば望ましい。
(7) デリシャス系
ア 斜立した枝は結実しにくいので、水平を中心に上下30度くらいの枝を主体に結果部位を作る。
イ 直立した強すぎる発育枝で成り枝を作ると花芽が付きにくく、早期落果を起こしやすいので、花芽の付きやすい素質の良い枝を選択して成り枝を作る。
ウ 結実した枝は下垂しやすい。下垂した枝は果実品質が特に劣るので、強めの切上げをして枝を若返らせる。
(8) 金星
ア ゴールデンデリシャスに似て枝は硬い。花芽の付きが良く、また、結実は早いので剪定は比較的容易である。
イ 成り枝には短果枝がスパー状に良く付くが衰弱も早いので、切返しで新梢や中・長果枝の発出を促す。
(9) さんさ
ア 樹姿は樹齢が若く、結実初期まではやや直立気味であるが、樹勢が落ちつき着果量が多くなるにつれて枝は開張してくる。
イ 樹勢は中位で、結果時期はデリシャス系より早く、つがるよりは遅い。結実母枝の短果枝の付きは良く、枝の下垂は概して早い。なお、枝が古くなってくると良芽が少なく、しょうが芽が多くなるので果台枝が多少出るくらいに強めの切返しを丁寧に入れる。
(10) 未希ライフ
ア 樹勢は若木の時に強く、苗木や高接ぎ樹では、3年以上の枝に立ち枝や角枝(直角に出る枝)が出やすい。
イ 結実後は年数が経るにつれて枝が開張し、その後下垂ぎみとなり、樹勢が弱くなる。したがって樹勢を回復させるためには、立ち枝を利用する。
(11) あおり9(彩香)
ア 短果枝の形成が多く、頂芽のみならず腋芽も花芽になりやすく、早期結実性である。
イ 幼木時からあまり果実を成らせ過ぎると樹勢の衰弱をまねき、果実肥大が不良となるので、樹勢を低下させないような栽培管理が必要である。
ウ わい性台木を利用すると樹勢が低下しやすいので、マルバ台を利用するか、またはマルバ台樹に高接ぎをした方がよい。
(12) あおり13
ア 枝の生長の仕方はあかねに似ており、若木の時は樹勢が強く、枝は直立気味に生長する。また、直立した枝では先端部付近だけから新梢が強く伸長し、その下の芽はほとんど短果枝だけとなる。
イ 花芽は比較的着きやすいが、短果枝よりも中〜長果枝に良品果が成る傾向にあるので、若い枝に対しては切り返しなど強い剪定を行わず、誘引を徹底することで中〜長果枝の形成を促す。
ウ 果実が成り込んで枝の勢力が弱まってくると、中〜長果枝が形成されず、短果枝がしょうが芽化するようになるので、その兆候が見え始めたら先刈りや切り返しを行い、枝の勢力回復に努める。
(13) あおり15
ア 樹の全体的な様相は、樹勢が弱めのふじに似ており、新梢は細く、やせた感じに生長し、頂芽もふくらみがなく、細長い。
イ 横枝の発生は比較的よいが、勢力が弱めになると、先端部付近だけの新梢が長く伸び、その下はすべて短果枝化するので、成り枝をつくる途中段階では強めの勢力を保持するように剪定する必要がある。
ウ 接ぎ木した時の新梢の伸びも他品種に比較して弱く、樹勢は落ち着きやすい。
(14) こうたろう
ア 枝は比較的硬く、1年生枝では先端部だけから新梢が強く生長し、基部側の芽は発芽率が低いため、はげ上がりが生じやすい。
イ 枝の勢力の強弱にあまり関係なく、花が咲いた短果枝や腋芽において、果台に頂芽が形成されないことが多く、このことも枝のはげ上がりを助長している。
ウ したがって、剪定は芽の形成状況をよく見て行う必要があり、はげ上がりが多い部分には切り詰めを入れたり目傷をつけるなどして、枝の発出を促す。 |
|
4) 樹勢別剪定の要点
(1)樹勢が強すぎる場合
ア 樹の特徴
(ァ) 斜立枝延長部先端の新梢が35cm以上で長さが不揃い。二次伸長も見られる。
(ィ) 徒長枝の発生が多い。
(ゥ) 頂芽が少ない。
(ェ) 結果枝には中、長果枝が多い。
(ォ) 樹肌は黒味を呈する。
イ 剪定のやり方
(ァ) できるだけ剪定を控えるが、枝が多くなり、混んできたら中枝を軽く間引きして樹冠内部まで日光が入り込むようにする。(ただし、残した枝にはあまり鉄を入れない)
(ィ) 若木などで主枝候補枝の数が多すぎる場合は、有力な候補枝を決めて、その枝の基部まで日光が入り込むように他の候補枝を漸時間引く。
(ゥ) 強すぎる発育枝は剪去し、短果枝から発達したような弱めの枝を多く残す。
(ェ) 若木や高接ぎで強過ぎる立枝には基部に鋸目を入れ、縄などで誘引してもよい。
(2)樹勢が適度の場合
ア 樹の特徴
(ァ) 斜立枝延長部先端の新梢が30〜35cmで太く、二次伸長が少ない。
(ィ) 頂芽のつきがよく、芽は大きくそろっている。
(ゥ) 果枝のうち短果枝がほば70〜80%を占める。
(ェ) 樹肌は灰白色か、やや赤味を呈する。
イ 剪定のやり方
(ァ) 下垂枝など衰弱に向かいつつある枝は切返し剪定を主体とし、上向枝や強めの枝は間引き剪定を主体として樹全体の樹勢の調和と維持を図る。
(ィ) 頂芽の多く付いている結実母枝などは、結果枝の間引きや新梢の先刈りなどで負担を軽くし下垂を抑える。
(ゥ) 若木から成木への移行期には骨格は永久的に固定できるよう腰を入れて(強めの切返しを行って)、長さと太さの釣合いをとる。
(3) 樹勢が弱い場合
ア 樹の特徴
(ァ) 斜立技延長部先端の新梢は30cm以下で細い。
(ィ) 花芽は多いが弱小芽が多い。
(ゥ) 結果枝はほとんど最短果枝か短果枝。
(ェ) 徒長枝はほとんど出ない。
(ォ) 樹肌は赤味を呈する。
イ 剪定のやり方
(ァ) 新梢は先刈りを多めにする。
(ィ) 結実母枝には切返しや間引きを多く入れる。
(ゥ) 花芽が多すぎる結果枝は蕾刈りなどを行う。
(ェ) 下垂枝は強い切上げを行う。
(ォ) 発育枝や徒長枝はできるだけ多く残し、古い枝の更新に努める。
(ヵ) 成りかすは整理する。
(キ) しょうが芽はよい芽を残して整理する。
(ク) 高接樹では中間台の枝を思い切って勇去する。 |
|
5) 花芽着生状況からみた剪定の要点
花芽着生状況によって樹勢の判断ができ、その年の結実量や着果量が読みとれ、そのことが生育後の樹体に与える影響もある程度推測できる。そこで、自園の花芽状況を確かめ、樹勢の適正化や樹体への悪影響をできるだけ少なくするために、花芽着生状況に合わせた剪定を行う。
(1) 花芽が多い場合(70%以上)
花芽が多いことから、樹勢は適正から弱い方向にあると判断され、結実量が多くなることによって樹体養分の消耗が多くなり、さらに樹勢の低下を招き、果実の肥大や品質、花芽形成などに悪影響を及ぼすことが考えられる。したがって、下記の点に留意して剪定作業を行う。
ア 成木で骨組みの枝が多い場合は、思いきって大枝を整理する。
イ 成り枝には切り返しや間引きを多く入れ、弱った下り枝や弱りそうな下り枝は切り上げを行い、樹勢強化をはかる。
ウ 花芽の多い成り枝に対しては、摘果のつもりで弱小芽を剪去し、良い芽を残す。
エ花芽の多い樹では、次年度以降の結実枝とするために予備枝を多めに残す。
オ成り疲れで樹勢が弱り、花芽が多すぎたり、弱小芽が多く、新梢も短く細いような樹では、結果枝の蕾切り、蕾刈り、先刈り及びしょうが芽の整理などを徹底する。また、発育枝は多めに残して、樹勢の強化に努める。
(2) 花芽が少ない場合(50%以下)
花芽が少ないと、枝の伸長が旺盛になり易く、樹勢が強くなることが考えられる。したがって、下記の点に留意して剪定作業を行う。
ア 樹冠内部に光が入るような配枝に努めるが、強勢定は控え、結実母枝の間引き剪定にとどめる。その場合、残った枝には鉄入れを少なくし、花芽量の確保をはかる。
イ 強すぎる発育枝は剪去するが、短果枝から発出したような弱めの枝は多く残す。
花芽調査の仕方
次の手順で行う。
①11月(収穫後)から剪定前までの時期に、樹の南北から5年生ぐらいの枝を1本ずつ切り取る。
②枝から頂芽を全部採取する。
③採取した頂芽を3ミリ以上と3ミリ以下(弱小芽)に区分し、カミソリやよく切れるナイフを使って、芽の中央でたて割りにする(図参照)。
④切断面をルーペを使って調べ、花芽か葉芽かを見分ける(図参照)。
⑤調査した頂芽数に対する花芽数の割合が花芽分化率である。
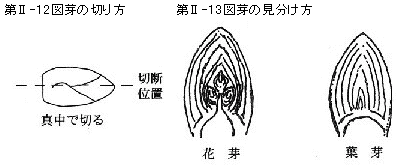 |