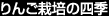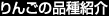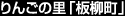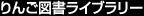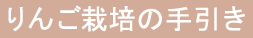|
|
|
| 4.��v�a�Q�̖h�� |
|
1)�@�����a
�����ʐϗ��́A���a63�N�ȍ~�����Ɍ����������Ă������A�������N��15%�O��Ɖ����ƂȂ��Ă���B�n��ɂ���ẮA�����X���ɓ]���Ă���Ƃ��������̂ŁA�h��������܂ňȏ�ɋ�������K�v������B
(1)�@���Ԃ̊T�v
�A�@�}�����E�E�E�E�E�E4�`5�N���ȉ��̔�r�I�ׂ��}�Ɍ`�����ꂽ�a���B��ɉʑ�♒�荭�A�}�̐�͂ꕔ�ɒW���F�̕a�����`������A�₪�Ď}�͂�ƂȂ�B
�C�@�������E�E�E�E�E�E�劲���}���̑�}�Ɍ`�����ꂽ�a���B�t��ɂ͕a��������C�����тĒ����F��悵�A�w�ʼn����ƒe�͐�������A�A���R�[���L����B
�E�@�ۂ̔��牷�x�E�E�E�E�E�E5�`35���A�K��25���B
�G�@�i��ԍ��فE�E�E�E�E�E�}�����̔��a�ɂ͖��炩�ȍ��͂Ȃ����A�ʕ�(��)�̗����ɂ����k�̍K�A�ӂ��y�э����ł͓E�ʌ�̉ʕ������ɂ��ʑ䔭�a�������B
�I�@���������y�ѐN�����ʁE�E�E�E�E�E�������ł������͎̂��n�ォ�痂�N��6�����܂ł̊��ԂŁA�E�ʌ�̉ʕ���̉ʍ�(�ʎ������n������)�A���荭�Ȃǂ̐V������������N�����₷���B�Â��Ȃ�����������͐N�����ɂ����B
�J�@�������甭�a�܂ł̊��ԁE�E�E�E�E�E�a���ۂ��N������ƁA��1�N�Ԃ�v���ēT�^�I�ȕa�����`������
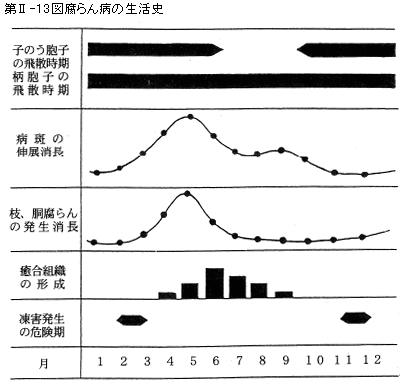
(2)�@�ώ@�̗v�_
�}������12�A1���̑��������ɂ������邪�A������3���ȍ~�Ɍ����̂ŁA����̎��ɒ��ӂ���Ύ��炪���ς��Ă���}���ł���B����E�W�t��ł͔��a���ʂ̏㕔�����肵�Ȃ����͎�����̂Ŕ������₷���B�������͎}�����̂ǂ��ɂł��������邪�A�}�̕����}�w�ʂ̓k���}��������Ջy�ю}�̐،��Ȃǂ��甭�a���Ă���ꍇ�������B�~�J���ɂ͕a����̎q��(���F�̃u�c�u�c)���琟�F�̔S�t�o���邪�A����͕��E�q�̏W��ł���B
(3)�@�h���̗v�_
��U�z�����ɗ��邱�ƂȂ��A�e�����͂��イ��̎{�p�ȂǍk��I������킹�čL��I�ɍs�����Ƃ���ł���B
�A�@�\�h
(�@)�@���n��U�z
���n��̖�U�z�́A�̉ʍ��Ȃǂ���̊����h�~���ʂ������̂ŁA�ł��邾�����߂ɐ��V�̓���I��ŕK�����s����B�U�z��܂́A�g�b�v�W��M���a��1,000�{�A�x�����[�g���a��2,000�{�A�׃t�����t��1,000�{�̂�����ł��悢�B
(�B)�@��o�������̎U�z
��o�������̖�U�z�́A���n��U�z���l�Ɍ��ʂ������̂ŁA�K�����{����B�U�z��܂́A�x�t�����t��1,000�{�Ƀ}�V��������(97)100�{�����p���Ēx��Ȃ��悤�ɒ��ӂ��ĎU�z����B
(�D)�@����30���㍠�̎U�z
�g�b�v�W��M���a��1,500�{�y�т׃����[�g���a��3,000�|�͓E�ʌ�̉ʕ������̖h�~���ʂ������̂ŁA�����̑������ł͗���30���㍠�̊��܂ɕK�����p����B
(�F)�@�E�ʍ܂̊��p
(�E�ʂɂ���ĉʑ�Ɏc���ꂽ�ʕ�������a���ۂ��N�����Ċ�������̂ŁA�E�ʍ�(�~�N���f�i�|�����a��)��ϋɓI�Ɏg�p���ĉʑ�ɉʕ����c��Ȃ��悤�ɂ���(�u��܂ɂ��E�ʁv�̍����Q��)�B
(�H)�@�����̒���
����̍ہA�}�̕t��������ł��邾���؊����c�����ɐ���̂��ǂ��B��c���������ƔS�ꍞ�݂������A�����a�ɂ�����₷���B���莞���͌o�c�K�͂�J���͎���ɂ���ĈقȂ邪�A�����a�\�h�̏ォ�珉�~�⌵�����͔����A�ł��邾��3���ȍ~�Ƃ���B
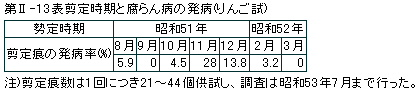
(��)�@�،��y�я����̕ی�
����ɂ���Đ������،��ɂ́A�o�b�`���[�g���ł��邾�����̓��̂����ɓh��A�����̖h�~�ƃJ���X�`���̑��i�ɓw�߂�B
(�L)�@�e����
�������͑��t���甭�a���A�a�����g�傷��B����O�ɑe������s���Ɠ������𑁊��ɔ������邱�Ƃ��ł��A�������̑��������E�������Âɖ𗧂̂ŕK�����{����B
(�N)�@���n���̒���
�{�a���ۂ͎��n���ɂ�܂�A�锲���Ƃ��Ďc�����ʕ�����N�����Ĕ��a���邱�Ƃ������̂ŁA�ʕ����ʑ�Ɏc��Ȃ��悤�ɒ��J�Ɏ��n����B�ʕ����c�����ꍇ�͕K���ʑ䂩���菜���B
(��)�����̓K����
�������ア���͕����a�ɂ�����₷���̂ŁA�抠��Ȃǐ�Ԃ��𑽂߂ɂ���������s���ƂƂ��ɗt�ʎU�z��͔�}���`�����{����B�܂��A�������ɒ[�ɋ����Ɠ��Q�ɂ��N����˂̑�����{�a�ɑ����R���̒ቺ���܂˂��̂ŁA����͊Ԉ�������̂Ƃ��A�{���������āA�����̓K�����ɓw�߂�B
(�R)�@�͂��イ��{�p
�͂��イ����{�p����ƕ����a�ɑ�����̂̒�R�������܂�A���a���ɂ����Ȃ�B�����͔|�����p���Ȃ���ϋɓI�ɑ͂��䂤����{�p����B
�C�@����
(�@)�@�}�����̐��菈��
�}�����͙���̍ۂɂ͓O��I�ɐ��邱�Ƃ͂������A5�`6���ȍ~�����a���Ă���̂Ő��������A�����������B�܂��A�a���ۂ͊O�Ϗ�̕a��������܂ŐN�����Ă���̂ŁA����ۂ͌��S����5cm�ȏ�܂߂Đ���A�a���ۂ��c��Ȃ��悤�ɂ���B����ꍇ�́A���̌�̃J���X�`����ǍD�ɂ��Č͂ꍞ�݂����Ȃ����邽�߂ɁA���S�ȉ�(�܂��͎})�̂�����ōs���B���������藎�Ƃ�����Q�}�����̂܂܉����ɕ��u����ƁA��������a���ۂ���U���A�܂̂��ƂɂȂ邩��K����������B�Ȃ��A���S�Ȏ}�ł����Ă����������Ƃ͉����ɕ��u������A�x���ȂǂɎg�p���Ȃ��B
(�B)�@�������̏��u
���莞���琏��������������ē������̑��������ɓw�߁A��Q���ɂ͎��̂����ꂩ�̏��u������B���Õa���̑傫���}�����͐܂�₷���Ȃ�̂ŁA�K�X�x��������B�Ȃ��A���a��������2/3�ȏ�̑�^�a���ł͎��������ɒ[�ɒቺ����̂ŁA�}���Ɛ藎�Ƃ��ď�������B
i�@�����@�ɂ�鎡��
�a�������p�̃i�C�t���͌g�ь^�̍����@�u����X�N���[�p�v�ō����A���̐Ղɓh�z�܂�h���Ď��Â�����@�ł���B�g�p����h�z�܂ɂ́A���̗L����������������̐[���Ƃ���܂ŐZ������^�C�v�ƐZ�����Ȃ��^�C�v��2��ނ�����̂ŁA���ꂼ��̓�����ǂ��������ĊԈႢ�̂Ȃ��悤�ɍs���B�Ȃ��A�a���ۂ͎}�����̏ꍇ�Ɠ��l�A�a�����E������2�`3cm��̌��S���ɂ܂ŐN�����Ă���B�؎����ł�1cm�O��̐[���܂ŐN�����Ă���B���Â͂��̂悤�ȕa���ۂ̐N���͈͂ɏ\���z�����Ď��{����B
�@�g�b�v�W��M�I�C���y�[�X�g�ɂ�鎡��
�{�܂̗L�������͎�������̐[���Ƃ���܂ŐZ������̂ŁA�ȉ��̎菇�ŕa�����Ǝ��ӌ��S�\���������ēh�z����B�a���̋��E�����m�F���A�����̕��s��������������B���ɁA��܂̐Z���������߂邽�߁A�a�����E������O���̌��S�Ȏ���\�w������1�`2mm���x�ɔ������B���͈̔͂́A�㉺�����ł�4�`5cm�A���E�����ł�2�`3cm�Ƃ���B��������Ղɂ̓g�b�v�W��M�I�C���y�[�X�g�J�ɓh�z����B�����͏E���W�߂ď�������B�Ȃ��A�{�܂̗L�������͑ϐ��ۂ��₷�������������Ă���̂ŁA�Ĕ��a�����ꍇ�͒����Ɏ��̇A�ɂ����@�A���邢�͓D�����@�ōĎ��Â���B�{�܂͎��Ì�̃J���X�`����j�Q����X���������̂ŁA�J���X�`������鐊����̕����a���Âɂ͓K���Ȃ��B�܂��A��ƕa�ɑ�����ʂ����̂ŁA���荭�Ȃǂ̐،��ی�ɂ��g�p���Ȃ��B
�A�t�����J�b�g�X�v���[�A�o�b�`���[�g���̓x�t�����h�z�܂ɂ�鎡��
�����3��ނ̓h�z�܂͗L����������������ɐZ������̂ŕa���������łȂ����ӌ��S�����Ă��˂��ɍ�����Ă���h�z����B��Ǝ菇�͈ȉ��̂Ƃ���ł���B�a�����̍����́A�}�����̏㉺�����ɉ����ĕa�����E������5cm���炢�O���܂ł̌��S�����܂߂čs���B���̏ꍇ�A��������Ղ��a���`�ɂȂ�悤�ɂ���B�܂��A����̐ؒf�ʂ��؎����ƒ��p�ɂȂ�悤�ɂ���ƁA���̌�̃J���X�`�����ǂ��B��������Ղɂ̓t�����J�b�g�X�v���[�A�o�b�`���[�g���͂׃t�����h�z�܂̂����ꂩ��h�z����B�������A�׃t�����h�z�܋y�уt�����J�b�g�X�v���[�ł̓J���X�`�����i���ʂ����҂ł��Ȃ��B�����͏E���W�߂ď�������B
�A�@�D�����@
�D�����͎��̎菇�Ŏ��{����B���������Ēc�q��ɂ��˂��D���A�a��������5�`6cm�L�߂ɁA3�`5cm�̌����ɒ���t����B����ɂ��̏���r�j�[�����̓|���G�`�����ȂǂŔ핢���A�����̓D�̊�����h���悤�ɂ��Ė�1�N�Ԃ��̂܂܂ɂ��Ă����B�D�������s���ꍇ�A�a�����͍��Ȃ��Ă��悢���A�a�������ȒP�ɍ�����Ă���D�������s���ƈ�w���ʓI�ł���B�Ȃ��A�ΎR�D�y����g�p����ꍇ�́A�e�ϔ�œy��9�ɑ��ēy����ǎ��ނ̈��ł���׃��g�i�C�g1�������Ă��˂�ƔS�����������A�D������Ƃ̔\�����ǂ��Ȃ�B�D�����ɂ͓y�Ƃ׃��g�i�C�g���悭�����Ă��琅�����ė���B���̍ہA�x���g�i�C�g�͗ʂ����߂���Ǝ��炪���s���A�������ʂ��ቺ����̂ʼn�����ʂ����Ȃ��悤�ɂ���B�D�����Œ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��_�́A�핢�����œD�̕t���Ă��Ȃ������̔�w�������s(�������s)���邱�Ƃł���B�����h�~���邽�߂ɂ́A�Ƃ��ǂ����s�̗L����_������Ƌ��ɁA�핢������������ꍇ�́A�������ߎ��ɂȂ�Ȃ��悤�Ɏ�߂ɍs�����ƁA�D��������Α��̔핢���ɏ����������āA���H�����܂�����ߎ��ɂȂ�Ȃ��悤�ɂ��邱��(���ɁA�����ɋ߂��}�̏ꍇ�͑�ł���)�y�є핢����K�v�ȏ�ɍL�����Ȃ����Ƃł���B
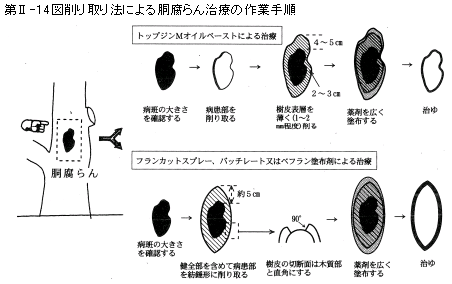
(�D)���ڂ��Ȃǂɂ�������
�������ɂ�����A�傫����w������������ꍇ�́A���������シ��̂ŋ��ڂ����s���A�����ɓw�߂�B�܂��A�A�f�̗t�ʎU�z�Ȃǂɂ�������}��B
(�F)�@���r��Q���̍X�V
�������̔��a���������A��}�ȂǑ唼�̎}����������A���ʂ������������������́A���Ñ���u���Ă����e�ՂłȂ��A�܂���������ɂ��Ċ������������B���ɂ͕a���ۂ̓`�����ɂ��Ȃ肩�˂Ȃ��̂ŁA�̌����݂̂Ȃ��ꍇ�͂ނ���ϋɓI�ɔ��̂��������ǂ��B���������āA�����a�̔����̌��������ł͕�A�p�c�̗{���𑁂߂ɍs���A�X�V���~���ɍs���B
�E�@�L��h���̐��̊m��
�ŋ߂̑������v���̈�ɕ��C�����邢�͊Ǘ��s�lj������͂ɉe����^���Ă��邱�Ƃ���������B�����a�h���͌X�̔_�Ƃ̓w�͂���{�ł��邪�A�����ɍL��h���̐����Ƃ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |
|
2)�@�����a
�������N�ȍ~�����͏��Ȃ߂Ɍo�߂��Ă������A����5�N�͑S���I�ɑ������A����10�N�ɂ��������ڗ������B���̂悤�ɖ{�a�́A����E�����̓V�����ƌ���������̒n��ł��������錜�O������B�e����ɒ��ӂ��A�K���h���ɓw�߂邱�Ƃ��d�v�ł���B
(1)�@���Ԃ̊T�v
�A�@�a���ۂ͔�Q���t�A�}�̕a���y�щ�̗ؕЂʼnz�~���邪�A���̒��Ŕ�Q���t�͗ʓI�ɂ������A��ꎟ�`�����Ƃ��čł��d�v�ł���B
�C�@��Q���t�ɂ͗��t�܂łɎq�̂��k�A�q�̂��A�q�̂��E�q�����Ɍ`������A���n�����q�̂��E����������B�~�J������Ǝq�̂��E�q���q�̂��k����͂��������A�t��ʎ��ɕt���A�N�����čŏ��̕a�����`������B
�E�@�q�̂��E�q�͒ʏ�J�Ԓ��O���痎��20���ケ��܂ő�����U���邪�A���ɗ��Ԋ�����̔�U�ʂ������B������5������ł���A6���n�ߍ����瑝������B
�G�@�a����ɂ͕����E�q���`������A�~�J������Ɣ�U���ėt��ʎ��ɐV���ȕa�����`������B�q�̂��E�q�ɂ�锭�a�������ꍇ�A�����E�q�̔�U�ʂ͎q�̂��E�q���͂邩�ɑ����A�����ɂ���Đ������Q����范�����Ȃ�B
�I�@�����E�q�ɂ�銴���͏H�܂ŌJ��Ԃ��s���邪�A�^�Ă̍������ɂ͈ꎞ�����B
�J�@�ʎ���8���ȍ~�Ɋ��������ꍇ�A���n���ɕa�����F�߂�ꂸ�A�������ɔ��a���Ă��邱�Ƃ�����B
(2)�@�ώ@�̗v�_
�A�@�t�ł͍ŏ����a��mm�A���͕s���Ă̗Ί��F�̏����_�Ƃ��Č���A�������ɂ������悷��B���̌�A�a���͂��g�債�A���F�`�Ê��F�̂�����̔��_�ƂȂ�B������Ɍ�����͕̂����E�q�������`������Ă��邩��ł���B
�C�@�a���͗t�̕\��������ɂ��������邪�A�����ɂ͂����ꂩ����Ɍ����邱�Ƃ�����A���ʂɔ��������ꍇ�ɂ͌������₷���̂Œ��ӂ��K�v�ł���B
�E�@�t�̕\�ʂɌ��ꂽ�a���͌Â��Ȃ�Ɨ��N���A���ɂ͌��������B
�G�@�������������ꍇ�ɂ�1�t������̕a�����������A���ɂ͗t�̈ꕔ���͑S�̂������ɕ���ꂽ�悤�ɂȂ�A�����ɗ��t����B
�I�@�ʎ��ł͍ŏ����F������̏����_�ƂȂ��Č����B�c�ʂł͂��������̎��ӂɔ��a���邱�Ƃ������A�t�ɏH�Ɋ��������ꍇ�͂錳�⌨�ɑ������a����B
�J�@�c�ʂɔ��a�����ꍇ�A�a���͉ʎ��̔��ƂƂ��Ɋg�債�A�Ǐ�������炩���Ԃ���ɂȂ�B�ʎ��͐���Ȑ��炪�}�����邽�߁A��`�ɂȂ�����A��������ʂƂȂ����肷��B
�L�@�t�Ɋ�����A�a���������O��EBI�܂��U�z�����ꍇ�A�����F�`���F�̎����^�a�����������邱�Ƃ�����B
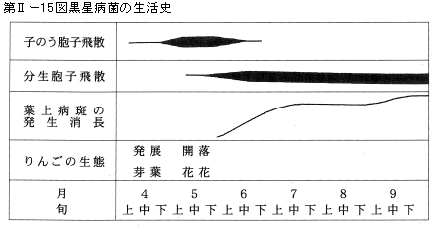 |
|
3)�@���_���t�a
�ߔN�A�{�a��9�����{�ȍ~�ɋ}������ꍇ�������B8������܂ł̖h���ŕa���ۖ��x��ቺ�����Ă������Ƃ���ł��邩��A�C�ۂɗ��ӂ��A�h���Ɏ蔲����̂Ȃ��悤�ɂ���B
(1)�@���Ԃ̊T�v
5���E�E�E��{�ȍ~�A�z�~��(��Q���t�Ɣ�Q�}��̕a��)��ɕ����E�q���`������A��U����B���{�ɗt�ɕa�������߂Ĕ�������B
6���E�E�E�t�̕a�����Q�����A�f���V���X�n�i��Ȃǂ̂�a���i��ł͗c�ʂւ̕a���ۂ̐N�����n�܂�B
7���E�E�E�t�̕a�����������A���t���ꕔ������B�L�܉ʂ͒��`���{����ʎ��ւ̕a���ۂ̐N�����n�܂�B
8���E�E�E�a����ɑ�ʂ̕����E�q���`������A��U����B�t�̕a�����܂��܂��������A���t��������B�V���ɂ��a����������B�ʎ��ւ̕a���ۂ̐N��������ɂȂ�B
9���E�E�E���t����������B�ʎ��a���������Ȃ�B
(2)�@�ώ@�̗v�_
�A�@�t�̕a��
5������ɏ����a�����`������A6�����玟��ɑ������A7������ȍ~�}������B�{�a�͍����A�����ŋ}������̂Œ��ӂ���B�a���ɂ͉~�`�a���Ɨ���^�a����2�̗[�C�u������B���̂�������^�a���������Ȃ�Ɨ��t���������A��Q���傫���Ȃ�B
�C�@�ʎ��a��
�f���V���X�n�i��Ȃǂ̂�a���i��ł�6�����甭�����邪�A�ӂ��A�����Ȃǂ̗L�܉ʂł�7�����{���甭������B
�E�@�}��a��
��Ƃ��ēk���}�̔�ڂ𒆐S�Ɍ`�������B
(3)�@�h���̗v�_
�A�@��ܖh��
(�@)�@�����h���E�E�E���Ԓ��ォ�痎��15���㍠�܂ŁA���̂悤�Ȗh���̌n�Ŏ��{����B
���Ԓ��� EBI������
����15���㍠ EBI������
(EBI�����܂̎�ނɂ��Ắu�����a�̍��v���Q��)
(�B)�@����h���E�E�E����30���㍠�ȍ~�͖{�a�̔����ɒ��ӂ��Ȃ���8�����{�܂Ŏ��̂����ꂩ�̖�܂��U�z����B
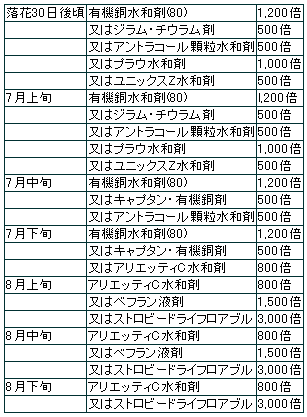
(�D)�@�h����܂̎g�p��̗��ӓ_
�@�@7������ȍ~�ɔ��_���t�a�̋}���̌��O�̂���ꍇ�͊��܂Ƀ|���I�L�V��AL���a��1,000�{���̓��u���\�����a��1,200�{�����p����B
�A�@�|���I�L�V��AL���a�܋y�у��u���[�����a�܂͖�ܑϐ��̐S�z������̂ŁA7�����{�܂ł͂ł��邾���g�p���Ȃ��悤�ɂ���ƂƂ��ɓ����܂̘A���U�z�͔�����B
�B�@�׃t�����t�܋y�уA���G�b�e�BC���a�܂͑��܂ƍ��p����ꍇ�A�Ō�ɉ��p����B
�C�@�v���E���a�ܖ��̓��j�b�N�XZ���a�܂͂����Ƃ��ɑ��Ė�Q�������錜�O������̂ŁA��U���Ȃ��悤�ɂ���B
�D�@���j�b�N�XZ���a�܂̓N���[�o�[�ނɖ�Q���錜�O������̂ŁA��������琶�珉���̃N���[�o�[�ނɔ�U���Ȃ��悤�ɂ���B
�E�@�X�g���r�[�h���C�t���A�u���̓X�~�`�I�����a�܂Ƃ�2�퍬�p�A���邢�̓X�~�`�I�����a�܂ƃI�}�C�g���a�ܖ��̓_�[�Y�o�����a�܂ƃI�}�C�g���a�܂Ƃ�3�퍬�p�ŁA����ɉ��ϗ��t�̖�Q���鋰�ꂪ����̂ŁA����ɂ͎g�p���Ȃ��B
�F�@�X�g���r�[�h���C�t���A�u���͊J�Ԋ��ȍ~�̂����Ƃ��ɑ��āA�t�Ɋ��ςȂǂ̖�Q��������̂ŁA���ӂɂ���ꍇ�͂�����Ȃ��悤�ɒ��ӂ���B
�C�@�ʎ���Q�h�~
���܂ɂ���̂��ł����ʓI�ł��邪�A�L�܍͔|�̏ꍇ��7�����{�ȍ~�ɉʎ��a���̔����̊댯���������Ȃ�̂�10�����Ƃ̎U�z�����B
�E�@�s�v�Ȕ���}�̙���
6���ȍ~�ɐ����s�v�Ȕ���}�����ĕa���ۂ̓`�������Ȃ�����B |
|
4)�@��H�a
�X���ɂ������H�a�̔�Q���͖�1��������̂Ɛ��肳���B�ŋ߁A�]�������̏��Ȃ���������H�a�̔�Q���������Ă���B��H�a�͓y��Ƃ������G�Ȋ�������Ɩ��ڂɊW���Ĕ�������̂ŁA�X�̑�𑍍��I�ɍs���Ėh���ɓw�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
(1)�@���Ԃ̊T�v�Ɗώ@�̗v�_
�A�@��H�a�ɂ͔���H�a�Ǝ���H�a�������āA���a�Ƃ������łȂ��Ԃǂ��A�Ȃ��Ȃǂ̉ʎ���K�Ȃǂɂ���������B
�C�@�����ɂ͖�H�a�̔������₷���ΎR�D�y��̉��n�Ɣ����̌����Ȃ��������ϓy��̉��n������B
�E�@�n�㕔�̏Ǐ�
(�@)�@�����̏Ǐ�͏H�̗��t�������A�ʎ��̒��F���ǍD�ŁA����̐F���W���Ȃ�B
(�B)�@�����̏Ǐ�͐V���̐L�т����A�t�F�����W���A�ԉ�y�ђ��ʗʂ���⑽���Ȃ�B
(�D)�@����ɂȂ�ƐV���̐��炪���������A�t�����ς��A�ʎ������ʂɂȂ�A����������������Č͎�����B
�G�@�n�����̏Ǐ�
����H�a�F���̕\�ʂɔ��F�̋ێ������t�����A������������ƈ×ΐF�ɂȂ�B�؎����̕\�ʂƓ����ɂ͔��F�̐��y�ѐ���̋ێ�����������B�a���ۂ͑g�D���ɐ[���N������̂ŁA�\��Ɩ؎����͗���ɂ����B
����H�a�F���̕\�ʂɊ��F�`�����F�̋ێ������Ԗځ`�}�b�g��ɕt������B�Ă���H�Ɋ��̒n�ە��Ɏ��`���F�̎q���̂��}�b�g��Ɍ`�������B�a���ۂ͍��̔�w�����s������̂ŕ\��͖؎�������e�Ղɗ����B
(2)�@�\�h�@
��H�a�̔������S�z�����ꏊ�ł̓N�����s�N�����œy����ł�����ɍ͐A����B���̏ꍇ�A�ʏ�͉��L�̑S�ʓy����Ŗ@�łقڗ\�h�ł��邪�A���ɕa���ۖ��x�������ꏊ�ł킢���͔|���s���ꍇ�͍���Ւf�@�ŗ\�h����B�������A�t�߂ɏZ���{�ɂ̂��鉀�n�ł̓N�����s�N�����ɂ����ł͍s�킸�A�A�����q�y��͔|�Ǘ�����̂Ƃ����\�h���s���B
�A�@�N�����s�N�����ɂ��Ւn���Ŗ@
�{�܂͓y�뒍���O�̐[�k�A���n�Ɠy�뒍����̃|���G�`�����t�B�����핢�ɂ���Ĉ��肵���h����������B���Ƀ|���G�`�����t�B�����ɂ��핢���s�\�����ƌ��ʂ���邾���łȂ��A�ꍇ�ɂ���Ă͖�܂��}���ɋC�����Ď��ӂ̔_�앨��l�{�ɔ�Q���y�ڂ����O������̂ŁA�������������Ă������Ȃ��悤�Ƀ|���G�`�����t�B�������Œ肷��B�Ւn���ł͈ȉ��̊�ōs���B
(�@)�@��������s���O�ɐV�퉀�A���A���y�є�Q�Ւn��[�k���āA��Q���͂�����S�������̑召���킸�A���J�ɏE���W�߂ď�������B
(�B)�@���n�������ƁA��p�̓y����ŋ@��p���āA30cm�l����1�J���̊����ŃN�����s�N�����̌��t(99.5%)5ml��[��30cm�ɒ������A�����ɒ������ł߂�B�Ȃ��A�y����ŋ@�ɂ͎����^�C�v�A�����^�C�v�A�n���f�B�^�C�v��3��ނ�����B
(�D)�@�����͏t����H�ɍs�����A�������ɂ͍s��Ȃ��B�܂��A������ɂ͕K������0.03m�̃|���G�`�����t�B�����Œn�\�ʂ�핢����B
(�F)�@3�T�Ԉȏ�핢������A�핢������菜���A��܂̏L�������Ȃ��Ȃ��Ă���A�y����ǂ��s���ĐA���t����B
�C�@����Ւf�@
�{�@�͎���������̕ۋۓy�납��|���G�`�����t�B�����Ŋu�����A�����̊u���y����N�����s�N�����ŏ��ł��Ă���͐A������@�ł���(�U-16�})�B�͐A��������4m�A����2m�Ƃ����ꍇ�̎菇�͈ȉ��̂Ƃ���ł���B
(�@)�@�����2m�̗����B���[�ɍa����15cm�A�[��80cm�̍a���@��B���̍ہA�g�����`���[���g�p����ƌ����悭��Ƃł���B
(�B)�@���̍a�Ɍ���0.1mm�A��135cm�̃|���G�`�����t�B����������B���̏ꍇ�A�t�B���������ɖ�������悤�ɍa��܂Ŗ��݂��A�n�㕔�ɂ�20cm���x�c���B�܂��A�|���G�`�����t�B�����̌p������������Ւf�̖��[������2m���x��d�ɏd�˂�B�Ȃ��A�Ւf�ɂ͕K���|���G�`�����t�B�������g�p���A�r�j�[��(�|�r�A���r)��|���I���t�C���n���ނ͎g�p���Ȃ��B
(�D)�@�Ւf���������Ƀ���^���[��������B���̍ہA�Ւf���ނ�j�����Ȃ��悤�ɒ��ӂ���B���̌�A�N�����s�N�����𒍓�����(�����ʋy�ђ����[�x�͏�L�̑S�ʓy����Ŗ@���Q��)�B
(�F)�@�������A���������0.03m�̃|���G�`�����t�B�����ŕ����B��3�T�Ԍ�ɔ핢�����������A�K�X���������Ă���͐A����B
(�H)�@�|���G�`�����t�B�����͒n�㕔�t�߂ł͔N�����o��Ɣj�����A�������̕�������Ւf��ȊO�̖����ŕ����L�����Ĝ�a���邱�Ƃ�����̂ŁA���̍��������������폜����B
(��)�@�͐A����������4m�A����2m�ɂ����܂�Ȃ��悤�ȏꍇ�ɂ́A�����|���G�`�����t�C�����̉��[����Ւf��O�̖����ŕ����ɐL�����Ĝ�a���邱�Ƃ�����B
�E�@�y�����
�y����ł��s������ɍs���B�S�ʏ��Ŗ@�ł͑S���̓y����ǂƐA�������ǂ��A����Ւf�@�ł͎����̓y����ǂƐA�������ǂ��s��(�u�V�A�y�ѐ������̓y����ǁv�̍����Q��)�B
�G�@�A�����q�y�ɂ��\�h
�킢���͔|�ɂ����Ă͐A����(60×60cm)�ɏ������ϓy����q�y����Ƌɂ߂č����\�h���ʂ�����B���̏ꍇ�A�ΊD���엿�Ɨn���胓����{�p����B�q�y���鉫�ϓy���X������y�뒲�����ނŎ����ƁA�Ìy�n���ł͉��{���A����ړ��ȂǁA����n���ł͓암�����K���ł���B
�I�@�A���t�����̕c�؏���
����H�a�F�A�t���O�ɕc�̍������g�b�v�W��M���a��500�{�t���̓x�����[�g���a��1,000�{�t�̂����ꂩ��10���ԐZ�ׂ���B�Z�Ќ�͍����������Ȃ��悤�ɂ��āA�ł��邾�������A���t����B
����H�a�F�g�p�ł����܂��Ȃ��̂ŁA���S�c��I��ŐA���t����B
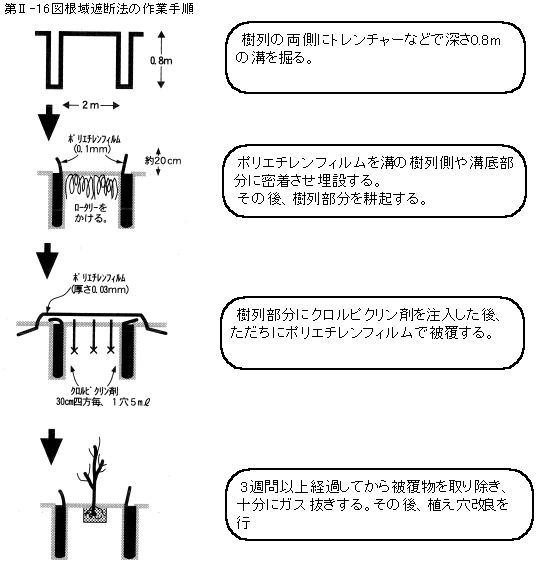
�J�@�K���Ȏ����̊Ǘ�
(�@)�@�͔�}���`���s���ƍ����\�h���ʂ�����̂Ŏ��̂悤�ɍs���B�킢������ł͔͑�������S��1m�l����30kg(���1�t��)�A���ʑ���ł�2.5m�l����180kg�N�}���`����B
(�B)�@�r���a�̐ݒu�A���A�����͔|�Ȃǂ��s���āA������点�Ȃ��悤�ɂ���B
(�D)�@��|�Ǘ���ǍD�ɂ��Ď��������ɓw�߂�B
(�F)�@�����������A���̂ɋ}���ȕω���^���Ȃ��B
(�H)�@����}�𗘗p���Ď�����Ԃ点��B
(��)�@�ʎ��𐬂点�߂���Ɣ������}������A���a���₷���Ȃ�̂œK���Ȓ��ʗʂɂ���B
(�L)�@�킢���͔|�ɂ����Ă͎������サ�₷���̂ŁA���������ɓw�߂�B�܂��A�c���}���o��ؕt���̏ꍇ�ɂ́A���ڕa�ɂ���H�a�̗U����h�����߁A�}���o�������Ďg�p���邩�A�i��A��Ƃ��E�C���X�t���[�̂��̂��g�p����B
(3)�@���Ö@
�A�@��������
(�@)�@���Â͔��a�����ɍs�����Ƃ��ł���ł���B
(�B)�@��a���������ɔ�������ɂ͉��ϗ��t�̑������A�}�ɒ��F���ǍD�ɂȂ������A�V���̐��炪�������y�є��a���ׂ̗̎��̍������@��a���ۂ̊��ώ@���A����H�a�Ǝ���H�a����ʂ���B
�C�@�I�o�@�ɂ�鎡��
(�@)�@��a���͓y���@��グ�A����I�o�����Ĕ�Q���x������B
(�B)�@����8���ȏ㕅�s���Ă���ꍇ�ɂ͔��̏������A�\�Ȕ�Q����ΏۂɈȉ��̎菇�Ŏ��Â���B
(�D)�@�y���@��グ�A��a���̍���I�o�����āA��[�܂ŕ����������͎�菜���A��[�����S�ȍ��͔�Q���������B
(�D)�@�y���@��グ�A��a���̍���I�o�����āA��[�܂ŕ����������͎�菜���A��[�����S�ȍ��͔�Q���������B
(�F)�@����H�a�̏ꍇ�̓g�b�v�W��M���a��1,000�{���̓t�����T�C�hSC1,000�{�A����H�a�̏ꍇ�̓_�C�Z���X�e�����X�t��1,000�{�A���]���b�N�X���a��1,000�{���̓t�����T�C�hSC1,000�{���g�p����B�܂��A����H�a�Ǝ���H�a�̕��������ʂł��Ȃ���Q���ł́A�g�b�v�W��M���a��1,000�{�Ƀ_�C�Z���X�e�����X�t��1,000�{���̓��]���b�N�X���a��1,000�{�����p���ď������邩�A�t�����T�C�hSC1,000�{��P�p�ŏ�������B�����ʂ͐��ł�300l�A��ł�100�`300l�Ƃ���B�������A�t�����T�C�hSC�͂킢��������̓}���o�J�C�h�E�ȂǕ��ʑ���̎�ł̎g�p�Ɍ���A���̏����ʂ͍ő�200l�Ƃ���B�e��t�ɂ͔A�f��500�{�ɂȂ�悤�ɉ��p����B
(�H)�@�I�o�������͖�t�ŐB����ɁA�@��グ���y�ɂ���t��ǂ��������킹�Ȃ��畢�y����B
(��)�@���y�̍ہA1�������芮�n�͔�100�`200kg�����邩�A�J�j�K���z���엿5�`10kg�ƃp�[���C�g50�`100l������ƈ�w�L���ł���B
(�L)�@�S�E�ʂ���B���Ƀ_�C�Z���X�e�����X�t�܂͌��ʎ��Ɏg�p�ł��Ȃ��̂ŁA�K���S�E�ʂ���B
�E�@�y�뒍���@�ɂ�鎡��
(�@)�@8�`9���̑�����������ʂ����t�𒆐S�ɉ��ϗ��t�������n�߂���t�F�����W���Ȃ�Ȃǔ��a�����̏Ǐ��悵�Ă���y�ǎ���Ώۂɓ��͕����@���̓X�s�[�h�X�v���[���ɘA�������y����p���āA����̖�܂�y�뒍������B
(�B)�@����H�a�̏ꍇ�́A���]���b�N�X���a��1,000�{���̓t�����T�C�hSC1,000�{�A����H�a�̏ꍇ�́A�t�����T�C�hSC1,000�{���g�p����B�܂��A����H�a�Ɣ���H�a�̕��������͗��҂���ʂł��Ȃ��ꍇ�́A�t�����T�C�hSC1,000�{���g�p����B�Ȃ��A�t�����T�C�hSC�̓}���o�J�C�h�E�ȂǕ��ʑ�̔�Q���ɂ����āA��܂̏����ʂƎ��Ì��ʂƂ̊W�����炩�łȂ��̂ŁA���ʑ���ɂ͎g�p���Ȃ��B
(�D)�@���]���b�N�X���a��
���������F�t����H�܂Ő����A���������ʎ��͎��n60���O�܂ŁB
�������@�F�������甼�a0.6�`2m�A�[��30cm�܂ŁA1�u�������40l�̖�t��y�뒍������B�����ʂ́A�킢������ł�50�`150JB�A���ʑ���ł�200�`500l�Ƃ���B
(�F)�@�t�����T�C�hSC
���������F�t����H�܂Ő����A���������ʎ��͎��n45���O�܂ŁB
�������@�F�킢������̔�Q����ΏۂɎ������甼�a1m�A�[��30cm�܂ŁA20�`30cm�Ԋu��30�`40�����A1����2�`3l�A1��������100l�̖�t��y�뒍������B
�G�@���Î��̊Ǘ�
(�@)�@���Ì�͂ł��邾��1�N�Ԓ��ʂ������A���̌����������܂Œ��ʗʂ𐧌�����B
(�B)�@�͂��イ��̎{�p��A�f�̗t�ʎU�z�Ȃǂɂ��A�����ɓw�߂�B
(�D)�@��ؖ��͕c����ڂ�����B
(�F)�@�͔�}���`�A�~���A�Ċ��̂��Ȃǂɂ�艀�n�̊����h�~�ɓw�߂�B
(�H)�@���N�A���Î��̍������y���x�グ�ėǂ��ώ@���A�ێ����̔ɐB���F�߂���ꍇ�͍Ăю��Â���B |
|
5)�@��t�a
�ߔN�A�{�a�͖����I�ɔ����������B
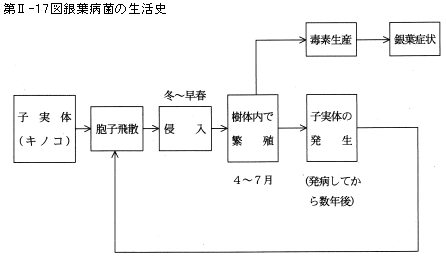
(1)�@���Ԃ̊T�v
�A�@�L�m�R(�����T�L�E���R�[�P)�͏Ǐ�̐i���ɁA�قΔN�Ԃ�ʂ��Ĕ������邪�A�����̍Ő�����10�����傩��12����{����ł���B
�C�@�L�m�R����̖E�q��U���N�Ԃ�ʂ��čs���邪�A�~�J��Z��ȂǂŃL�m�R���G��Ă���ꍇ�ɓ��ɑ����Ȃ�B
�E�@��U�����E�q�͐V�N�Ȑ،�(�}�̐،��A�}�̗��A���荭�Ȃ�)����N���A��������B�����̊댯���͓~�����瑁�t�ɍł������A���莞���ƈ�v����B
�G�@�a���ۂ͖؎����ŔɐB���ēőf���o���A�őf���t�ɓ��B����Ƌ�t�Ǐ����B
(2)�@�ώ@�̗v�_
�A�@�t���݂����F��悵�A�Ǐi�ނƗt�̕\�ʂɍׂ����T����ėt���ϐF���A�����ɗ��t����B
�C�@�ʎ��͏��ʂɂȂ�A���F�����A������ʂ������Ȃ�B
�E�@�d�ǎ��̎劲���}�Ƀ����T�L�E���R�^�P�ƌĂ�邤�낱��`������̃L�m�R��������B
�G�@����V�ɔ����������B
(3)�@�h���̗v�_
�A�@�`������o�ł��邽�߃����T�L�E���R�^�P�̐������d�ǎ��͔��̂���B���̏ꍇ�A���̂������͂������؊�����������B
�C�@�����̐،��╗��Q�̗��ɂ͂ł��邾�����̓��̂����Ƀo�b�`���[�g�h�z�܂J�ɓh��B
�E�@���a�̏����ɂ͎������������邱�Ƃɂ�莩�R�Ɏ���ꍇ���������Ƃ�����̋����������a���ɂ������Ƃ���A��|�Ǘ��A�͔|�Ǘ��ɒ��ӂ��Ď��������ɓw�߂�B
�G�@���݁A�_��ɂ��{�a�̎��Ö@�͂Ȃ��̂ŁA�a���ۂ̓`�d�h�~�A�N�������h�~�y�ю��������ȂǑ����I�ȗ\�h���n�悮��݂œO�ꂷ��悤�S������B |
|
6)�@���j���A�a
�N�ɂ���đ唭�����邱�Ƃ�����̂Ŏ蔲���h���͂ł��Ȃ��B��o�������Ɖ�o��10����̏����h����O�ꂵ�A�t����h�~�ɓw�߂邱�Ƃ��d�v�ł���B
(1)�@���Ԃ̊T�v
�A�@���t�ɋۊj����L�m�R���������A���̏�ɂ͎q�̂��E�q�������`�������B�q�̂��E�q�͔�U���Ēŗt�ɐN�����A�t����������N�����B�t���ꂪ�i�s����Ɖԕ���ɂȂ�B
�C�@�t�����ԕ���̏�ɕ����E�q���`������A�J�Ԓ��ɒ����ɔ�U�A�N�����Ď�����������N�����B�����ꂪ�i�ނƊ�����ɂȂ�B
�E�@������A�����ꂪ�n��ɗ������ċۊj�ɂȂ�A�z�~���ė��N�̓`�����ɂȂ�B
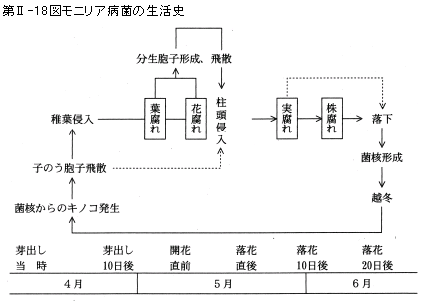 |
|
7)�@���ǂa
�ŋ߁A���������Ȃ��o�߂��Ă��邪��U�z���ȗ�����Α�������̂Œ��ӂ���B
(1)�@���Ԃ̊T�v
�A�@�a���ۂ���̒��ʼnz�~���A���������J�Ԋ��ɂ����ĉԂ����E���ɔ�������̖E�q�𑽐��`������B
�C�@�E�q����U���ėt�ɐN�����A�a���������B���̐N���A���a�͌J��Ԃ��s����B
�E�@�a���ۂ�7�����납���̒��ɓ����ĉz�~���A���N�̓`�����ɂȂ�B
(2)�@�ώ@�̗v�_
�A�@�z�~��
�a���ۂ̐N��������̓{�P��ɂȂ�B
�C�@��1������
����ォ�痎�Ԓ���ɉԂ����E�t�����S�̂����������ӂ��Ċ�`������B
�E�@��2������
��Ƃ��ĐV���t�̗��ʂɕs���`�ŕ���̕a����������B����ɂȂ�ƕa���͒E�F����W���Ȃ�����ÐԐF�ɂȂ�B
(3)�@�h���̗v�_
�A�@��ܖh��
���ǂa�̖h���͎��̖h���̌n�ōs���B
�J�Ԓ��O EBI�P��
���Ԓ��� EBI������
����15���㍠ EBI������
(EBI�����܂̎�ނɂ��Ắu�����a�v�̍����Q��)
�C�@�O�N�x�̔�Q�}�̙���
����̍ہA��Q�}�����ĉz�~���̖��x�̒ቺ��}��B
�E�@��Q�Ԃ����E�t�����̓E�ݎ��
�z�~�����肩��o���Ԃ����E�t�����ɖE�q���`������A��U���ē`�����ɂȂ�̂Ō�����đ��߂ɓE�ݎ��B |
|
8)�@�Ԑ��a
�ŋ߁A���������Ȃ��o�߂��Ă��邪�A�r���N�V���ނ̍͐A����Ă��鏊�̋߂��̉��Ŕ����������Ă���̂Œ��ӂ���B
(1)�@���Ԃ̊T�v
�A�@�a���ۂ͂�����ł͐����S�����邱�Ƃ��ł����A�K�����Ԋ��Ƃ��ăr���N�V���ނ�K�v�Ƃ���B
�C�@�{�a���ۂ͂�Ŗ�6�����A���Ԋ��(�r���N�V����)��2�`3�N��������B
�E�@��ł̐���
(�@)�@���Ԋ���̓~�E�q�����肵�A�����������q����U���Ă�ɕt���A�N������B��U��4�����傩��6�����{�ɋy�Ԃ��Ő�����5����{����6�����{�ł���B
(�B)�@�ŏ��̕a����5�����`���{�ɉ��F�̏����_�Ƃ��Č����B
(�D)�@7�����傱�납��t�̕a���̗��ʋy�щʎ��̕a�����ɊD���F�����q�тƌĂ��я�����Ɍ`�������B���ꂪ���іE�q����ł���B
(�F)�@���q�т��炳�іE�q����U���ăr���N�V���ނ̎Ⴂ���}�̊�ɕt�����A�z�~����B���іE�q�̔�U��8������9�����ł�����ł��邪�ꕔ��10�����{�܂ő����B
�G�@���Ԋ��(�r���N�V����)�ł̐���
�����r���N�V���ނɔ�U�����Ԑ��a�ۂ͖�10�����̐���������o�ė��N�̉ĂɃr���N�V���ނ̎}��ɏ����ȃR�u(�ۂ���)���`������B���̋ۂ����͔����債�A1�`2�N��(�����r���N�V���ނɔ�U����2�`3�N��)�̏t�ɐ��n���ē~�E�q�͂��`������B
(2)�@�ώ@�̗v�_
�A�@���
��ɗt�ɔ������邪�A�܂�ɗc�ʂ�Ⴂ�V���ɂ���������B5�����`���{�ɗt�̕\�Ɍa1mm�ʂ̉��F���_������A����Ɋg�債��0.5�`1cm�ʂ̕a���ɂȂ�B�a���ɂ͑����̕��q����`�����A�S�t���o���Č����тт�B7�����{�ȍ~�ɗt�̕a���̗��ɊD���F�����q�т��`������B�ʎ��̕a���͂��������ɐ����邱�Ƃ������A�ʎ��̐���ƂƂ��Ɋg�債�ėt�̕a�������傫���Ȃ�B�a�����ɂ͗t�̕a���Ɠ��l�ɏe�q�т��`������B
�C�@���Ԋ��
(�@)�@��ށE�E�E�J�C�Y�J�C�u�L�A�^�`�r���N�V���A�n�C�r���N�V��(�\�i��)�A�q���\�i���A�P���p�N�A�~���}�r���N�V���A�n�}�n�C�r���N�V���ȂǁB
(�B)�@�Ǐ�
���іE�q���H�ɎႢ�}��t�̏�ʼnz�~���A���t�ɔ���N�����ĉĂɎ}��ɏ����ȋۂ������`������B�ۂ����͔����債�ė��N���͗��X�N�̏t�ɓ~�E�q�͂��`�����A���ꂪ�~�J�ɂ����Ɗ��V����ɂȂ�B
(3)�h���̗v�_
�A�@���
�Ԑ��a�̖h���͎��̖h���̌n�ōs���B
�J�Ԓ��O EBI�P��
���Ԓ��� EBI������
����15���㍠ EBI������
(EBI�����܂̎�ނɂ��Ắu�����a�v�̍����Q��)
�����̑������ł́A����30���㍠�̊��܂Ƀo�C���g�����a��(5)1,000�{�����p����B
�C�@���Ԋ��(�r���N�V����)
(�@)�@�a���ۂ͒��Ԋ�傪�Ȃ���ΐ����ł��Ȃ��̂ŁA�����A�뉀�y�ъX�H�Ȃǂł����Ă��A�r���N�V���ނ͂ł��邾���A���Ȃ��悤�ɂ���ƂƂ��ɁA���ݐA�����Ă�����̂��\�Ȍ��蔰�̂��邩�A���̑��̎���ɐA���ւ���B���ɂ�͔|�҂͎��q�̂��ߐ�ΐA���Ȃ��悤�ɂ���B�Ή����̎�舵���Ǝ҂��ł��邾���r���N�V���ނ��ړ����Ȃ��悤�ɂ���B
(�B)�@�r���N�V���ނ̔��̂�ۂ����̓E�ݎ�肪�ł��Ȃ��ꍇ�́A�r���N�V���ނ�4�����{�`5����{�Ƀo�V�^�b�N���a��1,000�{��1�T�ԊԊu��2�J�ɎU�z����B |
|
9)�@���_�a
���a63�N�Ɋe�n�Ŕ����������A���̌�͂قƂ�ǔ������݂��Ă��Ȃ������B�������A����8�N�Ɍ���n���ő������Ă���A���ӂ�v����B
(1)�@���Ԃ̊T�v
�A�@�z�~������Q�t�Ɏq�̂��E�q���`�������U����B
�C�@�q�̂��E�q�͗��Ԓ��ォ��7�����{����܂Ŕ�U���A�c�ʂ�t�ɐN������B
�E�@�����̍Ő����͗���10���ォ�痎��30���ケ��܂łł���B
�G�@���m�Ȃ��y�ѓ��{�Ȃ������a����B���������Q���t�ɁA�z�~��A�q�̂��E�q���`������`�����ƂȂ�B
�I�@������̕i������a���邪�A����A�g�ʁA�W���i�S�[���h�A�����Ȃǂ����a���₷���B
(2)�@�ώ@�̗v�_
�ʎ��a����7�����߂��납��A��Ƃ��ĉʎ��̂��������𒆐S�ɗΐF�̏����_�Ƃ��Č���A���̌���g�債��2�`3mm�̔Z�`���F�̔��_�ɂȂ�B�ԓ����̌����ɐ������a���͑�^��5�`6mm�ɒB����ꍇ������B
(3)�@�h���̗v�_
�{�a�̖h���K���͗���10���㍠���痎��30���㍠�ł���B���̕a�Q�̓����h�����˂���ė��Ԓ���A����15���㍠�ɂ�EBI�����܂��A����30���㍠�ɂ͗L�@�����a��(80)1,200�{�A�W�����E�`�E������500�{�A�A���g���R�[���������a��500�{�A�v���E���a��1,000�{�A���j�b�N�XZ���a��500�{�̂����ꂩ���U�z����B�������A���_�a�̑��������O�����n��ł͗��Ԓ��ォ�痎��30���㍠�܂ł̊��Ԃ�10���Ԋu�Ŗh������B���̏ꍇ�A����10���㍠�Ɨ���20���㍠�ɂ̓W�����E�`�E������500�{���̓W�}�_�C�Z�����a��600�{�ɂ��ǂa�h����(�g�b�v�W��M���a��1,500�{���͂׃����[�g���a��3,000�{)�����p���ĎU�z����B�Ȃ��A�W�}���_�C�Z�����a�܂̓A���J�����̂��̂Ƃ͐���p���Ȃ��B |
|