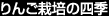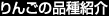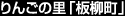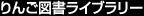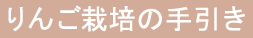|
| 5.主要害虫の防除 |
|
| ミダレカクモンハマキの発生は山手や河川近くの園地に限定されているが、発生地域では慢性的に多発している。ハダニ類は全体的にはナミハダニが優占しているが、平成12〜13年はリンゴハダニが各地で多発した。クワコナカイガラムシは最近増加傾向にある。リンゴコカクモンハマキ、キンモンホソガなどの発生は少ない。平成12年はモモシンクイガの発生が各地でみられた。平成11〜13年は、ヨモギエダシャクが津軽地域で多発した。平成13年はカメムシ類による果実被害が各地で見られた。 |
|
1) ハマキムシ類
(1) ミダレ力クモンハマキ
ア 生態の概要と発生観察の要点
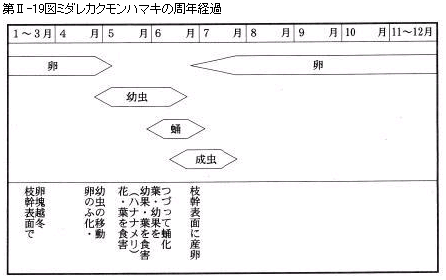
(ァ) 越冬
卵で越冬する。越冬卵は幹や枝の表面に卵塊の状態で産み付けられる。卵塊は越冬前は黒色であるが、越冬後には灰白色となる。
(ィ)幼虫加害
4月下句〜5月上旬ころにふ化する。幼虫は花そう・葉そうと新梢葉を食害し、好んで花をつづって加害する(ハナナメリ)。また、落花期以降、大きくなった幼虫が幼果を食害する。寄主範囲が広く、りんご以外の各種広葉樹や草本類にも発生する。隣接した山林やコバハンノキ、マツダナヤナギ、イタリアンポプラなどの防風林に発生し、若齢幼虫が風でりんご園に運ばれる場合がある。
イ 防除の要点
(ァ) 越冬卵の早期処分
剪定時などに卵塊を見つけたらつぶす。剪去枝に越冬卵が残り、発生源となる場合があるので、幼虫のふ化が始まる4月上旬までに処分する。
(ィ) 開花期前後の防除
発生が多い園地では、開花直前と落花直後の2回アタプロンSC、カスケード乳剤、ロムダンフロアブル、ファイブスター顆粒水和剤のいずれかを選択し、同一薬剤を連続して散布する。前三剤は昆虫成長制御剤(IGR剤)であり、後剤はBT剤(昆虫細菌病を起こす天敵細菌の一種、Bacillus thuringiensisの製剤)である。いずれもマメコバチに対する影響が少ないので、マメコバチが活動している場合でも散布できる。IGR剤及びBT剤は遅効的であるため、効果の発現までにある程度の期間が必要である。また、摂食量が十分でないと死亡しないため、1回の散布や散布量が不足した場合は効果が期待できない。
(ゥ)落花10日後頃の特別散布
落花10日後頃に発生が多い場合は直ちにダーズバン水和剤、トクチオン水和剤、エルサン水和剤のいずれかを特別散布する。この場合、落花15日後頃のクワコナカイガラムシ防除剤は省略できる。
(ェ)交信撹乱法による密度低減
性フェロモンを園地内に充満させることで成虫の交尾を阻害し、次世代の発生密度を低下させることができる。ミダレカクモンハマキに対しては交信撹乱剤「ハマキコン」が有効である。成虫期の対策であるため、当年の被害は回避できないが、次年度の発生密度の低下が期待できる。殺虫剤のような即効的な効果はないが、連年使用することで低密度の状態を維持することも可能となる。薬剤だけで防除しきれない園地及び本種の発生がみられる園地では、地域ぐるみで積極的に利用する。
豗 使用方法
ハマキコンは成虫の発生期前の5月下旬〜6月上旬に取り付ける。枝などにひとひねりして固定するが、食い込みを避けるために枝との間に余裕を持たせる。10a当たり100〜150本を目通りの高さに7割、残りを樹の上部に取り付ける。全園に均一に取り付けるようにするが、園周辺部はやや多めにする。成分は空気より若干重いので、傾斜がある場合は傾斜の上部を多めにする。また、周囲に雑木林がある場合は林地内にも設置する。約3か月有効である。使用後は剪定時などに回収し、処分する。
豩 利用上の注意
広い面積で処理するほど効果が高く、正方形に近い場合でも1ha以上が望ましい。急傾斜地やミダレカクモンハマキの密度が極端に高い場合は使用しない。また、隣接園地の密度が高い場合、交尾した成虫の飛び込みがあるので使用しない。
豭 価格及び取付け時間
10a当たり取付け量 参考価格(税抜き)
100本 1,550円
150本 2,325円
1人1時間で約10aの処理が可能である。
(2) リンゴコカクモンハマキ
ア生態の概要と発生観察の要点
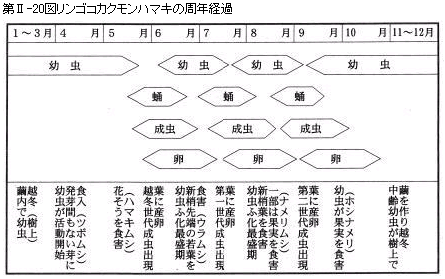
(ァ) 越冬
幼虫が枝の分岐部や切口、樹皮の割れ目やしわの部分などに薄い繭を作り、その中で越冬する。
(ィ) 幼虫加害
豗 春期
幼虫は発芽期〜展葉期(4月上旬〜中旬)に越冬場所から移動し、発芽した芽に食入する(ツボムシ)。
豩 夏期
7月上句〜中旬は徒長枝や上枝の新梢の先端部に集中して加害する。8月上旬〜中旬も同様であるが、若い新梢がないときは葉裏の葉脈に沿って糸を張り食害し、大きくなると葉を重ねてつづり、内部から葉脈を残して透かし状に食害する。葉が果実と接触している場合は隙間に潜り込み、また、有袋の場合は袋内に入り果皮を加害する。若齢幼虫は太い針で突いたような食痕を残し(ホシナメリ)、大きくなるとなめるように食害する(ナメリムシ)。
(ゥ) フェロモントラップによる発生調査
フェロモントラップを利用して成虫の発生時期を知ることができ、防除適期を予測できる。
豗 調査方法
トラップは園内中央部の高さ1.5m位の枝につるす。5月下旬から9月下句まで毎日の誘引成虫数を調査し、成虫は調査の都度取り除く。フェロモン剤は世代ごと(越冬世代:5月下旬〜6月下句、第1世代:7月上旬〜8月上旬、第2世代:8月中旬〜9月下旬)に交換し、粘着板は粘着力が低下したら適宜(通常10〜30日位)交換する。なお、古いフェロモン剤及び粘着板は必ず回収し、園内に放置しない。
豩 防除適期の予測
毎日の調査虫数は前日(前夜)のものとして扱う。明らかな誘引消長の山が認められる場合は、最も誘引数の多い日を成虫最盛期とみなす。誘引消長の変動が大きい場合は連続した3日間の合計誘引数が最も多い期間の中央日を成虫最盛期とする。成虫最盛期から2〜3日後(産卵前期間)が産卵最盛期となる。各時期における卵期間はおよそ表のとおりである。ふ化最盛期は卵期間と産卵前期間を合計することで推定できる。越冬世代成虫最盛期から第1世代幼虫のふ化最盛期までの期間(6月)は約15日であるが、気温が高い年には約12日、低い年には約17日となる。第1世代成虫の場合は平年で約10〜11日となる。防除適期は幼虫ふ化最盛期からその数日後までである。
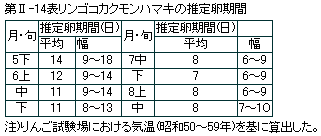
豭 利用上の注意
世代が進むにつれて誘引期間が長引き、発生が不揃いになる傾向があり、明らかな最盛期を捉えることが難しい場合もあるので、トラップの誘引消長だけに頼りすぎないよう注意する。調査の記録は保存し、次年以降の参考とする。
イ 防除の要点
同一薬剤の連用を避け、適期に十分量散布する。発生密度の高い場合は薬剤散布だけでなく、他の抑制対策も実施する。
(ァ) 剪去枝の早期処分
剪去枝には越冬幼虫が残っており、これを園地に残しておくと発生源になるので幼虫の活動が始まる4月上旬までに処分する。
(ィ) 薬剤による防除
越冬世代幼虫:ふじの芽出し10日後にトクチオン水和剤又はダーズバン水和剤を散布する。この時期のピレスロイド剤散布は訪花昆虫への影響が懸念されるので絶対に使用しない。第1世代及び第2世代幼虫:一般には防除適期は落花30日後頃及び8月上句頃にあるので、この時期に枝先に薬液が十分付着するようにダーズバン水和剤又はピレスロイド剤を散布する。しかし、地域や生によっては防除適期が異なる場合があるので、発生が多い場合にはフェロモントラップによる成虫の誘引消長を利用して防除時期を決定する。落花30日後頃のピレスロイド剤の散布によりキンモンホソガ、モモシンクイガなども同時に防除できる。さらに、次回のモモシンクイガ防除剤も省略できる。なお、ピレスロイド剤は成虫最盛期からふ化揃い期までの散布でも防除できる。7月下旬頃のキンモンホソガ防除にピレスロイド剤を散布した場合は8月上旬頃の対策は必要ない。
(ゥ) 適正な肥培管理の実施
ふ化直後の幼虫は若い葉に寄生する習性がある。このような若い葉や徒長枝が多いと薬液の付着が悪くなるので発生増加につながりやすい。新梢の伸長が遅くまで続いたり、二次伸長枝が多く出ることがないよう剪定、施肥、その他の管理に当たっては十分配慮する。
(ェ) 不要な発育枝の剪去
主枝、亜主枝上の徒長枝やひこばえには常に新葉が出るので幼虫が多く寄生する。第1世代幼虫のふ化が始まる落花30日後以降、随時剪去して処分する。
(ォ) 果実に覆いかぶさった葉の摘み取り
幼虫は果実と葉の接触部位に潜み、果皮を食害する。幼虫の発生が多い場合はなるべく早めに(8月以降)果実に接触している葉を摘み取って果実被害の軽減に努める。
(3) その他のハマキムシ類
ア 種類の概要と発生観察の要点
(ァ) 種類
一般のりんご園では年1回発生する卵態越冬のカクモンハマキと、年2〜3回発生する幼虫態越冬のリンゴモンハマキ、トビハマキ及びアトボシハマキが発生することがある。通常は特に防除する必要はない。
(ィ) 幼虫の識別方法
カクモンハマキは5〜6月に発生し、新梢中位の1枚の薬を横に筒状に堅くつづる。他にこのような巻き方をする種類はいない。リンゴモンハマキは5〜6月は新梢先端や果そうを粗い糸でつづり、7月以降は主に生育伸長中の新梢や徒長枝を加害する。終齢幼虫の頭部は黒褐色で、体色は暗緑色〜濃緑色。トビハマキは5〜6月は新梢先端を粗い糸でつづったり、新梢中位の1枚の葉を縦に二つ折りに緩くつづり、7月以降は主に生育伸長中の新梢や徒長枝を加害する。終齢幼虫の頭部は淡黄褐色で、体色は淡黄緑色。アトボシハマキは5〜6月は新梢先端や果そう葉を数枚粗い糸で大きくつづる。葉柄を噛み切ることもあり、枯れ葉も混じることがある。7月以降は主に生育伸長白の新梢や徒長枝を加害する。終齢幼虫の頭部は茶褐色で、体色は暗緑色〜淡黄褐色。
イ 防除の要点
(ァ) 薬剤による防除
発生が多い場合は、表のハマキムシ防除剤を散布する。
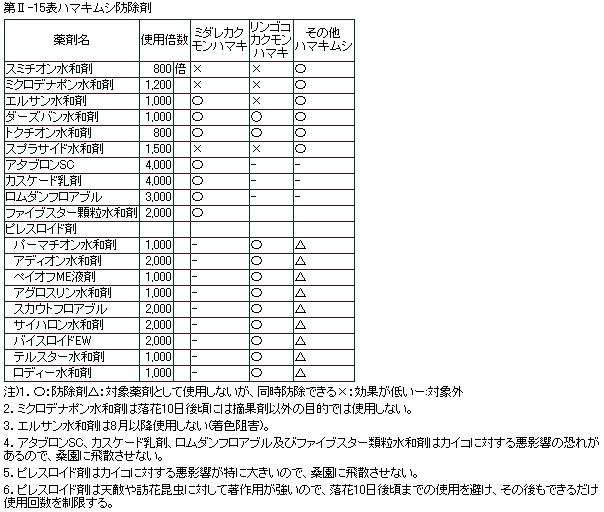 |
|
2) モモシンクイガ
(1) 生態の概要と発生観察の要点
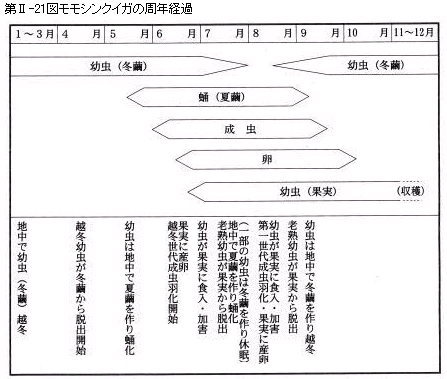
ア 越冬
幼虫が地中で冬繭を作り、その中で越冬する。
イ 成虫発生時期
(ァ)越冬世代
津軽地方:6月上旬〜7月下旬
県南地方:6月中旬〜8月上旬
(ィ)第1世代
津軽地方:7月下旬〜9月上旬
県南地方:8月上句〜9月上旬
ウ 産卵
6月中旬から9月上旬にかけて行われる。卵はケシ粒大で黄〜橙色を呈し、果実のがくあ部に7〜8割、つる元に2〜3割産み付けられる。
エ 被害果
卵からふ化した幼虫は果実表面から食入する。幼虫が食入した部分からは透明な露が出るが、これは乾燥して白くなる。その後、食入部は果実の肥大に伴って小さく陥没し、小黒点となる。肥大初期の果実や幼虫が果実の表面付近を潜行した場合は、果実の肥大に伴って坑道が陥没し、不整形となるので、外観から被害果を判別できる。しかし、幼虫が果心部にまっすぐ潜入した場合には、老熟幼虫が脱出口を開けるまでわからない。被害果は6月下句から収穫期まで見られる。
(2) 防除の要点
ア 環境の整備
放任樹(園)が付近にあったり、ずみ(サナシ)などがあると発生源となるので、これらを根絶する。また、薬剤散布の行われないもも、なし、あんず、まるめろなども発生源となるので、発生に注意する。放任園の結実量が減少した場合や伐採した場合には、成虫が果実を求めて周囲の園地に飛来し、被害が多発することがある。
イ 発生密度の低減
被害果を発見したら、幼虫が脱出する前に採取し、7日間以上水に漬けるか、穴に埋めて10cm以上の土をかぶせる。あるいは大きなナイロン袋に入れ、日当たりの良い場所に1か月くらい放置し、その後処分する。ナイロン袋を利用する場合は袋に穴が開かないように注意し、口を固く結ぶ。被害果をそのまま園地に放置すると次世代の発生源となるので、必ず処分する。発生密度が極めて高い場合は、1年間有袋栽培を行って徹底的な防除をしてから、無袋栽培に移る方がよい。
ウ 薬剤による防除
(ァ) 無袋栽培
落花30日後頃から10日ごとに毎回防除剤を加用して8月下旬まで散布する。前年の発生が多かった園地や、付近に放任樹(園)がある場合には、特に散布間隔があかないようにし、さらに9月上旬の特別散布を行う。ピレスロイド剤を使用した場合には次回のモモシンクイガ防除剤を省略できる。ただし、散布間隔があいた場合には省略できない。また、交信撹乱剤(コンフューザーA又はシンクイコン)を利用していても、周囲にモモシンクイガの多発している放任園がある場合は防除剤を省略できない。
(ィ) 有袋栽培
袋かけ前は無袋栽培に準じて防除する。
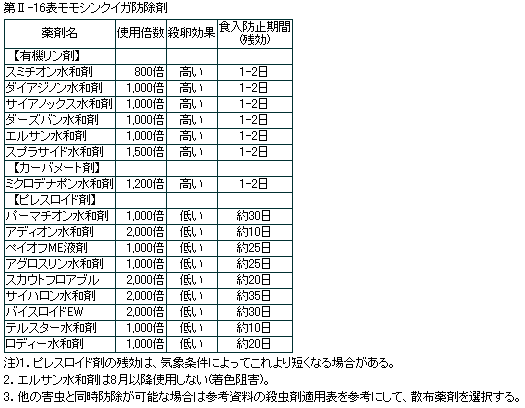 |
|
3) ナシヒメシンクイ
(1) 生態の概要と発生観察の要点
ア 越冬
幼虫が樹の粗皮下、樹皮の割れ目などに薄い繭を作り、その中で越冬する。
イ 成虫発生時期
越冬世代盛期:5月中旬〜6月上旬
第1世代盛期:7月上〜下旬
第2世代盛期:8月中旬〜9月中旬
ウ 産卵
葉や果実表面に1粒ずつ産み付けられる。卵は円盤状で白色透明である。
エ 新梢被害(心折れ)
6月ころ(新梢伸長期)から幼虫が新梢の先端に食入する。食入された新梢先端はしおれて下垂し「心折れ」となる。
オ 果実被害
7月以降、有袋、無袋に関わりなく幼虫が果実に食入し加害する。
(2) 防除の要点
ア 越冬幼虫の処分
粗皮削りした粗皮や除去したバンドは処分する。
イ 「心折れ」枝の処分
心折れは見つけしだい剪去して処分する。
ウ 被害果の処分
幼虫が果実から脱出する前に被害果を採取し、7日間以上水に漬ける。
エ 薬剤による防除
落花15日後頃にクワコナカイガラムシとの同時防除を図る。落花30日後頃以降は有袋、無袋栽培に関わりなく、無袋栽培のモモシンクイガ対策に準ずる。 |
|
4) キンモンホソガ
(1) 生態の概要と発生観察の要点
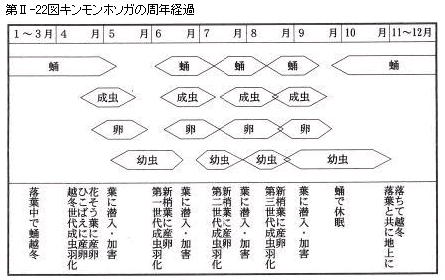
ア 越冬
幼虫の加害した落葉内で、蛹で越冬する。
イ 成虫発生時期
越冬世代:4月中句〜5月中句
第1世代:6月中〜下旬
第2世代:7月中句〜8月上旬
第3世代:8月中句〜9月上旬
ウ 産卵
葉の裏面に白色透明な円盤状の卵を一粒ずつ産み付ける。越冬世代成虫は温暖な日に活動し、早期には特に展葉の早いひこばえに集中的に産卵する傾向がある。その後、花そう・葉そうが展葉するにつれてこれに産卵する(1雌平均産卵数約30個)。第1世代以降は新梢葉を主体に産卵する(1雌平均産卵数約70個)。
エ 幼虫加害
ふ化幼虫は葉肉内に潜入する。若齢幼虫(吸汁型幼虫)による被害痕(虫孔)は葉の裏側に水ぶくれの症状を示す。老熟幼虫(食組織型幼虫)による虫孔は葉の表側に透かし状の斑点を示す。各世代の虫孔数の観察によって、発生程度を判断できる。
オ 蛹化及び羽化
虫孔内で踊化する。越冬蛹から羽化した成虫は樹の地際部〜1m位の所に静止している。この成虫を観察することにより当世代の羽化消長を把握できる。夏世代の成虫が羽化すると、蛹殻が虫孔の裏側表面から突き出た状態で残っている。この螺殻の観察から羽化状況が判るので、防除適期を予測できる。
カ 温度と発育
各発育段階の温度別所要日数は次のとおりである。
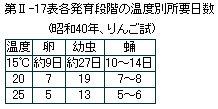
(2) 防除の要点
ア 春期に落葉を集めて処分する。
イ 春期に集中的に産卵されるひこばえは産卵が終了する開花期から落花直後に剪去する。
ウ 薬剤による防除
(ァ) 芽出し10日後
発生の多い場合は硫酸ニコチン液剤、デミリン水和剤、アドマイヤー水和剤、モスビラン水溶剤のいずれかを散布する。
ィ) 落花30日後頃、7月下句頃
防除剤を散布する。防除適期は成虫羽化率7〜8割の頃である。しかし、地域や年によっては防除適期が異なる場合があるので、発生が多い場合は羽化状況を利用して防除時期を決定する。
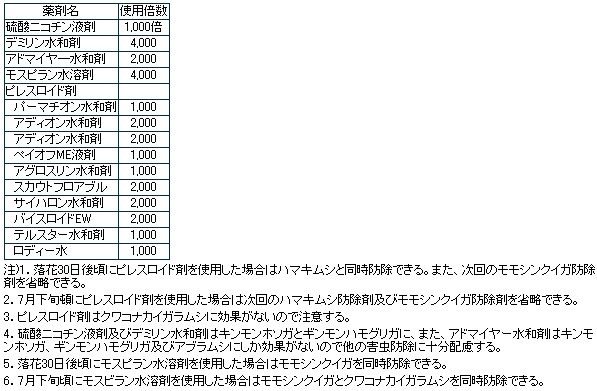 |
|
5) ギンモンハモグリガ
(1) 生態の概要と発生観察の要点
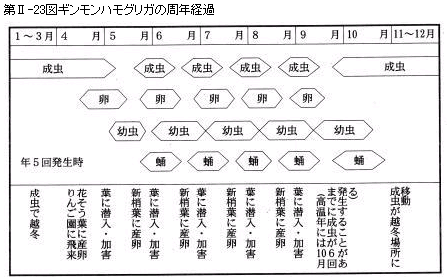
ア 越冬
雌成虫が越冬する。越冬世代成虫の翅は銀白色に黒色の縞模様がある(夏世代成虫は翅全体が銀白色)。越冬場所は垣根、小屋の板壁、樹幹の窪みなど風当りが少なく、雨や雪が入り難い所である。越冬世代成虫は4月上旬(発芽期頃)からりんご樹に飛来し、展葉間もない葉に産卵する。
イ 産卵部位
春期にはすべての葉が産卵対象となる。第2世代以降は生育伸長中の新梢先端部に限定され、生育が停止した葉には産卵しない。
ウ 幼虫加害
幼虫は葉肉内に潜って加害する。ふ化直後の幼虫は線状の虫孔を形成するが、2〜3齢幼虫は斑状の虫孔を形成する。幼虫は3齢で成熟し、葉肉内から脱出する。脱出幼虫は糸を垂れて下位の葉に移り、葉の裏側にハンモック状の白い繭を作り、その中で蛹化する。
エ 成虫発生時期
年によって5〜6回発生し、一定でない。5回発生の場合のおおよその発生時期は次のとおりである。
越冬世代:4月上旬〜5月上旬
第1世代:5月下旬〜6月中旬
第2世代:6月下旬〜7月中旬
第3世代:7月下旬〜8月中旬
第4世代:8月下旬〜9月中旬
第5世代:9月下句〜(越冬)
(2) 防除の要点
ア 耕種的対策
夏場以降、枝の徒長をできるだけ抑制するような栽培管理をし、産卵を抑制する。
イ 薬剤による防除
ァ) 前年秋期に発生が多かった場合は、芽出し10日後に硫酸ニコチン液剤、デミリン水和剤、アドマイヤー水和剤及びモスピラン水溶剤のいずれかを散布する。
(ィ) 幼虫の下垂最盛期から10日〜2週間後に当たる卵期に有効薬剤を散布する。
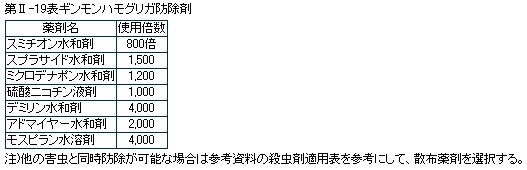 |
|
6) ハダニ類
(1)生態の概要と発生観察の要点
ア リンゴハダニ
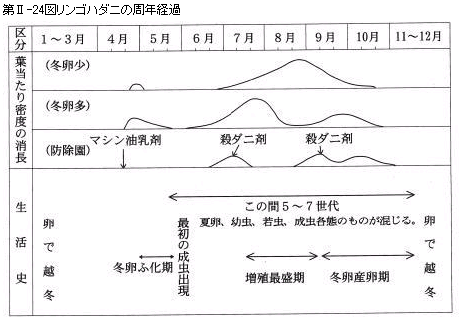
(ァ) 越冬
卵で越冬する。越冬卵は2〜5年枝上の枝の分岐部、芽の基部、樹皮のしわの部分などに産み付けられる。これを観察すると越冬量の多少を判断できる。
(ィ) 越冬世代卵からのふ化
5月上〜中旬にふ化し、幼若虫は最初に花そう・葉そうの基部葉に集中し、発育するにつれて分散する。落花直後頃に果そう基部葉の寄生状況の観察によって春期の発生程度を判断できる。
(ゥ) 発生の仕方と被害状況
5月末ころから最初の成虫が発生し、産卵を始める。その後、世代を繰返しながら増殖し、樹全体に移動・分散する。7月以降、特に梅雨明け後から、本格的な増殖期に入る。春期以外には世代が重複するため、卵、幼虫、若虫、成虫が混在する。本種は葉の裏表に寄生。加害するので、発生が多い場合は葉の表側が白っぽく抜け、裏側が褐変する。
イ ナミハダニ
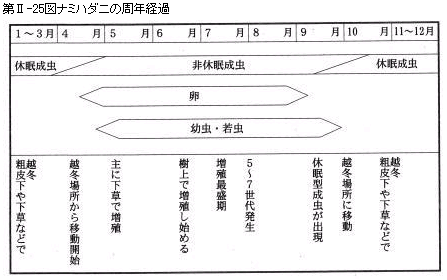
(ァ) 越冬
雌成虫で越冬する。夏世代成虫は乳白色の地色に2個の黒色斑点があるのに対し、越冬世代成虫は橙色で斑点はない。越冬場所は樹幹や大枝の粗皮下、樹皮の割れ目、枯草や落葉の下などであり、バンドを巻いておくとその中に多数潜入する。粗皮やバンドでの越冬世代成虫を観察すると越冬量の多少を判断できる。
(ィ) 越冬世代成虫の活動
4月に入り、気温が上昇すると活動を始め、越冬場所から移動する。
(ゥ) 春期の発生
4月下旬から6月上旬ころまでは幹や主枝など粗皮が多い部位の葉に発生する。春期にはりんご樹上での発生は比較的少ない。
(ェ) 夏期の発生
りんご樹で本格的な増殖が始まるのは7月後半からである。本種は葉裏にだけ寄生。加害するので、発生が多い場合でも、葉の裏側だけが褐変する。
(ォ) 秋期の成虫
9月下旬ころから体色が橙色になった休眠型成虫が出現し、越冬場所へ移動する。果実のこうあ部やがくあ部にも多数集まる。
(2) 防除の要点
ア 粗皮削り
粗皮削りを3月下旬頃までに行い、越冬成虫を除去する。粗皮は処分する。
イ マシン油乳剤の散布
リンゴハダニの越冬卵がある園では必ず行う。
ウ 落花直後の殺ダニ剤散布
マシン油乳剤を散布した場合は通常必要ない。マシン油乳剤の散布の有無にかかわらず、開花期頃にリンゴハダニの発生が目立った園では落花直後に殺ダニ剤を散布する。
エ 徒長枝及びひこばえの剪去
ナミハダニの越冬密度の高い園では、5月下句頃からひこばえや主枝、亜主枝など大枝から発出している徒長枝葉に多く寄生している。落花直後〜落花20日後頃にこれら徒長枝及びひこばえを剪去する。
オ 7月上旬の殺ダニ剤散布
7月中〜下旬にハダニが急増するので、7月上旬に殺ダニ剤を散布する。ただし、この時期に発生がほとんど認められない場合は、その後の発生に応じて7月中句以降に散布する。発生状況の観察はルーペを使い、1園地当たり10樹について行う。リンゴハダニの観察は、目通りの高さの新梢中位葉を1樹当たり10枚について行う。ナミハダニの観察は、樹冠内部の主幹や主枝から直接発出した新梢中位葉を1樹当たり10枚について行う。散布の目安として1葉当たり2個体以上あるいは寄生葉率50%以上の場合には、できるだけ早めに殺ダニ剤を散布する。
カ 殺ダニ剤使用上の留意点
(ァ) 散布回数は必要最小限にとどめる
ハダニ類の発生がほとんど見られないような場合は散布の必要がない。常時発生状況を観察し、発生を確認して散布する。このことは単に経済的な面のみならず、殺ダニ剤の抵抗性回避の上で重要である。
(ィ)全体の葉に十分かかるように配慮する
散布むらがあるとそこが発生源となり、抑制期間が短くなる。殺ダニ剤の効果をよく出すために、樹冠内部や葉の裏表にも十分薬剤がかかるように樹の仕立て方、薬液散布量、散布速度などに配慮する。また、不要な徒長枝は除去して散布薬剤の通りをよくする。
(ゥ) 同一殺ダニ剤の連続使用を避ける
同一薬剤を連続使用すると、その薬剤に対して抵抗性が早く現れ、ハダニ防除が難しくなる。同一薬剤の連続使用を避け、年1回の散布とする。
(ェ) 殺ダニ剤の特徴を知る
ハダニの種類や発育状態によって殺ダニ剤の効果に違いがあるので誤りのないように使用する。ただし、薬剤によっては急速に効果が低下する場合があるので注意する。
(ォ)効果の判定
散布3〜5日後に寄生葉を観察し、成虫、若虫及び幼虫の生存個体がいない場合は効果があったとみなせる。ただし、バロックフロアブルは成虫に効果がなく、若虫や幼虫も脱皮時に死亡するので、散布7〜10日後に若虫と幼虫の生存個体がいない場合は効果があったとみなせる。一方、生存個体が多い場合は効果が低かったか、散布むらである。なお、気温が低い場合には効果の発現に時間がかかるので、判定はこれよりも数日遅らせる。
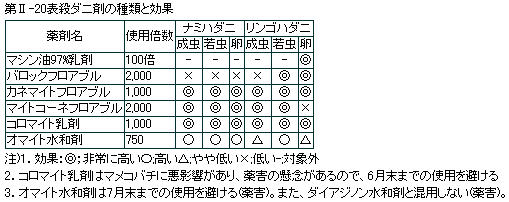 |
|
7)クワコナ力イガラムシ
(1) 生態の概要と発生観察の要点
ア 越冬
卵で越冬する。卵は200〜300個が白い綿状物質に包まれた卵のうとして幹や大枝の粗皮下、樹皮の割れ目、空洞部などに産み付けられる。バンドを巻いておくとその中にも産卵する。粗皮やバンド内の卵のう数を観察すると越冬量の多少を判断できる。
イ 越冬世代卵からのふ化
5月中旬から6月上旬にかけてふ化し、幼虫は樹上を移動して徒長枝基部、果そう基部、枝の切口などに定着する。
ウ 越冬世代成虫
6月下句から7月上旬に成虫となり、大枝の切口や徒長枝基部などに集まる。また、産卵場所へ移動する成虫が主枝や亜主枝で見られる。これらを観察することにより発生量の多少を判断できる。
エ 第1世代卵(夏卵)産卵
7月上旬から幹や主枝の粗皮下などに産卵し、7月中旬が最盛期となる。卵は7〜10日位でふ化する。
オ 第1世代幼虫の袋内侵入
幼虫が袋の中に侵入し、果実に寄生する。その際、虫の排泄物により袋が黒くすす状に汚染される。袋の汚染は8月下旬ころから多くなる。一重袋の場合は外側から判別できるが、二重袋、三重袋では判別できないので、袋をはいで点検する。
カ 第1世代成虫
8月中旬から10月下旬ころまで出現し、第2世代卵(越冬卵)を産む。
(2) 防除の要点
ア 越冬世代卵の殺卵
粗皮削りをしながら越冬世代卵をすりつぶす。削り落とした粗皮は処分する。また、前年に2回目の誘引用バンドを巻いたものについてはバンドを除去し、処分する。
イ ふ化幼虫の殺虫
落花15日後頃に防除剤を散布する。ただし、落花10日後頓にミダレカクモンハマキを対象として特別散布した場合は省略できる。発生が多い場合は落花10日後頃、落花20日後頃、7月下旬及び8月上旬に防除剤による胴木洗いを手散布で実施する。
ウ 成虫をつぶす
6月下旬から7月中旬まで成虫が大枝の切口や木の空洞部周辺に集まるのでブラシなどでつぶす。
エ 空洞部の充填
クワコナカイガラムシの隠れ場所となる枝幹部の空洞をモルタルなどで充填する。
オ バンド巻きによる誘殺
(ァ)実施方法
亜主枝など大枝に幅10cm程度のバンドを一周程度にきっちりと巻いて、成虫の潜伏、産卵場所を与える。その後、バンドを除去し、集めて焼却する。その際、樹体に残った卵のうはブラシなどですりつぶす。バンド巻きをしてもそのまま放置したり、取り外す時期を失するとむしろ増やす結果になるので必ず取る。バンド巻きには段ボール紙が便利で、バンドの横側(縦の長い面)に波形に見えるように切断すると、成虫が潜伏して産卵する場所が多くなる。(図参照)
(ィ) 実施時期
1回目は越冬世代成虫の産卵前(6月下句)に巻き付け、第1世代卵のふ化前(7月中句)に除去する。2回目は第1世代成虫の産卵前(8月中旬)に巻き付け、第2世代卵(越冬卵)のふ化前(ふじの収穫後〜翌年の5月上旬までの間)に除去する。1回目のバンド除去時に2回目のバンドを巻いてもよい。
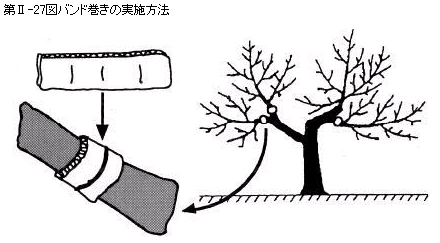
カ 早期除袋
被害が多く、袋の汚染が多い場合は、8月下旬以降早めに除袋し、被害の軽減を図る。
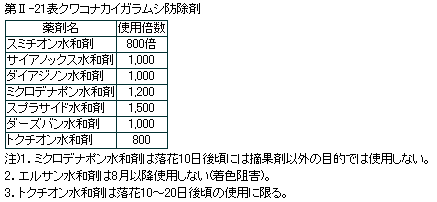 |
|
8) アプラムシ類
(1) 種類の概要と発生観察の要点
ア 種類
春期に花そう基部などに寄生し、葉を大きく巻き込むような縮葉を引き起こすのはリンゴクビレアブラムシである。6月以降、新梢先端に寄生する主要なアブラムシはユキヤナギアブラムシとリンゴミドリアブラムシである。多くの場合、ユキヤナギアブラムシが優占するが、時にリンゴミドリアブラムシが混在する。
イ 生態
リンゴクビレアブラムシはりんご樹上の芽の基部などで卵越冬し、展葉期ころにふ化する。密度が高いと開花期ころに花そう基部に密集し、5月中旬ころから葉を大きく巻き込むような縮葉を引き起こす。このころから翅のある個体が出現し、次々と夏寄主(草本類)に移るため、6月以降にはりんご樹上からいなくなる。秋期に再びりんご樹に飛来し、越冬卵を産み付ける。ユキヤナギアブラムシは6月以降にりんご園外から飛来する個体が発生源となる。伸長中の新梢にのみ寄生するため、伸長が停止する夏期には発生が少なくなる。
ウ ユキヤナギアプラムシとリンゴミドリアブラムシの識別
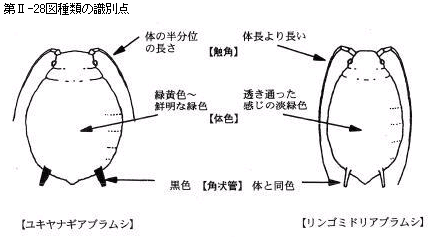
(2) 防除の要点
ア リンゴクビレアブラムシの防除
高密度にならなければ実害はない。また、6月以降にはりんご樹上での発生が見られなくなるので落花期以降の防除は必要ない。
イ ユキヤナギアブラムシ及びリンゴミドリアブラムシの防除
高密度にならなければ実害はない。枝の徒長をできるだけ抑制するような栽培管理をする。薬剤による防除は他害虫との同時防除が基本であるが、多発した場合は種類を確認し、有効な薬剤を選択する。アドマイヤー水和剤2,000倍及びモスピラン水溶剤4,000倍は両極に有効で残効も長い。 |
|
9) シャクトリムシ類
(1) 生態の概要と発生観察の要点
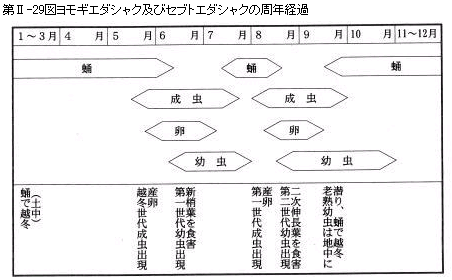
ア 越冬
浅い土中で蛹で越冬する。
イ 産卵
卵は緑色で樹幹の間隙、しわ、浮き上がった粗皮下などに数百〜数十個まとめて産み付けられる。
ウ 幼虫
ふ化した幼虫は樹上を移動し、あるいは糸を吐いて風に乗って分散し、初期にはやわらかい葉の表面をかじるように食害し、小穴をあける。大きくなると葉のふちから食害するようになる。
エ 種類
主要な種類はヨモギエダシャクとセブトエダシャクである。区別点は図のとおりである。両種とも通常薬剤散布されていないりんご以外の樹木、草本で発生している。シャクトリムシと同時期に発生し、混同されているものにヨトウムシがある。ヨトウムシの若齢幼虫は緑色で、シャクトリムシのような歩行をするため紛らわしいが、卵は黄白色(ふ化直前に紫色)で葉裏や果実・袋の表面に数十個まとめて産み付けられること、ふ化した幼虫は葉の裏側から葉脈を残して網目状に食害し、1〜2葉を食しただけでりんご葉から離れていくことから区別でき、防除の必要はない。
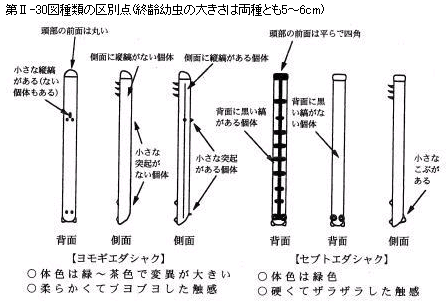
(2) 防除の要点
ア 耕種的対策
若齢幼虫はやわらかい葉がないと寄生できないので、不要な発育枝は随時剪去し、新梢の伸長が遅くまで続いたり、二次伸長枝が多く出るような肥培管理は避ける。
イ 薬剤による防除
第1世代幼虫:6月下句〜7月上旬
第2世代幼虫:8月中旬〜9月上旬
シャクトリムシ類に登録のある有効薬剤はないので、他害虫との同時防除が基本である。幼虫が大きくなると効果が低下するので、若齢のうちに防除する。第2世代幼虫の防除に当たっては適正使用基準(年間使用回数、収穫前日数)に特に注意する。葉があるうちは葉だけを食害し、果実を食害することはない。
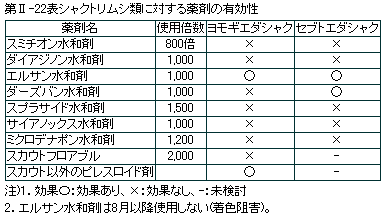 |
|
10) クロフタモンマダラメイガ
(1) 生態の概要と発生観察の要点
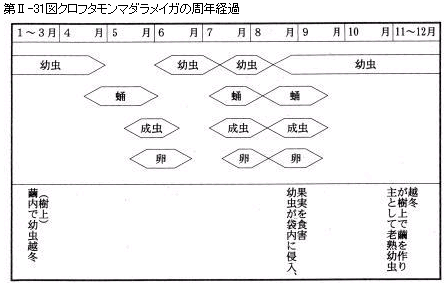
ア 越冬
幼虫が粗皮下、樹皮の割れ目の内側、胴腐らん病斑の下などに薄い繭を作り、その中で越冬する。
イ 産卵
粗皮や気根束などの荒れた部分に産み付けられる(推定)。
ウ 幼虫
幼虫は樹幹部の粗皮下や割れ目の内側に潜み、粗皮と皮部の間や気根束の表面を縦横に食べる。また、子座形成後の胴腐らん病斑下にも好んで生息し、健全部と腐敗部の境目から外側に虫糞を出しているので外観から容易に生息場所がわかる。粗皮下や割れ目の内側で蛹化する。
エ 果実被害
秋期に幼虫が有袋果の袋内に侵入し、ハマキムシの食害(ナメリ果)に類似した被害を出す。果実被害は有袋に限られ、わい性台樹や若木では少ない。粗皮や空洞部の多い老木などでは一般的に被害が見られる。除袋時の被害果には食害部に幼虫が潜んでいることが多い。リンゴコカクモンハマキの幼虫に類似するが、体色が淡褐色(リンゴコカクモンハマキは緑色)で、体毛がより長いこと、虫糞を糸で綴り、吐糸量が多いことで区別できる。
(2) 防除の要点
薬剤による防除法は確立されていない。
ア 粗皮削り
主要越冬場所である粗皮や樹幹にできた亀裂部分のめくれ上がった皮部を削ることによって、中に潜む幼虫を殺すとともに生息場所を少なくすることができる。また気根束の表面を削ったり、胴腐らんの治療を行い、夏期の生息場所を少なくする。
イ 無袋栽培の実施
発生密度の高い場合、無袋にして果実被害を少なくする。 |
|
11) 力メムシ類
平成12年は県内各地で9月下旬以降、クサギカメムシを主体とした果樹カメムシ類の越冬成虫が山間部で特に多く見られた。そのため、翌13年は越冬成虫が多かった園地で開花期〜幼果期の被害が目立った。また、県南地方ではチャバネアオカメムシの新成虫による被害も発生した。
(1)生態の概要と発生観察の要点
ア 越冬
クサギカメムシは山間部の小屋や家屋内などで、チャバネアオカメムシは広葉樹の落葉の下で越冬する。
イ 成虫の加害時期
加害は主に越冬成虫による開花期〜幼果期(5〜6月、まれに7月)と、新成虫による8月〜9月に起こり、無袋果を吸汁加害する。幼果期にはクサギカメムシでは産卵も認められるが、栽培種の果実では、幼虫は発育できずに途中で死亡する。クサギカメムシ、チャバネアオカメムシともに果樹以外で増殖し、餌が不足すると果樹への飛来が多くなる。そのため、果樹に飛来が起こるかどうかを予測するのは困難である。
ウ 被害果
幼果期の被害は、成虫が吸汁した部位からモモシンクイガ幼虫の食入痕のような小滴が見られ、その後、果実の肥大に伴って吸汁部位がえくばのようにくぼんだ奇形果となる。7月の被害は、吸汁部位がボルドー液の薬害や斑点落葉病のような濃緑色〜黒褐色の小斑点となる。その後、果実の肥大に伴って吸汁部位が浅くくぼんで凹凸になる。8月〜9月の被害は吸汁部位を中心に5mmくらいの大きさで褐色にくぼみ、ビターピットやコルクスポットの生理障害に類似している。いずれの被害も果実を切断すると、被害の中心に表面から内部に向かって針で刺したような痕が見られる。また、収穫時期が近づいた果実では吸汁部位が弱くくぼみ、表皮から数mm離れた部位がスポンジ化する。
(2) 防除の要点
ア 越冬成虫の捕殺
越冬成虫が活動を開始する前に、越冬場所(作業小屋や落葉の下などに潜伏している成虫を捕まえて処分する。
イ 薬剤による防除
越冬成虫が落花期以降目立つ園地では、幼果期(落花10日後頃〜落花30日後頃、年によっては7月上旬も)に他害虫と同時防除できる殺虫剤を使用する。クワコナカイガラムシ防除剤、モモシンクイガ防除剤、アブラムシ防除剤はいずれも有効である。ピレスロイド剤は残効は長いが、クワコナカイガラムシに効果が低い。新成虫の飛来がある場合には、飛来に応じて他害虫と同時防除できる殺虫剤を選択する。この時期は農薬の適正使用基準(収穫前日数、年間使用回数)を、特に早生種に配慮して薬剤を選択する。
(3) 被害の軽減
開花期に成虫が多く見られた場合には、摘花作業を行わず、被害がわかってから摘果作業を進めた方がよい。 |
|
12) リンゴサビダニ
これまであまり発生が目立たなかったが、近年各地で発生が見られるようになったので紹介する。本種はリンゴハダニやナミハダニが属するハダニ類とは異なる、フシダニ類に属するダニである。フシダニ類は寄生植物の範囲が狭く、本種はリンゴ属に寄生する。県内のりんご園に広く分布するが、本種による吸汁は被害が少ないので、特別に防除する必要はない。卵、第1若虫、第2若虫、成虫の発育段階があり、脱皮する直前にじっとして動かない静止期がある。雌成虫には二つの形態的に異なる型(第1雌、第2雌)がある。
ア 越冬
雌成虫(第2雌)が芽の鱗片や粗皮の下などの隙間に潜入して越冬する。
イ 形態
成虫は体長約0.2mm、体幅約0.07mmの細長いくさび形で、淡黄〜橙黄色をしている。脚は体の前方に2対(4本)ある。
ウ 発生生態
越冬後の活動は発芽に伴って4月上旬ころから始まる。発生が多くなるのは5月下旬〜6月上旬ころからで、果そう葉を主体に6月下旬ころまで増殖する。その後、新梢や徒長枝の伸長に伴って若くて軟らかい葉へ移動しながら増殖し続け、7月から8月上旬に最盛期となる。越冬態の第2雌は7月ころから出現し始める。
エ 加害様相
本種の寄生はハダニ類が見えないにも関わらずハダニ類が加害したような症状が進行することで気づくことが多い。本種は葉の裏表に寄生し、吸汁加害する。新梢先端部などの展開中の若い軟らかい葉を好むが、硬くなった葉にも寄生する。軟らかい葉に寄生すると、葉全体が褐変して縁から湾曲する。硬い葉に寄生すると、表側が鈍い銀白色(鉛色)になり、銀葉病に類似した症状を示すことがある。果実には加害しない。 |
|
13) コンフューザーAによる主要害虫の同時防除
交信撹乱剤「コンフューザーA」はりんごの主要害虫であるキンモンホソガ、ナシヒメシンクイ、ハマキムシ類、モモシンクイガの性フェロモンを含んでいる。本剤を園地内に充満させることで、対象害虫の成虫の交尾を連続的に阻害し、次世代の発生を抑制する。そのため、慣行防除に本剤を併用することで、対象害虫に対する防除効果が高まる。また、効果は約3〜4か月持続するので、対象害虫の発生密度が低い場合には殺虫剤の削減も可能である。本剤の対象害虫はキンモンホソガ、ナシヒメシンクイ、リンゴコカクモンハマキ、ミダレカクモンハマキ、リンゴモンハマキ、モモシンクイガであるが、アトボシハマキにも有効である。しかし、トビハマキには効果が低い。コンフューザーAやハマキコンなどの交信撹乱剤は対象害虫のみに作用し、人畜、蚕、水生生物、訪花昆虫、天敵などに対する影響や作物残留の心配がまったくなく、近年、環境保全型の防除資材として注目されている。
豗 使用方法
本剤はリンゴコカクモンハマキ越冬世代成虫の発生前の5月下旬-6月上旬に取り付ける。枝などにひとひねりして固定するが、食い込みを避けるために枝との間に余裕を持たせる。10a当たり150〜200本を目通りの高さに7割、残りを樹の上部に取り付ける。園地全体に均一に取り付けるが、園地の周辺部と、傾斜がある場合は傾斜の上部に多めに取り付ける。また、周囲に雑木林がある場合は林地内にも取り付ける。使用後は剪定時などに回収し、処分する。
豩 利用上の注意
広い面積で処理するほど効果が高く、正方形に近い場合でも1ha以上が望ましい。急傾斜地や対象害虫の発生密度が極端に高い場合は使用しない。また、隣接園地の発生密度が高い場合も使用しない。対象害虫に対する殺虫剤の削減が可能であるが、そのためには対象害虫の発生密度、対象以外の害虫発生状況の観察が必要である。本剤を使用した場合は、ミダレカクモンハマキ対策のハマキコンは不要である。
豭 価格及び取付け時間
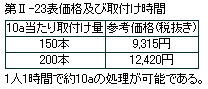 |