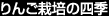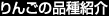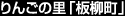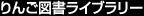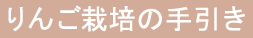|
| 8.授粉 |
|
現在、労力不足のためマメコバチの導入が多く行われている。マメコバチで授粉した場合の果実品質をみると、マメコバチの数が十分で天候が良いと人手による授粉との差がみられない。したがって、マメコバチで授粉する場合は蜂数を十分にし、しかも、適期放飼、花摘み、早期摘果に努める。なお、マメコバチの数が不十分な場合や、マメコバチを導入していない園、著しい不良天候が続く場合は人手による授粉が必要である。
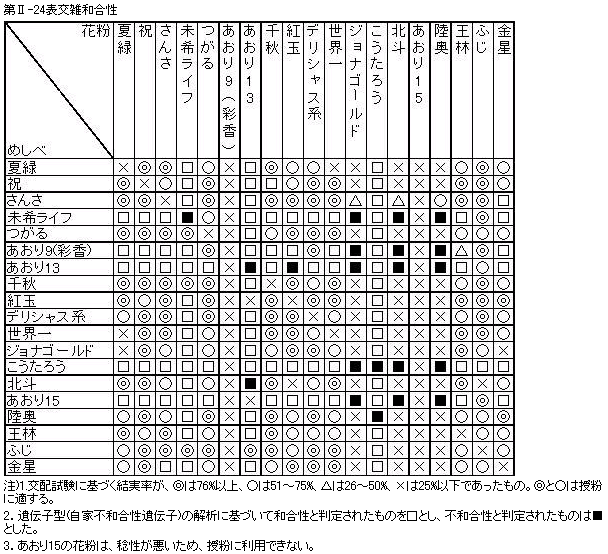 |
|
1)マメコバチによる授粉
マメコバチは花から花粉を集めて巣に運ぶ習性がある。柱頭や葯に接触する機会が多く、訪花数も多いので授粉能力が優れている。人畜に対する危害はない。年に1回、4〜5月に活動するだけなので、若干の配慮で農薬からの被害を回避でき、毎年同じ園で飼育できる。しかし、授粉範囲は比較的狭く、巣箱を分散・配置しなければならない。増殖に年数がかかるが、一旦飼育を始めると、年々増え続けるので、継続して利用できる。
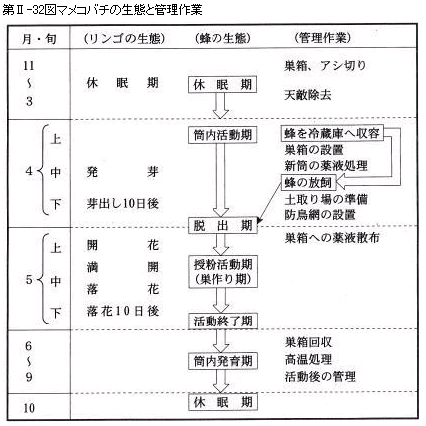 |
|
2) 人手授粉
(1) 授粉用の花粉選択
ア新しい花粉または貯蔵花粉を用いる。
イ対象の品種に対して交雑和合性の高い花粉を選択する。(「授粉」の項を参照)。なお、3倍体品種(陸奥、ジョナゴールド、北斗など)の花粉及び同一品種による授粉は行わない。また、北斗に対してふじと紅玉の花粉は結実率が低いので使用しない
(2) 花粉の調製
ア 花の採集
授粉予定日の2日以前に風船状から開花直後の花を採集する。採集量の目安は20〜30a分で約1手篭である。
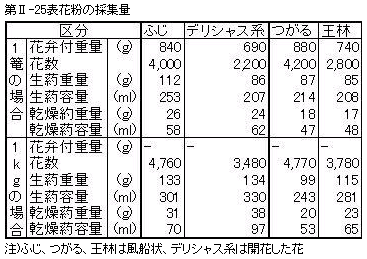
イ 葯落し
葯落し機を利用して花から葯を落し、3mm目の金網で葯だけをふるい落とす。なお、濡れた花を採集した場合は網袋に入れ、脱水機で水切り後に葯落しをする。また、ふるい落とした葯をすぐ開葯にまわすことができないときは、葯が蒸れるのを防ぐために紙などの上に広げておく。
ウ 開葯
開葯器を利用し、湿度を80%以下に保ち、温度20〜25℃で1〜2日間加温して開葯させる。この際、容器に約を厚く重ねないように注意する。
エ 花粉の発芽検定
(ァ) 寒天培地を作る(寒天1g、しょ糖10gを水100mlに入れ、かくはんしながら熱をかけて寒天を溶かす)。
(ィ) スライドグラスに滴下し、発芽床を作る。
(ゥ) 寒天培地が冷えて固まったら、綿棒や筆などを使って花粉を均一に分散するようにまく。なお、貯蔵花粉の場合は必ず前もって吸温させる。
(ェ) 浅く水を入れたシャーレにスライドグラスを移し、蓋をして約25℃の恒温器に3〜4時間入れる(スライドグラスは水の中に入らないように台の上にのせる)。
(ォ) 恒温器からシャーレを取り出し、顕微鏡で発芽状態を調べる。なお、シャーレから取り出した発芽床に染色固定液(コットンブルー0.5gを乳酸100mlに溶かし、水を加えて2倍に薄める)を吹き付けると検鏡しやすく、また発芽管の伸長が停止するため、いつでも都合のよい時に調べることができる。
オ 花粉の希釈
(ァ) 花粉は発芽率にあわせ、下表の基準によって石松子で希釈するが、悪天候の時は花粉の割合を基準より多くする。
(ィ) 授粉器などに使用する場合は約殻付花粉と石松子を混ぜながら80メッシュのふるいにかけて空になった葯を取り除く。
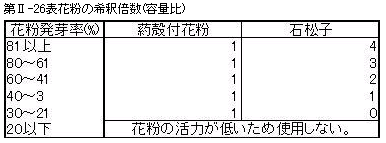
カ 花粉の保存
花粉をすぐ授粉に使わない場合は、密閉容器に乾燥剤と一緒に入れて冷暗所に保存する。これで当年使用の場合は発芽率がほとんど落ちない。なお、乾燥剤なしで室温放置した場合は5日以内なら発芽率があまり落ちないので使用できるが、それ以上放置したものは使用しない。
(3) 授粉の方法
ア 綿棒主体による授粉・・・・・・最も確実な授粉方法
(ァ) 中心花を主体に授粉し、早く咲いた花から順次行う。もし、中心花が霜などの災害に遭った場合は健全な側花に、また、中心花の素質の悪いものは側花の最も良いものに授粉する。めしべの受精能力は開花後4〜5日はあるので、降雨で葯が褐変した花でも授粉を実施してもよい。
(ィ) 不良天候の場合は、晴天時より2〜3割多めに授粉する。
(ゥ) 長く雨が続く場合、雨天でも授粉を実施する。
(ェ) 綿棒類は1回の花粉づけで20〜30花くらい授粉できるが、強風や降雨の場合は10〜20花程度とする。
イ 交配器による授粉・・・・・・ピストル型やプラスチック製の交配器がある。
綿棒類に比べて能率は上がるが、確実さがやや劣る。
(ァ) 花粉容器に1/2〜2/3くらい入れる。
(ィ) 花そうあるいは枝をねらって授粉する(綿棒の約3倍の能率)。なお、一花一花ねらってやると綿棒にやや近い結果を得ることができるが能率はやや劣る。
(ゥ) 授粉の時期は中心花5分咲きと満開時の2回とする。もし、綿棒類主体の授粉と併用する場合は、中心花5分咲き時に綿棒類で授粉し、満開時に交配器で授粉する。 |
|
3) 花粉の長期貯蔵
花粉の寿命は環境により大きく支配され、自然状態に放置すれば高温、高湿の条件下では約1週間、低湿の条件下でも約4週間で生命力を失う。花粉を長期間貯蔵するには、特に湿度に注意し、できるだけ低温、低湿に保つようにする。
(1) 貯蔵花粉の条件と包装の仕方
貯蔵用の花粉は開約したできるだけ新しいものを用いる。また、貯蔵前に必ず発芽検定を行って、発芽率が高いほどよいが少なくとも60%以上のものを貯蔵する。花粉の包装は通気性のある紙袋を使用し、一つの包装を200g以上にしない。
(2) 貯蔵方法
デシケ一夕を用い、すりあわせ部分にはワセリンを十分塗布し、密封できるようにする。また、外気としゃ断できる容器、例えば茶筒などでもよい。ただし、この際は蓋はビニールテープで密封する。
(3) 貯蔵容器内の乾燥剤
乾燥剤の種類・・・・・・シリカゲル(濃い青色)
乾燥剤の量・・・・・・容器に入れる花粉の量、花粉の水分含量によって異なるが、葯付き乾燥花粉と等量くらいの乾燥剤を入れると安全である。
(4) 貯蔵中の温度
翌年の開花期まで貯蔵する場合は低温ほどよく、家庭用冷蔵庫などでもよい。
(5) 貯蔵中の湿度
貯蔵中少なくとも数回にわたって、容器中の湿度が完全に低湿になっているかどうか点検する。シリカゲルは青色のものを使用した場合、吸湿すると青色から淡いピンク色に変わるので確認しやすい。シリカゲルが淡いピンク色になりかけたら青色のものと取り替える。なお、吸湿したシリカゲルは青色になるまで熱を加えて除湿すると何回も使用できる。 |