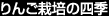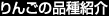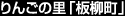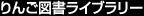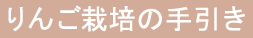|
| 3.栽植 |
|
1) 樹列方向
わい化栽培では一般に並木植えにするが、この際の樹列方向は、南北とする。傾斜地は等高線植えとするが、スピードスプレーヤが登れる程度の傾斜では平坦地と同様に南北の樹列方向が良い。 |
|
2) 裁植距離
M.26、M.9A、M.9EMLA台使用の場合は、列間4m,樹間2mを基本とする。なお、この応用として3列植えもあるが、この様式では中央の列の樹は大苗育成用とし、果実が本格的に成り始める前に掘り上げ、最終的には1列植えにする。
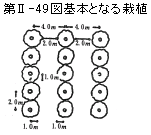 |
|
3) 混植
自然結実率を高めるために、2〜3列に1列ぐらいの割合で異品種を混植する(「栽植」及び「授粉」の項を参照)。 |
|
4) 植え穴
植え穴はスクリューデガーで直径60cm、深さ60cmの大きさにするか、バックホーで幅60cm、長さ1m、深さ60cmの大きさにする。また、バックホーを利用する場合は幅60cm、深さ60cmの連続した帯状にしてもよい。しかし、心土破枠など土壌改良の不完全な園地では幅90cm、深さ60cm程度の大きさの植え穴をつくる。なお、機械掘した場合、植え付け前にスコップ等で穴の壁面を膨軟にする。改良資材は、直径60cm、深さ60cmの植え穴の場合、堆きゅう肥10kg、溶成リン肥0.7〜1.0kg、苦土炭カル0.3〜0.5kgを土壌と混合して施用する(「土壌改良、植え穴の改良」の項を参照)。 |
|
5) 支柱
わい化栽培では永久的に支柱が必要である。その理由は、わい性台樹は浅根性のため強風による倒状が起こりやすいこと、主幹が軟弱なために積雪や果実の重みなどで湾曲しやすいこと、接木部がもろく折損しやすいことなどの弱点を補強したり、枝の誘引、吊上げに利用するなど多くの役割を果すためである。支柱の立て方には、1樹ごとに独立した形で立てる1本支柱方式とそれぞれの支柱を張線で連絡するトレリス方式がある。1本支柱方式は、①樹が高くなると支えきれない、②多雨を伴う強風に弱い、③地盤が軟弱な園では倒状しやすいなどの問題がある。一方、トレリス方式は強風に対しては1本支柱方式より強いが、地形が複雑で起伏の激しい園や小規模な園では施設費が割高になるなど問題がある。どちらの方式を採用するかは、それぞれの園地の状況をよく把握して判断する。
(1) 1本支柱式
ア 支柱の種類
現在市販されている1本文柱には鋼管支柱、木製支柱などがある。強度、耐用年数、価格を考慮して適正な支柱を選ぶ必要がある。
(ァ) 鋼管支柱
支柱の強度、耐用年数は外径、肉厚、亜鉛の量によって異なるが強度を考えた場合外径30mm以上、肉厚0.9mm以上のものを使用する。なお、耐用年数は亜鉛付着量が多いほど長くなる。鋼管の腐食が激しいものは地際からの折損が多く、倒状につながるので必ず防錆加工したものを使用する。
(ィ) 木製支柱
現在出回っている木製支柱の樹種はスギ、カラマツ、マツ、ヒバなどがあり、これにクレオソート、ペンタグリーンなどの防腐薬剤を高圧注入したものが耐用年数が長い。木製支柱では製材したものは丸太より強度が落ちるので、できるだけ丸太を使用し、末口の太さが5cm前後のものを使用する。また、木製支柱は誘引、枝つりなどの作業性に富んでいるので利用価値が高い。
イ 支柱の長さ
3.5m〜4mとする。
ウ 打ち込み
地下70〜100cm入るように打ち込むことを原則とする。もし、下層に礫があって打ち込みが困難な場合、あるいは下層が砂れきや浮石などで支柱の安定性がよくないときは根かせをつける。棒状の1本根かせを使うときは風の方向に平行になるように設置する。
(2) トレリス方式
支柱の立て方や材料は園地の形、入手した材料の種類によって様々であるが、その要点は次のとおりである。樹列の両端に丈夫な柱(隅柱)を立て、樹列に沿って10〜20mおきにやや丈夫な柱(中柱)を立て、これを2〜3条の張線(上と下の線の間隔約1m)で連結し、中柱ごとに樹列方向と直角に1〜2条の張線で連結する。そして個々の樹には主幹を真直ぐに伸ばしてゆける程度のやや細めの支柱(既に1本文柱方式を行っており、それをトレリス方式に変える場合は既存の支柱をそのまま利用)を立て、支柱の上部を張線と結合する。隅柱や中柱としては直径50〜60mm程度の鋼管や木製支柱(防腐加工したもの)及び古電柱などが使われている。隅柱や中柱は丈夫で、しっかり固定する必要があり、特に隅柱は補助柱やアンカーなどを使ってしっかり固定する。
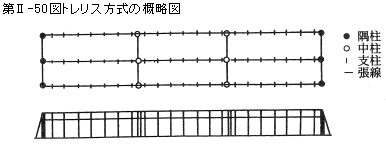 |
|
6) 定植
生育の良い苗木を植えるが、その場合、苗木養成固で1〜2年肥培した2〜3年苗を定植した方がよい。マルバ台つき苗木は、そのまま定植すると樹勢の不揃いや高接病の発生が懸念され、針金を巻いて定植すると紋羽病を誘発する恐れがある。したがって、マルバ台部分は切り落として定植することを原則とする。なお、わい性台木部分から十分発根していないため、やむなくマルバ台をつけたままで定植する場合でも、栽植距離や様式はわい性台白根苗木に準じて行なう。また、植え付けの際は、穂品種の接木部位は地表面より20cm程度出るようにするが、マルバ台付きでは浅植えとならないように注意する。苗木は植え付けの際に必ず消毒する。
(1) 定植の時期
津軽地方では一般に秋植えの方がよい。春植えでも4月中旬頃までならよい生育を示すが、春期は他の作業との競合などで栽植が遅れがちになるので注意する。県南地方では土壌凍結があるので春植えとする。なお、秋植えの場合は次の点に注意する。
ア 暖地産の軟弱な苗木及び早掘りした苗木は冬期に凍害を受けやすいから、植付け後に紙などで被覆する。
イ 排水不良地では植え穴に集水があるため、秋植えすると湿害を強く受けやすいので排水対策を十分に行なってから栽植する。
ウ 雪害、野ネズミ、野ウサギの対策を十分に行う。
(2) 定植のやり方
苗木の植付けは次の図に示した手順で行う。
第Ⅱ-51図苗木の植え方の手順
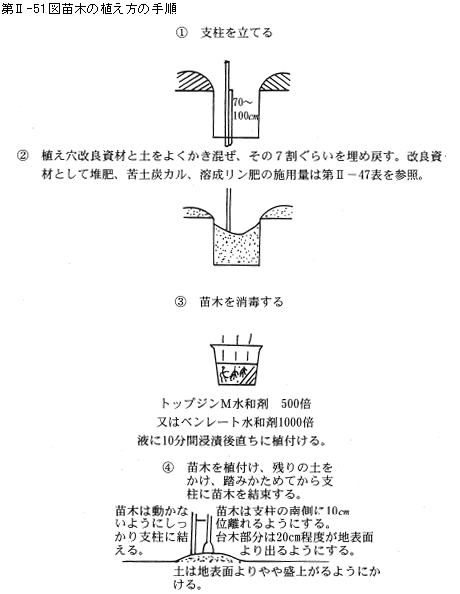 |