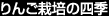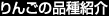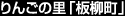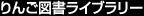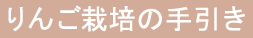|
| 5.��ʍ͔|�Ǘ� |
|
| �i��\���A�a�Q���h���A�����A�E�ʁA���F�Ǘ��͕��ʍ͔|�ɏ�����B |
|
1)�@�y��Ǘ�
�킢���͔|�̊�{�I�ȓy��Ǘ��@�͎���Ԗq�������A���������k�̕��������͔|�ł���B
(1)�@���������̂���
�������͐��k�Ƃ��A����Ԃ͑����Ƃ���B����������͎������֕~�v����B
�A�@����ԑ���
�u�����͔|�v�̍����Q�ƁB
�C�@���������k
���k�Ə����܂𗘗p���Đ��k���ێ�����(�u�����܂̗��p�v�̍����Q��)�B
(2)�@�L�@���⋋�ƐΊD���엿�{�p
���t�A��������10a������600kg���x�̑͂��イ��ƐΊD���엿(��y�Y�J����10a������100kg���x)���{�p���A5cm���x�̐[���Ōy���k�N����B
(3)�@�����h�~
�킢������͍��邪�A�����̉e�����Ղ��̂ŁA�������₷�����n(���I�y�̌�����쌴�n�т�ΎR�D�y��A�X�Βn�y��)�ł͎��̑���s���B
�A�@����}���`�̗��p
���𒆐S��2m�l����16kg(4kg/�u)�̈�����}���`����B
�C�@����
�{�݂𗘗p���������@�Ƃ��Ă͓_�H�����@���L���ł���A�ߐ��݂̂Ȃ炸�A�킢���͔|�̍͐A�l���Ƀ}�b�`�����������ł���B�������f������@�Ƃ��ẮA�e���V�I���[�^�[�����p����̂��ł��֗��Ŋm���ł���B�e���V�I���\�^�[��������80�`100cm���ꂽ�[��30cm�̈ʒu�ɖ��݂��Ă����A���x��������600cm(pF2.8)���������炩���n�߂�B�e���V�I���[�^�[���Ȃ��ꍇ�́A���V������ڈ��ɂ��āA2�T�Ԉʖ��~�J��Ԃ��������炩����B1��̂��ʂ�20mm(1m2������20l)���x�Ƃ���B |
|
2)�@�{��
10a������̎{��ʂ͕\�̂Ƃ���ł���B
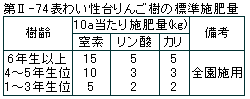
�Ȃ��A�W���{��ʈȊO�̎����́u�{��v�̍����Q�ƁB |
|
3)�@��������̑�
(1)�@�͔�}���`�y�єA�f�̗t�ʎU�z���s���B�͔�}���`�͊��𒆐S��1m�l��(1m2)��30kg�{�p����B�J�Ԓ��O����6�����{�܂ŔA�f�̗t�ʎU�z(��10l������A�f20g)��3�`4��s���B
(2)�@�ږؕ��ʂ������A�C�����̑��������O�������ɂ͐ږؕ��ʂ�10cm���̍����܂Ŏ������S�ʂɐ��y������B���łɋC�������������Đ��サ�Ă�����ɂ͎��̂悤�ȑ�̂����ꂩ���u����B�ӂ��̎}���i��Ƒ�ɋ��ڂ������A��ؕ����Ɉꎞ�I�ɐ��y������B�ӂ���ڂ�M.26��̕c���i��Ɋڂ�����B�Ȃ��A��i�핔���͎���������܂Ő�Ԃ���������߂ɍs���A���ʗʂ������ĔA�f��t�ʎU�z����B
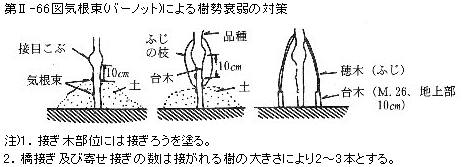
(3)�@�ږڂ���(�ږؕ��̑���)���o�Ă��Ď�������ƂȂ��Ă���ꍇ�́A���ڂ�(�ӂ��̎})��ڂ�(�ӂ�/M.26)������B�Ȃ��A�n�㕔�̎戵���͋C������ɏ�����B |
|
4)�@���n
�킢������̉ʎ��M�x�́A��ʂɕ��ʑ�����5�`7�����炢���܂�̂ŁA4���ȍ~�܂Œ�������ꍇ�͕��ʑ������⑁�߂Ɏ��n����B |
|
5)�@�ЊQ��
(1)�@���Q��
�킢���͔|�͑��Q�ɑ��ē��ɔ�Q���邱�Ƃ��\�z�����B�~�����\�z���ꂽ��h�~����u����K�v������(�u�ЊQ��v�̍����Q��)�B
(2)�@��Q��
�킢���͔|�͐�Q�Ɏア�̂ŁA��Q�ɋ������`����邱�Ƃ���Ȃ���łȂ��A���ꂼ��̉��n�̐ϐ�ʂɉ����āA�ϐ�O���͐ϐ���Ԓ��̑K�v�ł���B
���N�̍ō��ϐ�[1m�ȉ��F3�N�����܂ł̗c�؎���ɂ͎}��K����������B����N���l������ƌ������}�����������悢�B
���N�̍ō��ϐ�[1.5m�����F�������}�����ő傫�Ȕ�Q�͖Ƃ꓾�邪�A���ɐ�̑����N�ɂ͖x�グ�A�r��A���ł߁A�Z��U�z�Ȃǂ̑���Ď��{����K�v������B�������}���Ȃ��ꍇ�ɂ͂����̑�̕K�v�x����w�����B
���N�̍ō��ϐ�[1.5m�ȏ�F�������}�̂ق��ɖx�グ�A�r��A���ł߁A�Z��U�z�Ȃǂ̑����قƂ�ǍP��I�ɕK�v�ł���B
�Ìy�n���̂���ɂ�����ō��ϐ�[�͉��\�̂Ƃ���ł���B
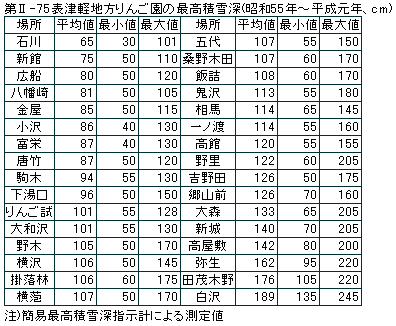
�Ȃ��A�����ɂ�����ϐᕪ�z(���ύŐ[�ϐ�)�͐}�̂Ƃ���ł���B
��1m�ȉ��̒n��
�Ìy�n��ł͕��꒬�A�O�O�s�ΐ�𒆐S�Ƃ������암�A����n��ł͎��˒��A�c�q���Ȃǂ����Ԑ��̑����m���ł���B
��1�`1,5m�̒n��
���쌴�s�A�����A�Q�����̕��암�A��؎R�[�y�ѐX�s���Ȃǂł���B
��1.5m�ȏ�̒n��
���ډ����A�O�O�s�퐶�A���P���������Ԋ�؎R�[�A�Q�����ז�A�Q���_���A�g�X��`�A�X�s�c�Ζؖ�����Ԕ��b�c�R����n�тł���B
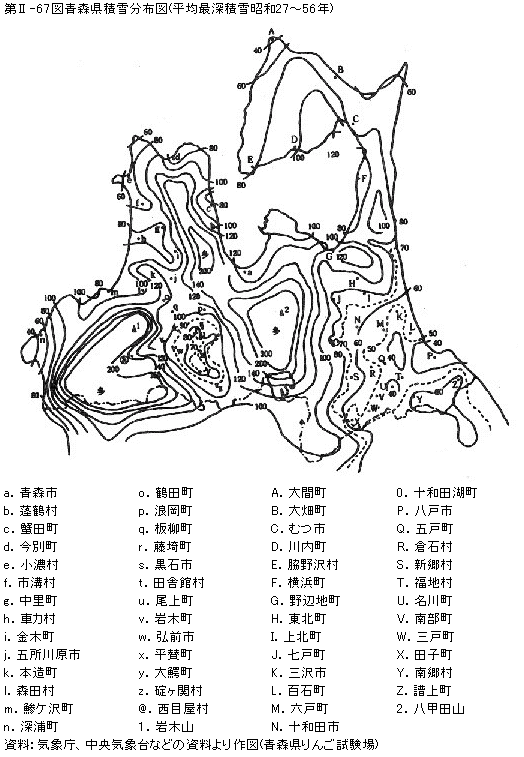
�A�@���}�����̑�
(�@)�@����n�тł̌������}�̎��{
���̒n��̐ϐ�ɉ����A�ᒆ�ɖ��v����Ǝv����}�ɂ��ĕK���������}���s���B
(�B)�@�劲��������B
�劲�̉����������������萊�シ��̂�h�����߁A����ɉ����ĐؕԂ���x���ւ̌������s���B
(�D)�@�����Z������B
�劲���甭�o���鑤�������Ɛ܂ꂽ����肷��̂ōʼn��ʂł�85cm�ȉ��ɂƂǂ߁A����ȏ㒷���Ȃ�����ؖ߂�������B
(�F)�@����p�x�̍L���}�𒅂���B
�ؕԂ��t�߂��甭�o�����悤�ȕ���p�x�̋����}�͐�Q�Ɏア�̂ŕ���p�x�̍L���}�𒅂���B
(�H)�@����̕����L���Ȃ��B
���}����̕��}�𑽂����ĉ������L����ƁA��Q���₷���̂ŕ��}�����Ȃ����A�������傫�����Ȃ��B
(��)�@����̐������Ȃ��Ɛ�Q���₷���̂ŁA�ڕW�̑����m�ۂ���B
�C�@�ϐ�O�̑�
(�@)�@�c�̌���
���A��Ȃǂ�2�`3�����x���𒆐S�Ɍ�������B��������̂Ȃ��悤�ɒ��ӂ���B
(�B)�@���̎}�݂�
�}���ł��Ȃ��Č������ł��Ȃ��ꍇ�͎}�݂������B�������A�}�̒������Ő����p�x�ɒ݂�ƒ݂����Ƃ��납��܂��̂ŁA����̕������}�悪������ɂȂ���x�܂Œ݂�グ��B
�E�@�ϐ���Ԓ��̑�
(�@)�@�Z��̑��i����ђ��~�͂̌y��
2����{����3����{�ɂ�����2�`3��ɂ킽��A���V�̓���I��ŗZ��܂��U�z����B
(�B)�@�}�̌@��グ
���v�����}��ᒆ����@��グ����A�a��Ȃǂ��s���B
(�D)�@��̓��ł�
�ϐ�[��70�`80cm���炢�ɂȂ����牺�}�����̐�ł߁A���̌�90cm���炢�ɂȂ�����Ăѓ��ł߂�B
(3)�@���Q��
�킢���͔|�͕��Q�Ɏキ�A���a56�N�䕗15���y�ѕ���3�N�䕗19���ɂ��傫�Ȕ�Q������ꂽ�B�J���ɓ������Ă͖h���і��͖h���_�̐ݒu����{�ƂȂ邪�A�J����ł����Ă������h���{�݂̓������K�v�ł���A�܂����̓_�ɂ����ӂ���B
�A�@�劲�Ǝx���̌����͑ϋv�͂̂���ޗ��ōs���A�K��2�`3������������B�����ޗ��͖��N�_�����A�キ�Ȃ������͎̂��ւ���B
�C�@�����傫���Ȃ�A�����������Ȃ�ƕ����ɑς�����Ȃ��Ȃ�̂ŁA�V���������x���͎��ւ���B�܂��A�|�ǎx���ł̓��b�L�h�����Ƃꂽ��핢�ނ��������肵�ċ��x�A�ϋv�����キ�Ȃ�̂Ő����_�����A��C�܂�h�邩�h�I�e�[�v�������B
�E�@���ݎg�p���Ă���x���̑ł����݂��A������ꍇ�͍ēx�ł����ނ��A�ł����݂�����ȏꍇ�͎���ɉ����Ďx���̒����ɒ������A����ɉ��Ԃ��h�~���邽�߂ɒ��p�Ɍ�������悤�ɒ������|���h�~���s��
�G�@�劲�㕔�̑����傫�������A������3m�ɗ}����B
(4)�@��l�Y�~�A��E�T�M��
�Ƃ��ɎR�ԕ��ł͂����̔�Q�͐[���ł���B��l�Y�~��Ƃ��Ă͎E���܂�ߊl��ɂ�閧�x�̒ቺ�A���Ɋ����܂̓h�z����ԂȂǂ̊���������̋ᖡ�Ƒ��̊�����A�ӏH�̒n�ە��̐��k�ȂǑ����I�Ȗh���K�v�ł���B��E�T�M�ɑ��Ă͊J�����ɉ��n�̊O�������Ԃň͂߂Δ�Q�͂Ȃ����A�J����͐₦�����Ԃ�_�����Ĕj���ӏ��͕�C����(�u���b�Q��v�̍����Q��)�B |